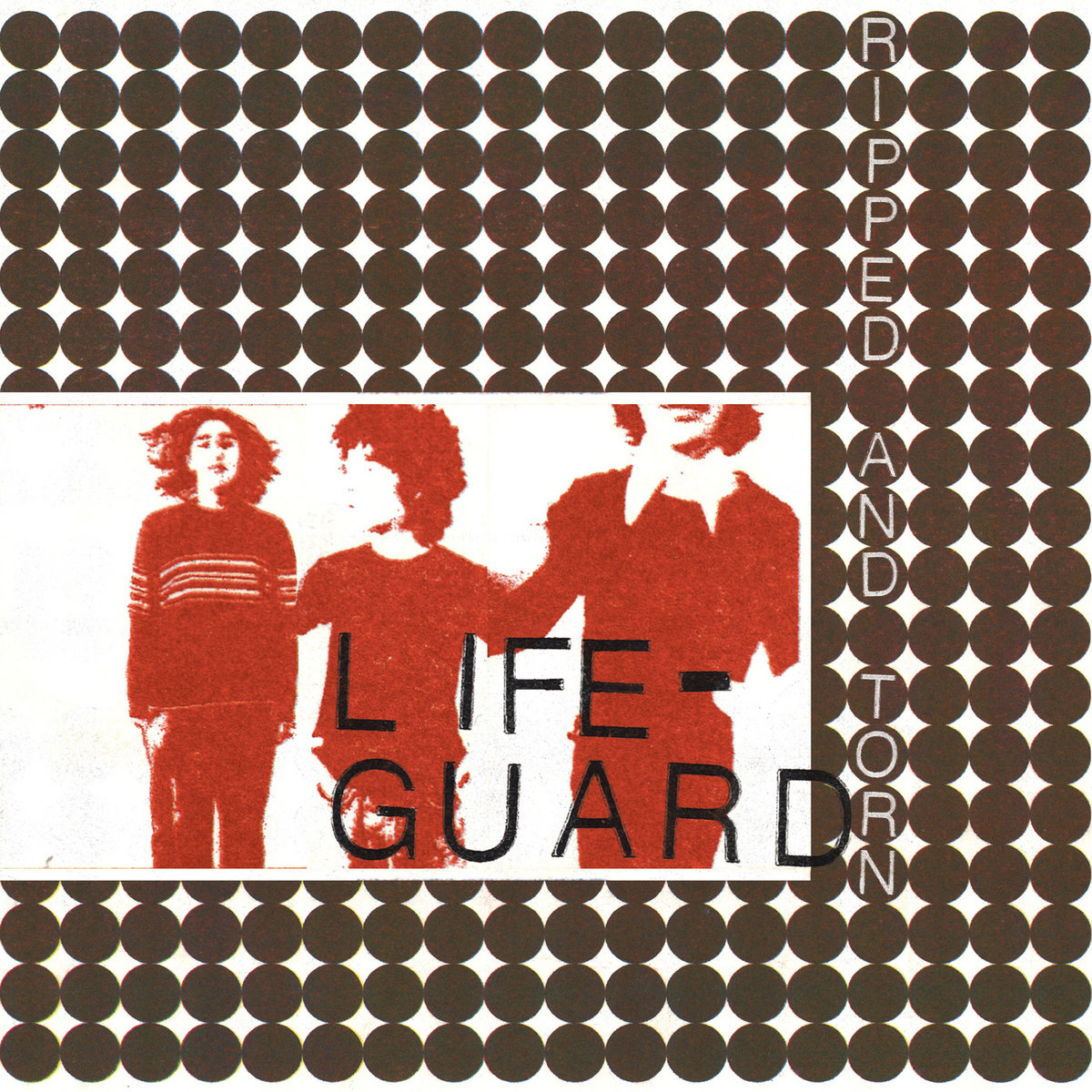Elliot Smith
エリオット・スミスは、アメリカではインディー系のアーティストとしては、異常なほどの人気を誇るミュージシャンである。それは一つ、彼の音楽性の本質的な良さというものの背後に潜んでいる悲しき運命も、彼の人気を後押ししていると思われる。彼の生み出す楽曲に明瞭に表れているのは、いわゆるアメリカのインディー・ロック/フォークの系譜を真っ当に受け継いだストレートな音楽の持つ魅力である。
また、彼の音楽は非常に静かで昂じるようなところがない。それはもちろん、アコースティックギター一本で奏でられる本格派のフォーク・ロック/ポップスだからだけれども、さらにエリオット・スミスのボーカル、声というのは一貫して明るさはなく、どんよりとした印象が滲んでいる。
自分の中にある暗く淀んだ感情をしかと直視し、それをゆるい感じフォーク音楽として何気なく表現する。彼の音楽は、ディランのような張りこそないものの、素晴らしいポップセンスがあり、いまだに不思議な魅力を放ちつづけている。
つまり、それがインディーロックの系譜にあるローファイ、サッドコアという音楽ジャンルの本質なのだろうか?
しかし、エリオット・スミスは、その全生涯の作品において、その自分の中の暗さの最中でもがき苦しみ、そこからどうにか這い出ようと努めていたように思える。これは信じられないことに、実は、グランジのカート・コバーンの芸術性と本質的には一緒なのかもしれない。
つまり、グランジは、苛烈なロックンロールの申し子として、そして、ローファイ、サッドコアは、インディー・フォークの静かなる後継者として、この2つの音楽は、八十、九十年代のアメリカのアンダーグラウンドシーンに在し、アメリカの若者たちの魂を癒やしつづけたのだろう。
エリオット・スミスは、「Kill Rock stars」というインディー・レーベルからデビューを飾り、このレーベルを中心に活動をしていたミュージシャンである。当時、つまり、リアルタイムの80年代後半、九十年代において、アメリカで、どれくらいの人気が獲得したのかまではあまり知らない。
しかし、その音楽的な素朴な良さというのは、普遍的な価値があり、少なくとも、2000年代に入っても全然古びることはなく、多くのアメリカ人の共感を呼び続け、今では彼の知名度、人気だけが一人歩きをしている感がある。それは、彼の音の表現には普遍的な人間の弱さ、誰にも存在する内的な暗さに、そっと寄り添う慈しみが込められているからなのだろうと思う。
今ではすっかり、アメリカのインディー・ロックの大御所というように目されるようになったエリオット・スミス。もし、今でも健在であったら、どのような素晴らしい音楽をファンの元に届けてくれたのだろうか。
2000年代初頭、正確に言えば、2003年の10月21日、エリオット・スミスは、胸に刺し傷がある状態で、自宅で発見された。当時の恋人による他殺説もあるが、現在では、自殺という説が最も有力視されている。
そして、彼の不可解な死は、毎年10月になると、ミュージックシーンの話題に上ることがあり、同アメリカの伝説的ミステリー作家アラン・ポーのように、いまだ多くのベールに包まれ、様々な憶測を呼びつづけている。
「Either/or」 1997 Kill Rock Stars
TrackLisiting
1.Speed Trails
2.Alameda
3.Ballad of Big Nothing
4.Between the Bars
5.Pictures Of Me
6.No Name No.5
7.Rose Parade
8.Punch And Judy
9.Angeles
10.Cupid Trick
11.2:45 AM
12.Say Yes
所謂、エリオット・スミスの代表作、最高傑作として一番良く知られている作品である。個人的にはこのアルバムを十年前くらいに購入したが、当時、どことなく地味な印象があったためか、それほど深く聴き込まなかった覚えがある。まだ、この渋さのある音の本質がいまいちつかめなかったのかもしれない。
当時としては、かなり陰鬱な印象をうけたからか、いくらか倦厭するような向きがあったものの、それは大きな思い違いだったのだ、と、自分の耳の過ちを認めるよりほかない。現在、あらためて聴き直してみたところ、やはり、良質で素晴らしいインディーロック/ ポップスで、これほど痛快なフォーク・ロックは見当たらない気がする。どことなく、ビック・スター、マシュー・スイートの後の世代のアメリカのインディー・ロックの後継者という感じであり、しかも、同時に、ビートルズのような親しみやすい普遍的なポップ性も兼ね備えているのが特徴といえる。
このアルバムを、当時はインディー・ロックというジャンルを知るために聴いたような部分もあったけれども、再生能力の高いオーディオでじっくり聴いてみると、彼の音楽の本質が何となく掴むことができた。
そして、何と言っても、このアルバムは、インディー・レーベルからのリリースでありながら、非常にみずみずしい質感に彩られた上質な作品である。アコースティックギターの音の粒のようなものが非常にあざやかであり、また、あたたかみのある弦楽器としての魅力が凝縮されている。
そして、エリオット・スミスの作曲というのは、渋みあるアメリカンフォークの系譜を引き継いでいる。そして、それをいくらかスタイリッシュさをまじえて表現しているあたりがこのアルバムの本質かもしれない。
アルバムの全体の印象としては、やはり、からりとした明るさはないと思う。しかし反面、その要素が多くのファンから支持を受ける理由でもあると思う。派手さこそないものの、親しみやすさがある。言い換えれば、純朴さ、素朴さというのがエリオット・スミスの音楽の魅力なのかもしれない。
「Speed Trials」 「Between the Bars」「Punch and Judy」といった楽曲には、エリオット・スミスらしい内省的で繊細なポップセンスが感じられる。また、サイモン&ガーファンクル、ビック・スターの音楽性からの影響を感じさせる「Rose Parade」「Alameda」といった楽曲では、フォーク寄りのアプローチを図っている。表面的には、フォーク音楽の系譜にあるのだけれども、そこに、エリオットらしい、どことなく暗澹とした情感が込められている気がする。
また、そこには、男としての弱さ、というのも明け透けに表現されている。強いばかりが人間ではない、弱さを見せたって構わないのだというのは、マッチョイズムの支配するアメリカ社会の息苦しさがいかほどに深甚なものなのかを端的に表しているように思える。
つまり、エリオット・スミスの音楽は、アメリカ人としての健全さだとか一般的な価値観からはずれてしまった人々を救い上げるような温かみが込められている。これは日本人にはよく理解しえない概念かもしれないと思われるが、全く関係のない話ではないように思える。果たしてここ、日本にも、健全とされる概念が全然蔓延していない、と断言しきれるだろうか。だとすると、これは、非常に現代的なフォーク、真の意味でのヘヴィな音楽ともいえる。これらの複雑に絡み合った要素が、エリオット・スミスの親しみやすいポップソングとして昇華されているから、今日まで、この作品がアメリカのインディーロックの傑作として語り継がれているように思える。
そして、このアルバム「Either or」で最も素晴らしい曲は、最終トラックとして収録されている「Say Yes」ではないかと個人的には考えている。ここで、エリオット・スミスは、インディー・ロックという表面的ベールを剥ぎ取り、素晴らしいポピュラー音楽のシンガーソングライターとしての才覚を遺憾なく発揮してみせた。これから、どのような素晴らしい作品が聴けるものかと多くのファンが期待した矢先の生命の断絶であり、あまりに唐突な死であったように思える。