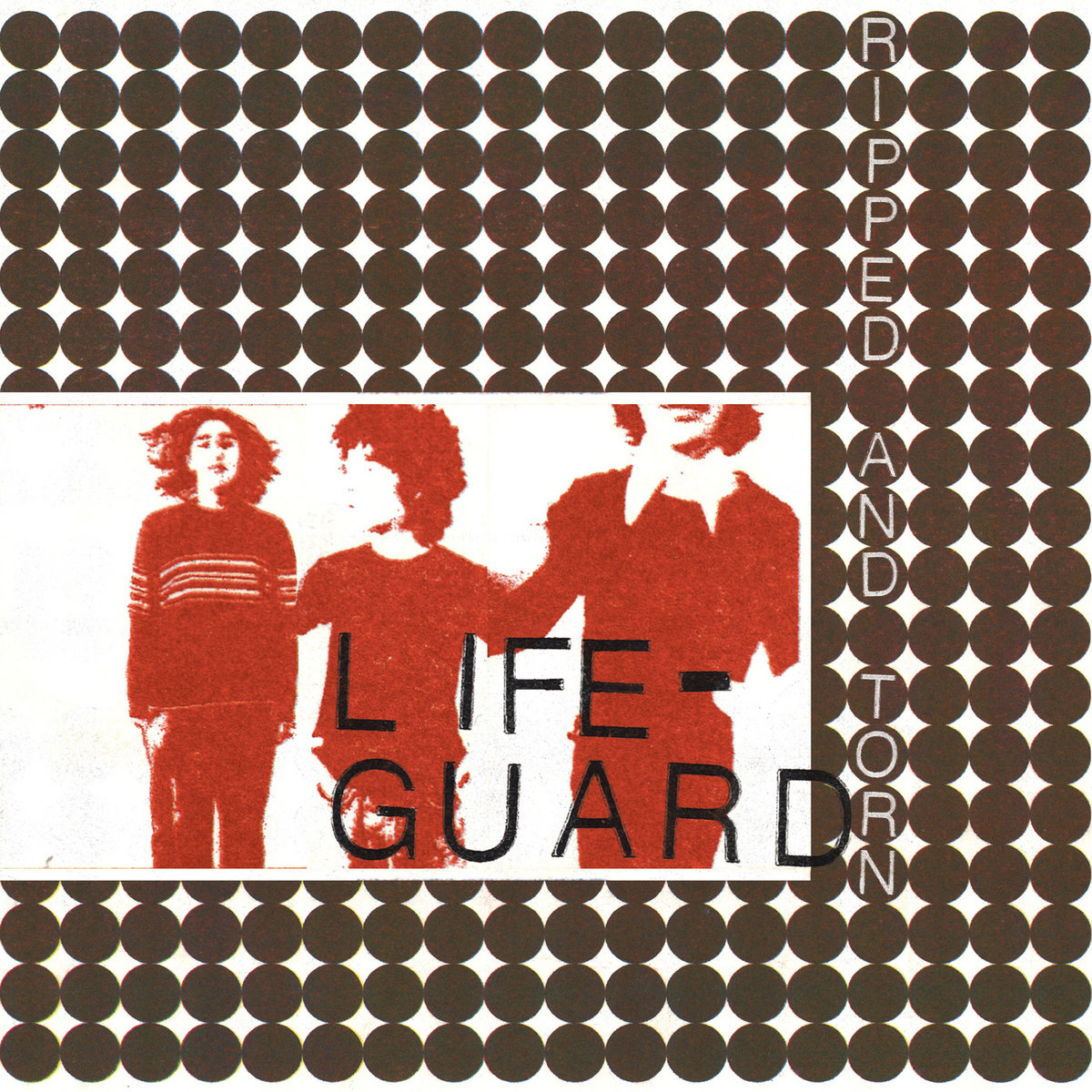|
現在ロサンゼルスを拠点に活動するローレル・ヘイローは、10年以上にわたってさまざまな町や都市に足を踏み入れ、一瞬、あるいはそれ以上の時間を過ごしてきた。彼女の新しいインプリントAweからのデビュー・アルバム『Atlas』は、その感覚を音楽にしようとする試みである。電子楽器とアコースティック楽器の両方を使用し、ヘイローは、オーケストラの層、モーダル・ハーモニーの陰影、隠された音のディテール、デチューンされた幻覚的なテクスチャーで構成された、官能的なアンビエント・ジャズ・コラージュの強力なセットを作り上げた。この音楽は、現実と空想の場所、そして語られなかったことを表現するための一連の地図として機能する。
Atlasの作曲過程は、彼女がピアノと再会した2020年に始まった。彼女はピアノの物理的なフィードバックと、感情や軽さを表現する能力を楽しんだ。翌2021年、パリの伝説的なCRMスタジオが彼女をレジデンスに招いたとき、彼女は時間を惜しまず、それまでの数ヶ月間に録音したシンプルなピアノのスケッチをダビングし、ストレッチし、操作した。2021年と2022年の残りの期間、ベルリンとロンドンを行き来しながら、ヘイローはギター、ヴァイオリン、ヴィブラフォンを追加録音し、サックス奏者のベンディク・ギスク、ヴァイオリニストのジェームス・アンダーウッド、チェリストのルーシー・レイルトン、ヴォーカリストのコビー・セイといった友人やコラボレーターのアコースティック楽器も録音した。これらの音はすべて、形を変え、溶け合い、アレンジの中に再構成され、そのアコースティックな起源は不気味なものとなった。
要するに、『Atlas』は潜在意識のためのロード・トリップ・ミュージックなのである。繰り返し聴くことで、暗い森の中を夕暮れ時に歩くような、深い感覚的な印象をリスナーに残すことができるレコードだ。そのユーモアと鋭い着眼点は、感傷的という概念を払拭するだろう。ヘイローの他のカタログとは完全に一線を画す『Atlas』は、最も静かな場所で繁栄するアルバムであり、大げさな表現を拒絶し、畏敬の念を抱かせる。
彼女の新しいレコーディング・レーベルからのデビュー・リリースにふさわしく、そのスローガンはアルバムのムードや雰囲気と類似している。畏敬の念とは、自然、宇宙、カオス、ヒューマンエラー、幻覚など、自分のコントロールを超えた力に直面したときに感じるものである。
『Atlas』/ AWE
 | |
カットアップ・コラージュとドローン/アンビエントの傑作
ローレル・ヘイローは、現行のアンビエント・シーンでも傑出した才覚を持つプロデューサーである。2012年のデビュー作で、会田誠の絵画をアートワークデザインに配したアルバムで台頭し、DJ作品とオリジナル・スコアを除けば、『Atlas』はヘイローにとって5作目の作品となるだろうか。そして、もう一つ注目しておきたいのが、坂本龍一が生前最後に残したSpotifyのプレイリスト「Funeral」の中で、ローレル・ヘイローの楽曲がリストアップされていたことである。しかも、坂本龍一が最後にリストアップしたのが、「Breath」という曲。これは彼がこのアーティストを高く評価しているとともに、並々ならぬ期待をしていたことの表れとなるだろう。
ローレル・ヘイローの作品は、どのアルバムもレビューが難しく、音楽だけを知っていれば済むという話ではない。特に、ローレル・ヘイローというプロデューサーの芸術における美学、平たく言えば、美的センスを読み解くことが必要であり、なおかつ実際の作品も、ポスト・モダニズムに属し、きわめて抽象的な音像を有しており、様々な観点から作風を解き明かす必要がある。例えば、実験音楽の批評で名高いイギリスのThe Quietusですら、今回の作品のレビューは容易ではなかったらしく、該当するレビューでは、ニューヨークのアンビエント・プロデューサー、ウィリアム・バシンスキー、ウィリアム・ターナーの絵画の抽象主義、そしてフランソワ・ミレーに代表されるフランスのバルビゾン派の絵画、そして、ゲーテの哲学的な思考等を事例に取り上げながら、多角的な側面から言及を行っている。そして、The Quietusのテクストに関してはそれほど長くないが、その中には確かに鋭い洞察も含まれていることが分かる。
謎解きやミステリー映画「ダ・ヴィンチ・コード」のように様々な考察の余地があり、聞き手の数だけ聴き方も違うと思われる『Atlas』。実は、深読みすればするほど、難解にならざるを得ない作品である。そして、裏を読めば読むほど、的確な批評をするのが困難になる。しかし少なくとも、この作品は、あるイギリスのコントラバス奏者、そして哲学をリーズ大学で学んだ作曲家の作風が思い浮かべると、その謎解きは面白いように一気に答えへと導かれていくのだ。
その答えは、オープニング「Abandon」で予兆的に示されている。例えば、「Abandon」に「ed Ship」という文節をつけると、一つの音楽作品が浮かび上がってくる。イギリスの作曲家、Gavin Bryars(ギャヴィン・ブライヤーズ)の「The Sinking of The Titanic」である。これはブライヤーズのライフワークで、これまでに何度となく作曲家が再構成と再演に挑戦して来た。ブライヤーズは、Aphex Twinにも強い触発を及ぼし、エレクトロニック系のアーティストからも絶大な支持を得る作曲家。彼は、タイタニックの沈没の実際的な証言を元にし、ときには給水塔やプール等の特殊な音響効果を使用し、このライフワークの再構成に取り組んできた経緯がある。
ローレル・ヘイローの『Atlas』のオープナー「Abandon」 ではこの特殊な音響効果の手法が取り入れられ、それがドローン・アンビエントという形に昇華されている。アンビエントのテクスチャーとしては、Loscil、Fennez、Tim Hecker、Hatakeyamaに近い音像を中心とし、音の粒の精彩なドローン音が展開される。そこに、ボウ・ピアノ、クラスター音のシンセ、ドローン音を用いたストリング、ファラオ・サンダースのようなサックスの断片が積み重なり、複雑怪奇なテクスチャーを構成している。つまりコラージュの手法を取り入れ、別のマテリアルを組みわせ、ドローン音という巨大なカンバスの中にジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングのような感じで、自由自在にペイントを振るうというのが『Atlas』における作曲技法である。
そして、ブライアン・イーノとハロルド・バッドが最初に確立したアンビエントの長きに渡る系譜を追う中で欠かさざるテーマが、「Naked to the Light」に取り入れられていることが分かる。それは崩壊の中にある美という観念。またそれは、朽ち果てていく文明に見いだせる退廃美という観念である。これは例えば、ニューヨークのWilliam Basinsky(ウィリアム・バシンスキー)が、ニューヨークの同時多発テロに触発された『The Disintegration Loop』という作品で取り組んだ手法。これは元のモチーフが徐々に破壊され、崩壊されていく中に、幻想的な美的感覚を見出すという観念をもとにした”Variation”の極北にある実験音楽。それは、ウンベルト・エーコが指摘する、本来は醜い対象物の中にそれとは相反する美の概念を捉えるという感覚である。
ヘイローは、バシンスキーのような長大な作品を書くことは避けているが、少なくとも前例を取り入れ、ドローン音楽という大きな枠組みを用意し、その中に変幻自在にボウ・ピアノのフレーズを配し、独特な音像空間を作り上げている。それは例えば、坂本龍一とフェネスのコラボレーション・アルバム『Cendre』において断片的に示された手法の一つである。そして、ストリングスを用い、ドローン音の効果を活かしながら、それらの自由なフレーズの中に色彩的な和音を追求している。
プーランク、メシアン、ラヴェル、ガーシュウィン等が好んで用いたようなクラシック・ジャズの源流にある近代和音が抽象的なドローン音の中を華麗に舞うという技法は、坂本龍一がご存命であったのなら、その先で取り組んでいたかもしれない作風である。そして、この曲は、ポピュラー・ミュージックシーンで最近好んで取り入れられている20世紀初頭の雰囲気を遠巻きに見つめるようなロマンチシズムに満ちあふれていることが分かる。
「Naked to the Light」