Oneohtrix Point Never 『Again』
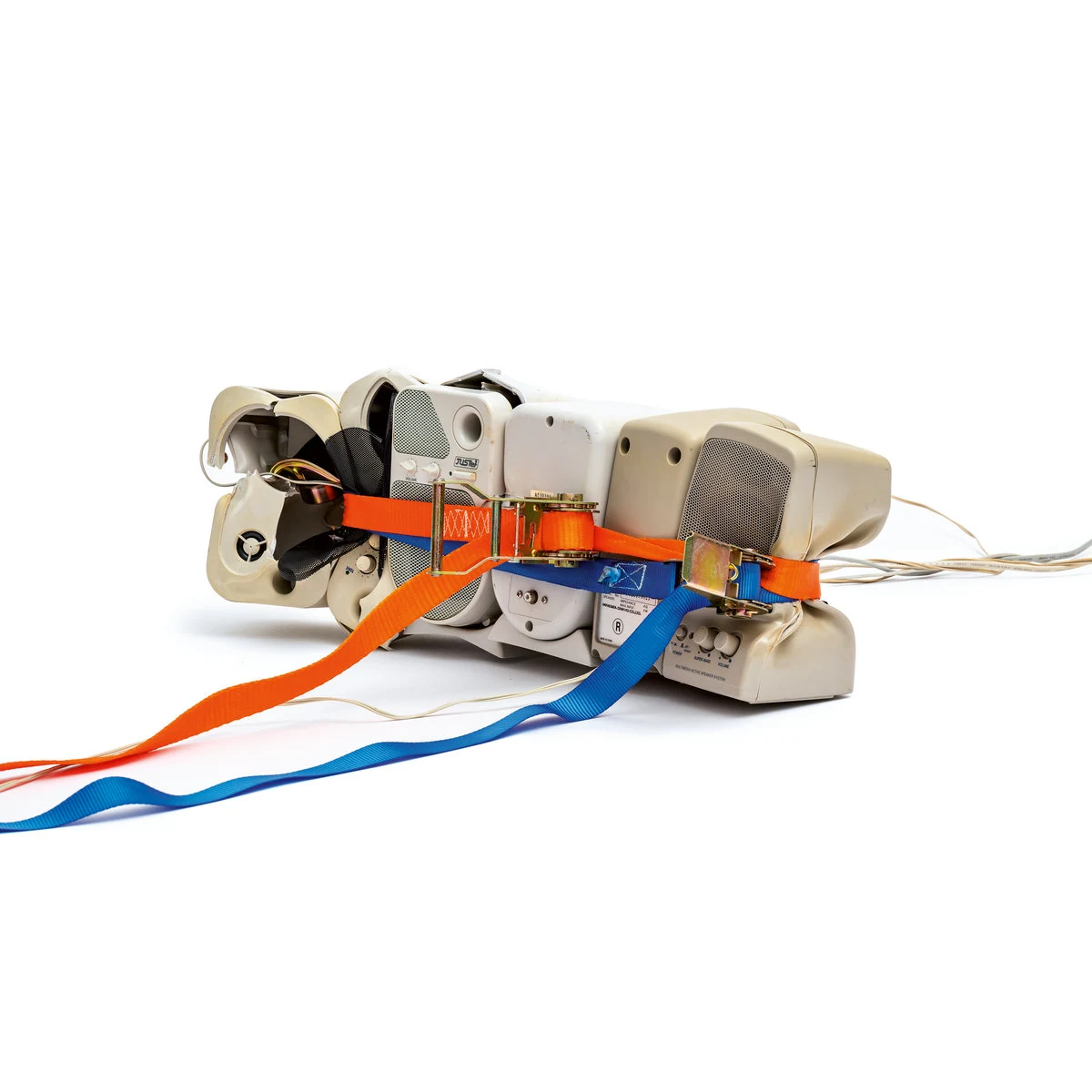 |
Label: Warp
Release: 2023/9/29
Review
イギリスのOneohtrix Point Neverこと、ダニエル・ロパティンの2年振りのアルバムは、「思索的な自伝」と銘打たれている。
Boards Of Canada、Aphex Twin、Squarepusher、Autechreと並んで、ワープ・レコードの代表的なアーティストで、レーベルの知名度の普及に貢献を果たした。
表向きには、ダニエル・ロパティンはアンビエントのアーティストとして紹介される場合もあるが、印象的には、オウテカのようにノンリズムや無調、ノイズのアプローチを取り入れ、電子音楽という枠組みにとらわれず、前衛音楽の可能性を絶えず追求してきた素晴らしい音楽家である。
今回のアルバム、「よく分からなかった」という一般的な意見も見受けられた。もしかすると、ダニエル・ロパティの『Again』は分かるために聴くという感じでもなく、また、旧来のジャンルに当てはめて聴くという感じでもないかもしれない。ランタイムは、54分以上にも及び、電子音楽による長大な叙事詩、もしくは、エレクトロニックによる交響曲といった壮絶な作品である。
実際に、畑違いにも関わらず、交響曲と称する必要があるのは、すべてではないにせよ、ストリングの重厚な演奏を取り入れ、電子音楽とオーケストラの融合を図っている曲が複数収録されているからだ。また、旧来の作品と同様、ボーカルのコラージュ(時には、YAMAHAのボーカロイドのようなボーカルの録音)を多角的に配し、武満徹と湯浅譲二が「実験工房」で制作していたテープ音楽「愛」「空」「鳥」等の実験音楽群の前衛性に接近したり、さらに、スティーヴ・ライヒの『Different Trains/ Electric Counterpoint』の作品に見受けられる語りのサンプリングを導入したりと、コラージュの手法を介して電子音楽の構成の中にミニマリズムとして取り入れる場合もある。
さらに、ジョン・ケージの「Chance Operation」やイーノ/ボウイの「Oblique Strategy」における偶然性を取り入れた音楽の手法を取る時もある。Kraftwerkの「Autobahn」の時代のジャーマン・テクノに近い深遠な電子音楽があるかと思えば、Jimi Hendrix、Led Zeppelinのようなワイト島のロック・フェスティヴァルで鳴り響いた長大なストーリー性を持つハードロックを電子音楽という形で再構成した曲まで、ジャンルレスで無数の音楽の記憶が本作には組み込まれている。そう、これはアーティストによる個人的な思索であるとともに、音楽そのものの記憶なのかもしれない。
一曲の構成についても、一定のビートの中で音のミクロな要素を組み立てていくのではなく、ノンリズムを織り交ぜながら変奏的な展開力を見せる。ビートを内包したミニマル・テクノが現れたかと思えば、それと入れ替わるようにして、リズムという観念が希薄な抽象的なドローン/アンビエントが出現する。そして、聞き手がそのドローンやアンビエントを認識した瞬間、音楽性をすぐに変容させて、一瞬にして、まったく別のアプローチへと移行する。良く言えば、流動的であり、悪く言えば、無節操とも解釈出来る「脱構築の音楽」をロパティンは組み上げようとしている。建築学的に言えば、「ポスト・モダニズムの電子音楽」という見方が妥当なのかもしれない。ロパティンは、構造性や反復性を徹底して排除し、ある一定のスタイルに止まることを作品全体を通じて、忌避し、疎んじてさえいる。それに加えて、曲の中において自己模倣に走ることを自らに禁じている。これは、とてもストイックなアルバムなのだ。
平均的な創造性をもとに音源制作を行う制作者にとっては、それほどクリエイティビティを掻き立てられないようなシンプルきわまりないシンセの基礎的な音源も、ダニエル・ロパティンという名工の手に掛かるや否や、驚愕すべきことに、優れた素材に変化してしまう。オーケストラのストリングスの録音とボーカルのコラージュを除けば、ロパティンが使用しているMIDI音源というのは、作曲ソフトやDTMの最初から備わっているシンプルで飾り気のない音源ばかり。
しかし、偉大な音の魔術師、ロパティンは、パン・フルート、シンセ・リード、シークエンス、アルペジエーター、エレクトリック・ピアノ、そういった標準的なシンセの音源を駆使して、最終的にはアントニオ・ガウディの建築群さながらに荘厳で、いかなる人も圧倒させる長大な電子音楽のモニュメントを構築してしまう。おそらく、この世の大多数の電子音楽の制作者は、ロパティンと同じ様な音源を所有していたとしても、また、同じ様な制作環境に恵まれたとしても、こういったアルバムを書き上げることは至難の業となるだろう。微細なマテリアルを一つずつ配し、リズムをゼロから独力で作り出し、彼はほとんど手作業で精密模型のような電子音楽を丹念に積み上げていく。そこに近道はない。アルバムの制作には、気の遠くなるような時間が費やされたことが予測出来る。そして驚くべきことに、そういったものはなべて、アーティストの電子音楽に対する情熱のみによって突き動かされ、オープニング「Elsewhere」からクローズ「A Barely Lit Path」に至るまで、その熱情がいっかな途切れることがないのだ。
このアルバムには、モダン・オーケストラ、ミニマル・ミュージック、プログレッシヴ・テクノ、ノンリズムを織り交ぜた前衛的なテクノ、アンビエント/ドローン、ノイズ、ロック的な性質を持つ曲に至るまで、アーティストが知りうる音楽すべてが示されている。アルバムのオープニングとエンディングを飾る「Elsewhere」、「A Barely Lit Path」は、Clarkが『Playground In A Lake』で示した近年の電子音楽として主流になりつつあるオーケストラとの融合を図っている。
これらのアルバムの主要なイメージを形成する曲を通じて、制作者は、従来の音楽的な観念の殻を破り、現代音楽の領域へと果敢に挑戦し、ダンス・ミュージック=電子音楽という固定観念からエレクトロニックを開放させ、IDMの未知の可能性を示している。「World Outside」、「Plastic Antique」では、ノイズ・ミュージックとミニマル・テクノの中間にある難解なアプローチを図っている。他方、比較的、取っ付きやすい曲も収録されている。「Gray Subviolet」では、ゲーム音楽が示した手法ーーレトロな電子音楽とクラシックの融合ーーに焦点を当て、RPGのサントラのような印象を擁する作風に挑む。ゲームミュージック的な手法は、ボーカル・コラージュとチップ・チューンを融合させた「Again」にも見いだせる。彼は、8ビットの電子音を駆使し、レトロとモダンのイメージの中間にある奇妙なイメージを引き出そうとしている。
その他にも、同レーベルに所属する”Biblo”のような叙情的なテクノ・ミュージックを踏襲した曲も聞き逃すことは出来ない。「Krumville」、「Memories of Music」では、電子音楽のAI的な印象とは別のエモーショナルなテクノを制作している。電子音楽というのが必ずしも、人工的な印象のみを打ち出したものではないことを理解していただけるはず。 他にも、ボーカル・アートの領域を追求した「The Body Train」では、スティーヴ・ライヒのミニマリズムとボーカルのコラージュを踏襲し、電子音楽という切り口から現代音楽の可能性に挑んでいる。カール・シュトックハウゼンが夢見た電子音楽の未来に対するロパティンの答えが示されていると言えそうだ。
さらに、ロック・ミュージックをテックハウスから解釈した曲も収録されている。とりわけ、「On An Axis」では、リズム・トラックにギターの演奏を交え、ケミカル・ブラザーズ、プライマル・スクリームが志向したようなダンスとロックのシンプルな融合性が示されている。最終的には、ロパティンの音楽性の一つの要素であるノイズが加味されることで、ポスト・ロックのような展開性を呼び起こす。
他にも、Clarkが『Body Riddle』の時代に試行した、ロックとテクノを融合させ、ある種の熱狂性を呼び起こそうという、90年代のテクノが熱かった時代の手法を「Nightmare Paint」に見いだせすことができる。ここでは、静と動を交え、緩急のあるテクノを作り出している。こういった旧来の手法一つをとっても、曲そのものから只ならぬ熱狂性が感じられるのは、制作者が受け手と同じか、それ以上の熱情を持ってトラックの制作に取り組んでいるからに違いない。つまり、制作者が徹底して熱狂しなければ、潜在的な聞き手を熱狂させることは難しいのである。
こういった無数の数限りない音楽ジャンルや手法が複雑に絡み合いながら、電子音楽の一大的な構成は、サグラダ・ファミリアの建築物のような神聖な印象を相携えながら、アルバムのサブストーリーを形成している。そして、音楽の印象を絶えず変化させながら、アルバムはクライマックスに至る。
「Memories of Music」は、叙情的なイントロから始まり、ハードロックのような音楽性へと変化する。そして、その中にはシンセのギターリードの演奏を交え、ギター・ヒーロに対するリスペクトが示されている。また、70年代のジャーマン・テクノへの愛着も、長大なストーリー性を持つ電子音楽に副次的に組み込まれている。そして、圧倒的な電子音楽の創造性は、終盤で花開く。アンビエントとテクノの中間点に位置する「Ubiquity Road」では、古典的なアプローチや音色を選び、ストーリー性を擁する電子音楽の理想形を示している。さらに、アルペジエーターを駆使したミニマル・テクノ「A Barely Lit Path」は、わずかに神聖な感覚を宿している。
このアルバム『Again』を聞き終えた頃には、プレスリリースに違わず、ダニエル・ロパンティンの長大な個人的な思索を追体験したような気がし、また、同じように、広大な電子音楽の叙事詩を体験したような不思議な達成感を覚えてしまう。少なくとも、難解なリズム、構成、着想を併せ持つ本作ではあるが、これらの音楽には、「未来への希望」という明るいイデアを部分的に感じとることが出来る。希望というのは何なのか。それは、次にやってくる未知なるものに対し、漠然と心湧き立つような期待感を覚えるということ。電子音楽としては、極めて前衛的でありながら、気持ちが晴れやかになってくる稀有な作品の一つだ。これもまた、長きにわたり、ワープ・レコードというダンス・ミュージックの本丸を支えてきたアーティストの矜持にも似た思いが、こういった長大かつ聴き応え十分のアルバムを生み出したのかもしれない。
88/100
「Ubiquity Road」







.jpg)














