 |
イスタンブール出身のEkin Üzeltüzenci(エキン・ウゼルチュゼンチ)のソロ名義であるEkin Filはアンビエント・ブレイクでカットされたインダストリアル・ノイズの中を駆け抜け、夢見るような眼差しで物語を語ったりと、彼女の音楽はとてもパーソナルで、胸を打つほど繊細である。
これまでに、Ekin Fil(エキン・フィル)は、イスタンブール、ベルリン、ハンブルク、クレーフェルト、オッフェンバッハ、ケルン、ヴァレッタ(マルタ)、マインツ、ワルシャワ、ヴロツローの様々な会場でライブを行い、マルコム・ミドルトン(元アラブ・ストラップ)、グルーパー、マウンテンズなどの前座を務めた。2009年に、イスタンブールでGrouperのオープニングを務め、ジェフレ=カントゥ=レデスマのルート・ストラータや進化するアメリカ西海岸/アンビエント・フォーク・ドローン・シーンにエキン・ユゼルチュゼンチを引き合わせた。
フィルのドローン・ポップは、ドリームポップのアンビエンスという一瞥を裏切るような、重厚な情感という内的論理を基にしている。遠ざかる夢を音楽として汲み取るかのように、漠然とした音色と間遠い歌によって浮かび上がる。彼女の歌とソングライティングは、プルーストの回想をトリガーとし、デヴィッド・リンチの映画の忘れられたワンシーン、Cocteau Twins(コクトー・ツインズ)のElizabeth Flazer(エリザベス・フレイザー)の声の断片的なエーテルやエッセンスを巧みに織り交ぜている。深遠な何か。隠された何か。寂しく悲しき感覚への讃歌...。
カルフォルニアのアンダーグラウンドのプリント、ヘレン・スカーズデール・エージェンシーは、エキンの作曲家としての継続的な発展、成熟、成長を目の当たりにする喜びを味わってきた。彼女のおもむろに燃え上がるような意気消沈したバラードは、高低差のある周波数と明度と暗度の間を揺れ動き、悲しみを深遠な場所から引き上げる。失われた愛。壊れた世界への落胆。
『Sleepwalkers- 夢遊病者』は、ナルコレプシーや、睡眠と覚醒の間の不安定な存在の状態、あるいは廃墟のような建物を見たときに感じざるをえない朽ちかけたものに対する癒やされるような感覚といった、エキン・フィルの作品ではお馴染みのメタファーが取り入れられている。
その中には、いくつかの未来的な試行も、最新アルバムでは実験的に示されている。例えば、"Stone Cold "の重力を司るソフトなノイズであったり、野心的な "Gone Gone "のアンビエント・クロールを彩るスローモーションのセリエル音楽のように、Tim Hecker(ティム・ヘッカー)の系譜にある一連のコンセプチュアルな楽曲の構成を通じて、彼女は非凡な才覚を表している。
『Sleepwalkers』- The Helen Scandale Agency ボーカルアートとシンセテクスチャーの極北
これまでのエキン・フィルの旧来のカタログに関しては、ボーカル録音を取り入れた曲もあるにはあったが、それはどちらかといえば、アメリカの西海岸のベースメントで、リバイバルとして少し前から流行っているローファイ、要するにスラッカー・ロックの範疇に属するものだった。
つまり、それほどボーカルが前面に出てくることはなく、デモトラックやミックステープのような控えめな録音、「BGM」の範疇にとどまっていた。これは、制作者が敬愛するポートランドのGrouperの影響が色濃く、ボーカル録音は、一貫して補佐的な意味合いにとどまっていたとも言える。
しかし、この最新アルバムで、イスタンブールのエキン・フィルは、持ち味のモジュラーシンセで組み上げるアンビエントの複合的なテクスチャを基にし、ボーカルアートの画期的な領域へと歩みを進めようとしている。それらのボーカルのヒントとなったのが、プレスリリースにも挙げられている通り、エリザベス・フレイザーのドリーム・ポップの影響下にあるボーカルの形式である。また、ドリーム・ポップとアンビエントーーこれらのスタイルが相性が良いのは、ハロルド・バッドのコクトー・ツインズとのコラボレーションを見ると、一目瞭然である。
同時に、エキン・フィルのアルバムの録音は、re:stの代表作を見る限りでは、音質の粗さというのが難点だった。たとえローファイな感覚のあるコアな音楽の魅力を有するとしても、音楽の本来の魅力が、荒削りな録音によって帳消しになってしまうことがあった。つまり、低音がやや弱い、という懸念事項があった。要するに、これらの要素は、エキン・フィルの作品の印象を良くも悪くも薄めていたのである。しかし、最新作に関しては、弱点が克服されているにとどまらず、期待以上のイノベーションが示されている。何より、中東から音楽をメッセージのように発信しつづけることは、他の主要な地域の音楽よりも重要な意味が求められるかもしれない。今回のアルバムは、Loscil、Tim Hecker、Irissariの最新のアンビエントの系譜にあり、対旋律的な意味を持つ低音部が強調され、重厚な感覚が立ち表れている。音楽そのものの印象が強固で、インパクトのある作品となっている。5曲というEPのようなコンパクトな構成にまとめ上げられているが、聴き応えは十分で、一度聴いただけでその全容を捉えることは困難である。
ボーカルは、トルコの言語で歌われている。これらの固有の言語、あるいは、固有の音楽という二つの考えについては、2000年代以降、そのエキゾチズムという観点から大きな注目をあつめることがあったが、最早それは昔の話である。今日日の音楽ファンが、例えば、スペイン語やイタリア語、ないしはそれとは別のアフリカのような今まであまり知られていなかった地域の言語の音楽に親しむようになったのは、単なる物珍しさによるものだけではないだろう。
いわば世界全体がひとつのグローバリズム一色に染め上げられる中で、多くの人々が固有性に着目しているということを象徴づけている。また、それらの異言語や異文化がむしろ、グローバリゼーションを推進した国家や地域等の音楽に見受けられるのは皮肉というべきか。これは意外にもグローバリズムが限界に達した時、一極主義に反転することを意味している。また、このことは世界政府や一国主義の流れに、懐疑的な視線を向ける人々が一定数どこかに存在することの証ともなりえる。グローバリゼーションの中には「多様性」という考えが含まれているが、因果なことに、多様性というのは、「固有性の差異の集積」から生み出される。つまり、共同体やEUのような考えから導かれるのは、それと対極にある「スペシャリティー」でしかあり得ない。
エキン・フィルの音楽は、Brian Eno(ブライアン・イーノ)の「Neroli」に象徴づけられるモジュラー・シンセによるアンビエントの構造、オシレーターの使用でもたらされるトーンの変化を用いた音楽という構造を持ち、本作に象徴づけられるように「音の流動性」に焦点が置かれている。
例えば、このアルバムのオープニングを飾る「#1 Sonua Kader」は「Neroli」の系譜にある一曲で、あまり明かされなかったことであるにせよ、今作のエキン・フィルの作曲が意外にもブライアン・イーノの古典的なアンビエントの系譜に位置づけられることを示す。サウンドパレットを建築や機械設備の図面のように解釈し、マレット・シンセのような音色を用い、深いリバーブ/ディレイをかけることで、それらの音楽的な構図に抽象的かつ色彩的な点を散りばめている。
最初は、何の意味を持たなかった点が広がっていき、そして何らかの意味を持ちはじめ、瞑想的な音楽を生み出す。これは、エキン・フィルがブライアン・イーノの秘伝のメチエの間接的な継承者であることを意味している。
しかし、それらの技法は、「音の魔術師」であるエキン・フィルの手にかかるやいなや、全く別様の音楽に変化する。大気の風の音を模したようなドローンの抽象的なテクスチャをパレットに敷き詰め、それらにマレットやグロッケンシュピールのようなアナログシンセのパーカッシヴな旋律を配し、通奏低音の配置にボーカルを挿入する。それらはメレディス・モンク、エリザベス・フレイザー、ベス・ギボンズの先を行く「ボーカルアートとしての極北」を意味する。
今回のエキン・フィルのボーカルは歌ではなく、ほとんど「祈り」のような概念を意味しているように思える。これまでのアルバムのボーカル・トラックの系譜にあるドリーム・ポップやドローン・ポップの範疇にあるものだが、間遠く聞こえるボーカルはモザイクの尖塔を頂くモスクの下のムスリムの輪唱さながらに響き渡る。高音部には、シンセのテクスチャとボーカル、低音部に同じくモジュラーシンセによるベース音を対旋律として配置し、重厚な建築物のごとき崇高性を生み出す。
表向きには政治的なテーマが語られることはない。それでも、制作者は、前作でギリシャ地方の大規模火災をテーマにしており、今回も深読みが促される作風である。夢遊病患者とは、世界全体を意味しており、ヘルマン・ブロッホの小説「夢遊の人々」のように、政変に翻弄される無数の人々を象徴づけているのかもしれない。更に捉え方によっては、ドキュメンタリー風の映画、まさにデヴィッド・リンチのような社会への鋭い風刺や、何らかの一家言を持った音楽が貫流しているというふうに解釈することもできるかもしれない。
オープニングで示された夢想的な感覚は、続く「#2 Stone Cold」で強烈なノイズに突き破られる。それらのドリーミーな感覚はほとんど、現実的な感覚を持ち始める。しかし、嵐のように瞬間最大風速を持って吹き荒れるすさまじい風の向こうから、かすかに日の暈のような幻想が浮かんでくる。そして、それはやがてドゥーム・メタルのような感覚を持ち、聞き手を無限の惑乱にいざなう。瞑想的とも暗示的とも、洗脳的とも言える圧倒的なテクスチャーの中で、ほとんど情景的なものは浮かんでこない。それらは、オリーブの木が茂っていた古代のイスラエルのオリーブ山が今や殺伐として、閑散とした荒れ野となり、そして、二千年を経たつかの間の夢の中では、聖書に描かれている楽園的な幻想は、現代性によって消し去られたという事実を決定づけている。そして、抽象的なサウンドスケープを描く中で、徹底して、聞き苦しいもの、嫌悪感を誘うもの、そして遠ざけたいものを、巧みに、リアリズムを以て表現している。しかし、それらのサウンドスケープは変遷していき、その向こうからエキン・フィルの亡霊のような声が、はっきりと(ぼんやりと)浮かび上がる。これらの荒野の中にさまよう無数の霊、あるいは朽ち果てた不思議な感覚を彼女自身のボーカルアートとモジュラーシンセを用い表現する。
前曲のアウトロでは、日の暈のような感覚を思わせる明るいイメージが示されている。しかし、続く「#3 Reflection」では、同じように抽象的なドローンによるアンビエントテクスチャを描きながら、それらの魂の変遷を巧みに捉えようとする。一音一音の連なり、その連続性が生み出す複合的な音像がさらなる音の連続を呼び覚まし、これらの音の集積が、必ずしもドローンという範疇にあるものではないことを暗示している。なぜなら、音の運びのひとつひとつは、必ずしもスムーズに生み出されるわけではなく、シンセの出力に何らかのためらいがあり、どの音の出力をどの配列に挿入するのか、そういった制作者の迷いが反映されているのである。
しかし、それらの一瞬のためらいは、次の瞬間、音が発生した瞬間に迷妄に変わり、新しい要素が出現する。オスマン・トルコ、神聖ローマ、プロイセン、ワイマール、有史以来のヨーロッパの国家の繁栄と衰退をメタファーとして暗示するように、絶えず変遷を繰り返すかのような霊的な感覚を擁する、一般的には理解しがたい、ある意味では不条理な音楽の中で、エキン・フィルは一貫して、得難いものや捉えがたいものを、作曲性や音楽観の基底に体現させる。そして偶然に起きたこと、必然的に計画されていたこと、双方の要素を交え、異質な音楽を発生させる。音楽が必ずしもあらかじめ決められた設計や構図の中で動くわけではないことを示し、そして、それらの制作者自身の手ではコントロールしがたい箇所に芸術の神々が宿ることを表す。これらの前衛主義やこれまでに存在しなかった概念は、夢想的なボーカルにより和らげられる。
アンビエントの全体的な録音のテクスチャーー音楽作品の構成要素--の中で最も重要なものは、音の全体的な広がりや音像の持つ奥行きである。実際的に言えば、マスターで、どれくらいの音響効果を掛けるか、どのくらい規模の音像を持つ音楽にするのかという点は、多くの制作者が念頭に置かざるを得ない。最近のアンビエントのトレンドでは、極大の音像を持つ作風が増加傾向にある。オーケストラでいえば、どれくらいの規模のホールでスコアを演奏するのか、また、チャイコフスキーの管弦楽法のように、作品やスコアによってストリングやホーンの編成を増やすのか減らすのか(ときには制作時の意図に反して)という考えに近いものがある。
これらの概念は、新しい電子音楽ーエレクトロニックを考える際に度外視できないし、実験音楽を制作する上でも見過ごせない要素となるかもしれない。「#4 Sleepwalkers」では、マクロコスモスを象徴づける極大の音像が作り出され、それらを「Drone-Pop」として昇華し、チェルシー・ウルフの系譜にある新しいポピュラーの形式を探求する。それは、ゴシックやニューロマンティックの表現下にあるドリーム・ポップ、あるいは、その先を行く現代で最も前衛的な音楽であるドローン・ミュージックという、2つのスタイルのクロスオーバーを意味している。
これらの音楽形式は、Grouper(リズ・ハリス)が先駆者であるが、エキン・フィルは、薫陶を受けたミュージシャンの影響を糧にして先鋭的な音楽へと昇華させている。いわば「ノイズーポップ」という「心地よくないものー心地よいもの」という相容れない概念の融合については、従来にはない音楽の形式の誕生を予感させる。メレディス・モンクの旧ドイツ時代に録音されたデビューアルバム『Dolmen Music』を見てもわかる通り、新しい表現のほとんどは、メインストリームから生み出されることは非常に少なく、その多くは、アンダーグランドーー誰も知らない不気味な一角ーーから出発する。ある意味、それが音楽や芸術のサンクチュアリとも言えるのである。それらがメインストリームに持ち込まれ、持てはやされるようになった時、つまり一般的になった時には、すでにそれは形骸化しており、衰退が始まっているのである。
旧来、エキン・フィルの作風は、古典的に傾きすぎる向きもあったが、アルバムの音楽は、ラスコーの壁画のような有史以来最も古い芸術形態から、それとは対極にあるモダニズムの形式を的確に織り交ぜながら、評価基準の一般化という概念から音楽そのものを開放させようとしている。また、このアルバムは、全般的には、ヒプノティックな感覚へと聞き手をいざない、静かな環境で聴いていてしばらく経つと、より懐深い感覚が立ち上ってくる。つまり、顕在意識とは異なる領域に感覚が移行していることを思い至らせる。それは日頃私達が感じている日常的な感覚とは別の領域への移ろい、言い換えれば「深層心理や潜在意識への旅」を意味する。
最後の曲「Gone Gone」では、このことが端的に体現されているのではないでしょうか。イリサリが最近制作している先鋭的なドローン、実験音楽の極北がクライマックスに集約されている。しかし、表面的に捉えられる抽象性とは対照的に、現代の世界情勢の歪みを刻印したような重厚な低音のベースが表面上のテクスチャーと蠱惑的な対比を描く。それらのリアリズムーー今日の世界の分離を徹底して実験音楽で表現しようとした崇高性ーーに関しては、他の追随を許さない。本作はいかなる類型にも属さず、孤絶や逸脱することを恐れていない。こういった勇敢な音楽が、女性プロデューサーの手から生み出されたということに対して称賛を送りたい。
100/100
Ekin Filによるニューアルバム『Sleepwalkers』はThe Helen Scandale Agencyから6月15日に発売。アルバムのストリーミングはこちらから。






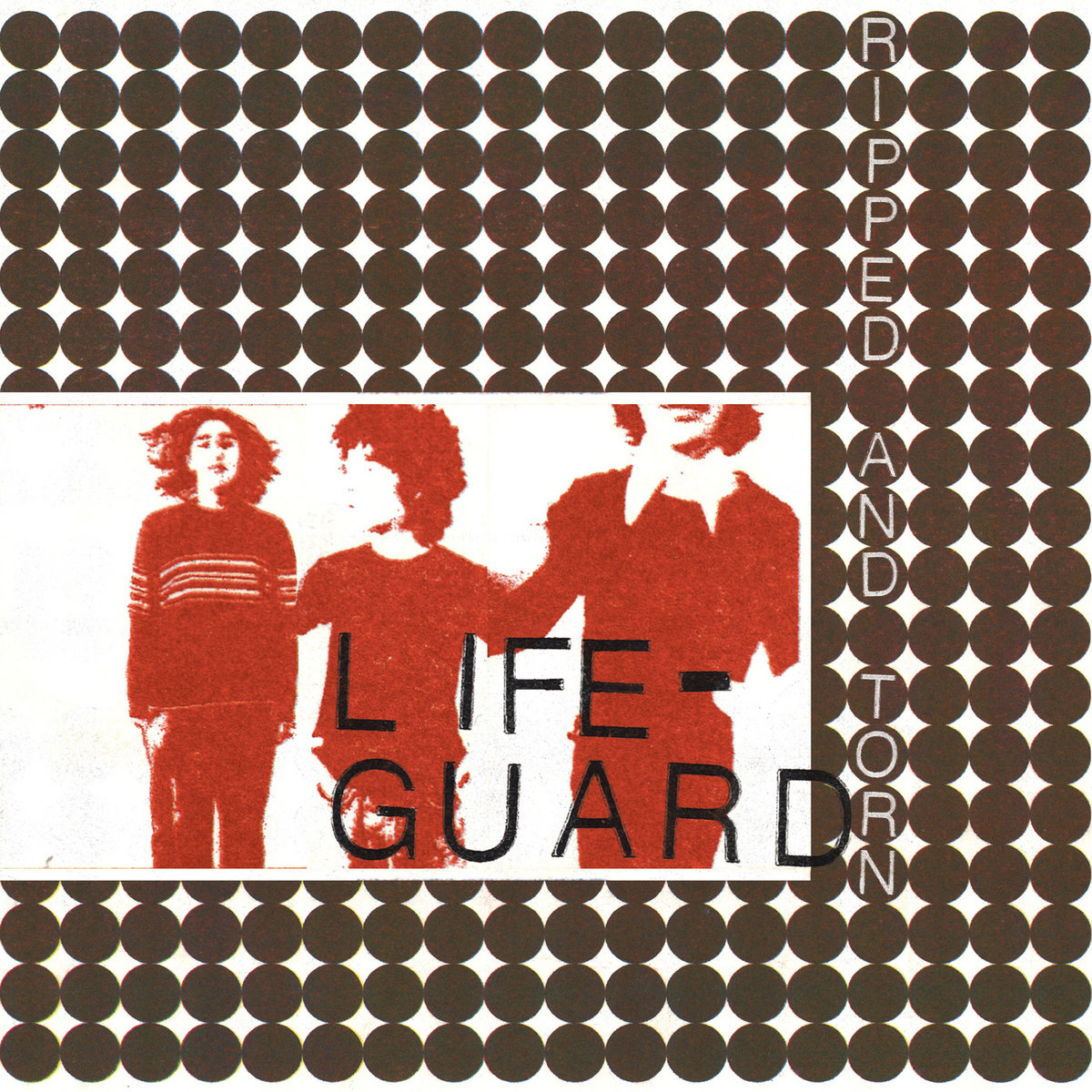













0 comments:
コメントを投稿