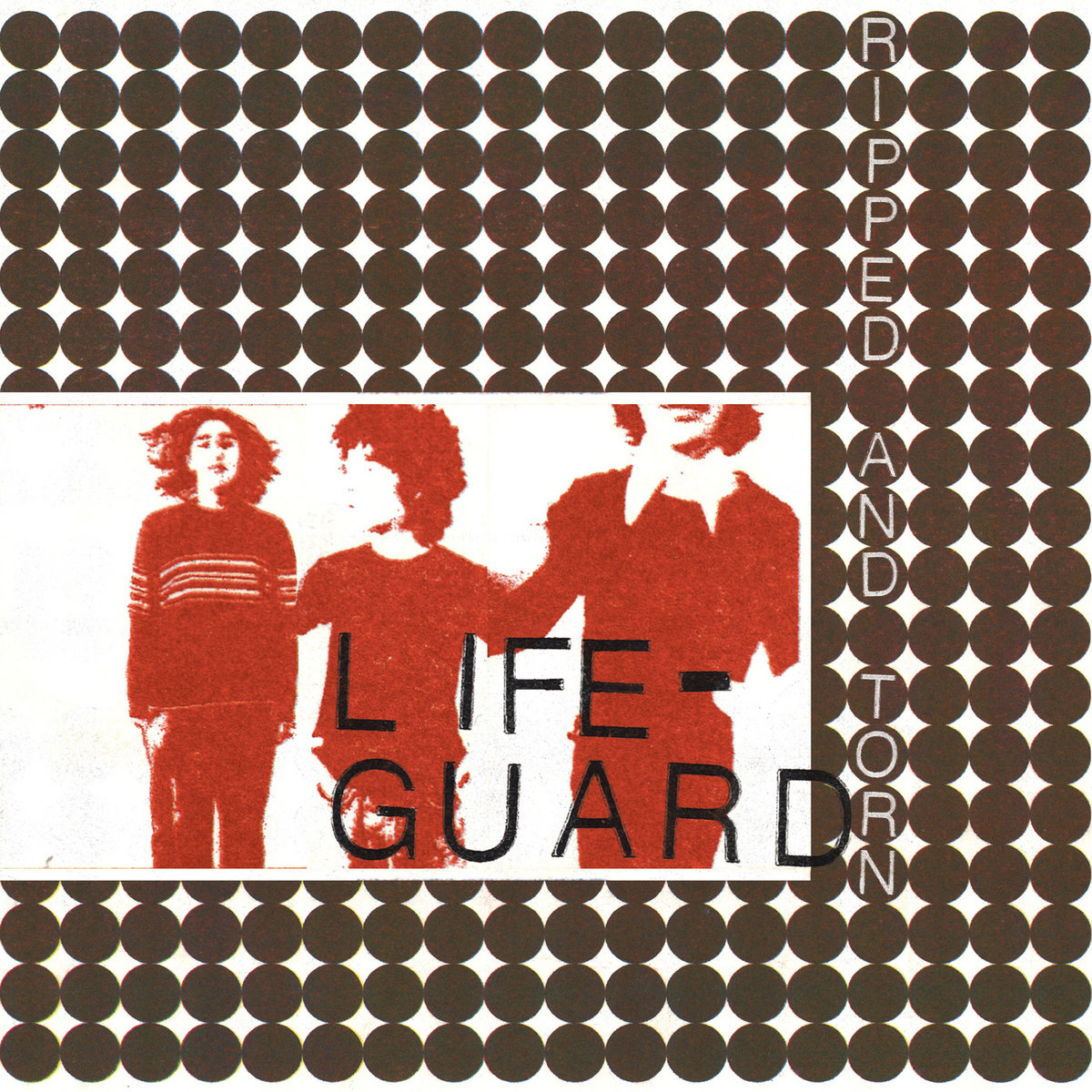Land Of Talk 『The EPs』
 |
Label: Saddle Creek
Release: 2024年7月12日
Review
現在、オルタナティヴロックの再興が起こっているのが、カナダのモントリオール。ジャズフェスティバルを中心に栄えてきたモントリオールのバンドは、米国のオルタナティヴロックの系譜に属しながらも、音楽性の性質が少し異なることで知られています。
そして、無名のバンドであっても、意外とベテランのバンドが多い。エリザベス・パウエル率いるLand Of Talkは、デビューからキャリア18年目に突入しているが、今なおデビュー当時のバンドのような熱情や鮮烈さを失わずに活動をつづけています。
「The EPs」はバンドの最初期の音楽性を踏襲し、テクスチャーとトーンの実験性を活かし、憧れと贖罪をテーマにしている。ポスト・パンクからのフィードバックがあるという点では、同地のColaと同様だが、ボーカリストのエリザベス・パウエルのボーカルが独特なキャラクター性を付け加えている。
オープナー「Sixteen Asterisk」は、ポスト・パンクサウンドとオルトロックの中間を行く楽曲であるが、パウエルのボーカルは何かに対する憧憬を示すかのように、ポピュラーの要素を付加する。しかし、バンド全体のサウンドは平凡なものにはならず、少しひねりが付け加えられている。
もちろん、変拍子を織り交ぜた立体的なサウンド、そしてシンセサイザーの要素がポスト・パンクバンドとしての性質を強化し、ニューヨークのBodegaのような先鋭的な音楽性をもたらす。さらに、ジャキジャキとした不協和音を活かしたギターが、それらに独自のテイストをもたらす。テクスチャーとトーンの複雑性という実験的な要素がありながらも聞きやすいのは、エリザベスのボーカルがポップネスを意識しているからでしょう。
懐古的なメロディーを擁するシンセピアノで始まる「May You Never」は、どことなく映画音楽のようなピクチャレスクな印象をもたらす。バンドの実験的な性質を象徴づけている。そして、その後、米国のフィラデルフィアのバンドとも共鳴付けられるようなオルトロックソングへと移行する。
特に、シンプルなドラムのプレイから引き出される、アンセミックなパウエルのボーカルは、米国のバンドとは異なるエキゾチズムをもたらす。ボーカルと呼応するようにして暴れまわるギターラインは、Land Of Talkの象徴的なサウンドと言えるでしょう。
しかし、その後、ディストーションを配したローファイなギター、さらにはドライブ感を持つドラムサウンドがバンド全体を巧みにリードし、ボーカルを上手く演出したり、引き立てたりしている。いわばベテランのバンドとしての巧みな展開力やリズムの運びが、曲に聴きごたえをもたらす。荒削りであるが、米国の90年代や00年代のSebadohのようなサウンドは、かなり魅力的です。
Land Of Talkのようなバンドは、男性のボーカリストをフロントマンに擁するバンドとは異なり、その夢想的な雰囲気や恋い焦がれるようなアトモスフィアが含まれる場合が多い。それらが硬派なオルトロック・バンドとしての枠組みの中、絶妙なバランス感覚をもたらすことがある。Alvveys、Ratboys、Wednesdayといった現代の注目すべきオルトロックバンドは、このバランス感覚を上手に活かしながら、聞きやすく乗りやすいインディーロックソングを制作している。
ご多分に漏れず、Land Of Talkも同様に、「As Me」「A Series of Small Flames」といった中盤のハイライトの中で、これらの幻想性と夢想的な感覚をオルトロックソングの中に織り交ぜている。ドラムの演奏がバンドの司令塔や大きな骨組みとなっているのは事実だが、その前面で変幻自在に展開されるギターやボーカルは、シューゲイズ風のギターを披露したり、また、それとは別に、90年代の米国のオルタナティヴロックのように乾いた質感を持つフレーズを演奏している。
これが全体的に合わさることで、ボーカルのThrowing Musesの系譜にあるファンシーなロックソングが構築される。一方、「A Series of Small Flames」では、Ratboysを彷彿とさせる夢想的なインディーロックソングである。続いて、「As Me」では、ギターがシューゲイズの範疇を越えて、アートのドローイングのような色彩的なテクスチャーを作り上げ、最終的にサイケデリックな性質を帯びる。これらは、彼らが平均的なバンドではないことの証立てになるかもしれません。
「Leave It Alone」、「Moment Feed」に関しては、エクスペリメンタルポップを下地にしたオルトロックソングに移行する。
これらはエリザベス・フレイザーのような現代的なアートポップソングを重視したバンドサウンドと称せるかもしれない。 後者の「Moment Feed」では、アルバムの序盤のポストパンクの系譜にある変則的なリズム、立体的なサウンドのテクスチャーを構築し、リアルなサウンドを作り上げる。ベースラインが全体的なサウンドから浮かび上がってくる時、バンドのもう一つのキャラクターである"シックな印象"が立ちのぼる。
「Something Will Be Said」では、バンドのローファイ、サイケ、R&Bなどの意外な性質がにじみ出て、EPの全体的な印象はガラリと一変する。最後の曲には、パウエルのソングライターとしての才覚が遺憾なく発揮されているようにおもえる。ギターとシンセのテクスチャーが組み合わされると、夢想的とか幻想的とかいう月並みな言葉以上の深さがにじみ出てくるのです。
"音楽によるアトモスフィア"といえばそれまでに過ぎませんが、この最後の曲には、バンド全体のスピリットのようなものが宿っている。アウトロの流れを生み出す熱狂的なギターソロ、背後のテクスチャーを構成するギター、シンセが組み合わされ、イントロからは予測しえないような壮大なエンディングを生み出す。この曲では、全体で一つになるような理想的なサウンドが味わえます。
本来は分離した存在がアンサンブルを通じて、どのような一体感をもたらすか? これは、バンドや複数のミュージシャンのセッションという形態でしかなしえないことでもある。
多くの方がご存知の通り、現在は有力な各メーカーの開発力によって、レコーディング技術が日々進歩し続けているため、ソロアーティストでもバックバンドやコラボレーターの協力を得ることにより、バンドに引けを取らない高い水準のサウンドを制作出来るようになっています。そのため、今後は、バンドでなければいけない理由を示すことが重要になってくるかもしれません。
78/100