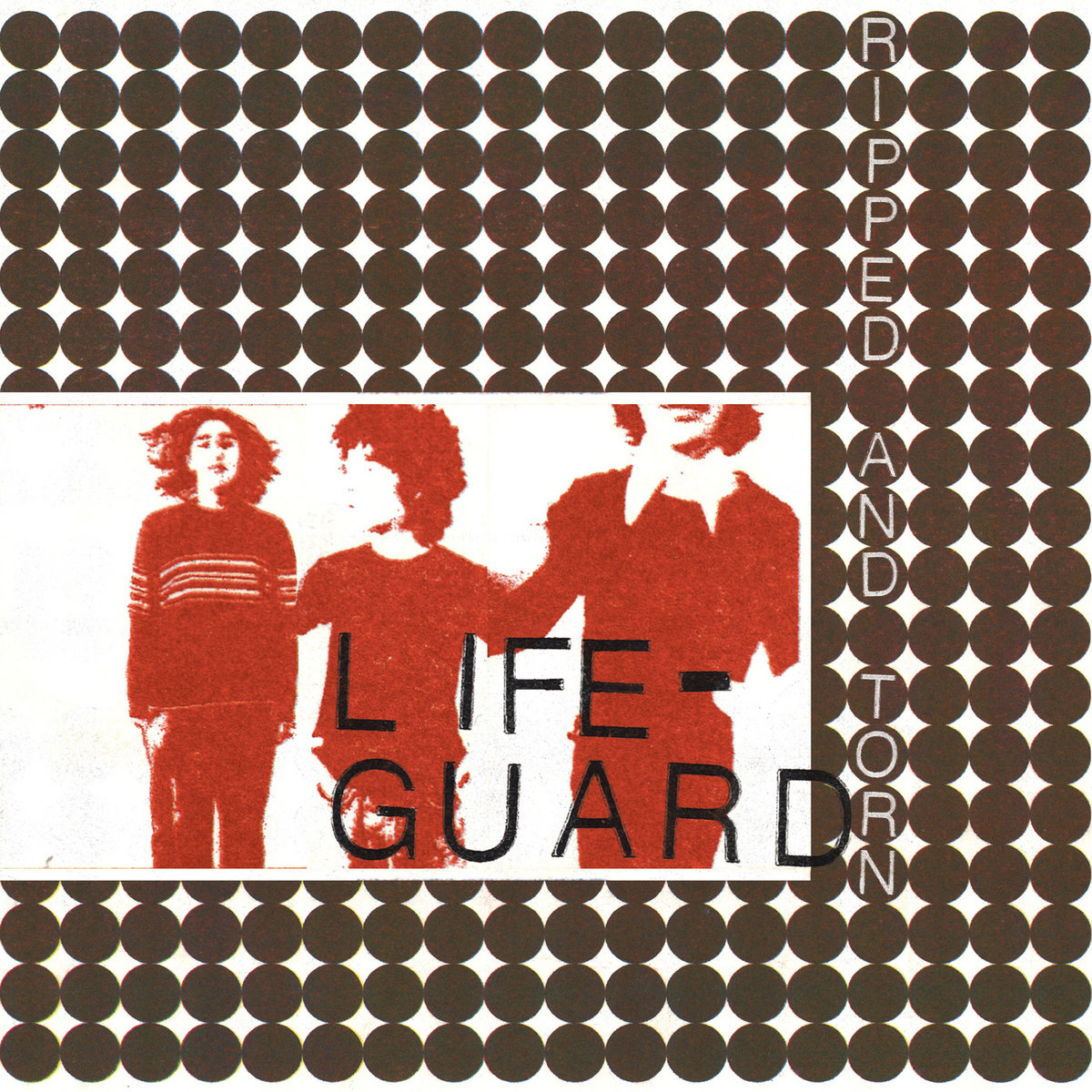Molly Payton 『Yoyotta』
 |
Label: Molly Payton
Release: 2024年8月30日
Review ◾️ニュージーランドの気鋭のシンガーソングライターのデビュー作
ニュージーランドのモリー・ペイトンのフルレングス・デビューアルバム『YOYOTTA』は、彼女が最も傷つきやすい状態のアーティストを描いた、深く個人的なプロジェクトである。
このアルバムでは、彼女がキャリアで初めてクリエイティブの首座に座り、プロジェクトのサウンドだけでなく、ビジュアル面でも主導権を握った。結果、過去のリリースを結びつけ、アーティストの人生と感情に新たな文脈を与える作品となった。ペイトンは、Beabadoobee、Arlo Parks、Alex G、Tom Odell、Palaceなど数多くのアーティストとのツアー、Primavera、Laneway、Pitchfork Parisでのプレイを経て、2024年後半は8月に「All Points East」でプレイし、アルバム『YOYOTTA』のリリース後、イギリスとヨーロッパでのヘッドライナー・ツアーに乗り出す。
オセアニア圏ではそれ相応の知名度を誇るペイトンのデビュー・アルバムは、世界で支持されるだろうか。少なくとも、全体としては、オルタナティヴロックをベースにしたポップソングが心地よい雰囲気を醸し出している。このアルバムがきっかけとなり、より大きな人気を獲得したとしても大きな不思議ではないだろう。モリー・ペイトンのソングライティングのスタイルは、上記のBeabadoobee、またはアーロ・パークスに近いが、声質がクリアで澄んでいるため、開放的な感覚のポップスとしても楽しむことが出来る。アルバムでは、センチメンタルな感覚が漂い、それがペイトンが10代の頃からソングライティングという形で培ってきたスタイルと上手く合致している。
オープナーを飾る「Asphalt」では、インディーフォーク風のイントロから、オルダス・ハーディングの系譜にあるオーガニックな音楽性、そして、編集的なオルトロックサウンドを織り交ぜたポップスへと展開していく。さほど物珍しさはないものの、良質なポップスと見て差し支えないだろう。
二曲目の「Benchwarmer」では一転して、ギターロックの範疇にあるオルタナティヴロックソングが繰り広げられる。この曲もまた同じく現代的なロックソングであるが、単調のフレーズを部分的に織り交ぜながら、若い年代としてのセンチメンタルな感覚を組み込んでいる。サビでは、求心力のあるギターサウンドをバックグラウンドにして、感染力のあるポップバンガーを書こうとチャレンジしている。これは、大型のライヴツアーをこなすようになったシンガーソングライターの「アリーナで映える曲を書こう」という意識が、こういった曲を生み出すことになったものと推測される。
アルバムの中盤では、シンセサイザーをオルガンのように見立てた「A Hand Held Strong」において、深妙なポップスを制作している。繊細な感覚を示すことをためらわず、アーティストなりの神聖な感覚で縁取ろうとしている。若手のシンガーソングライターであるにも関わらず、それほど傲慢にならず、謙虚な姿勢を持つことは、アーティストとして素晴らしい資質のひとつである。音楽に対する敬意を欠かさない姿勢や音楽に対して一歩距離を置いたような控えめな感覚は、実際的に良質な作品を生み出すための入り口となる。モリー・ペイトンは現在のところ、完璧なソングライティングの術を身につけたとまではいいがたいが、音楽に対する真摯な姿勢は、今後、何らかの形で花開く時が来るかもしれない。少なくとも、この曲では、それらがバラードというポピュラーシンガーとしての最初の関門をくぐり抜けるきっかけを与えている。
若いシンガーソングライターとして、感情の揺れ動きを曲の中で表現することは、それ以上の年代のミュージシャンよりもはるかに重要な意味が求められる。もちろん、若いリスナーに強いカタルシスをもたらすことはそれほど想像に難くない。現代的な生活の中で、たしかにSNSでもそういったことはできるが、楽曲の制作や録音現場で自分の本来の姿を見つけるということはありうる。
アルバムの中盤では、起伏のあるサウンドが描かれていて、それは開放的で癒やしのあるインディーフォークソング「Thrown Over」、続く「Accelerate」では、パンチとフックのあるオルタナティヴロックソングという対象的なコントラストを形成する。これらの気分の激しい揺れ動きや変調は、単なる衝動性以上の動機が含まれている。例えば、後者の場合は、シンセポップと現代的なロックの融合というフローレンス・ウェルチのようなスタイルを彷彿とさせ、これはスターシンガーとしての道を選んだことの証ともなり得る。実際的には、音楽に既視感があるという弊害を差し引いても、こういった曲が今後どのような特性を持ち得るのかに注目してきたいところだ。
同じように、オルトロックシンガーとしての性質と合わせて、繊細な感覚を持つポピュラーソングが本作の終盤に登場する。続く「Devotion」では、オルガンの演奏を背景にして、精妙な感覚を持つポップスを書こうと試みている。果たして、歌手が志すのが、ゴスペルのようなブラックミュージックなのか、教会音楽のような讃美歌なのかまでは分からないが、ここに理想とするポップスの雛形のようなものが暗示されたといえるだろう。また、それに続く「Doing Our Worst」では、映画的なポップスを書いており、「Pretty Woman」の主題歌を持ち前の自虐的なジョークで縁取っている。
これらのモダンなポップスはオルダス・ハーディングの系譜や、ヨーロッパの移民系のポピュラーシンガーの脱力感のあるソングライティングの形式を受け継いでいる。全般的には、良質なポピュラー・ソング集として楽しめるが、じっくりと聞かせるものや、核心となるものが乏しいのが懸念事項である。つまり、才能があるのにそれをイマイチ使いきれていないのが惜しい点だ。
「Teenager Bedroom Floor」では、再びクランチなギターロックへと舞い戻り、総仕上げとなるクローズ「Get Back To You」では、アルバムの冒頭と同じように、夢想的なオルタナティヴフォークを最後のテーマに掲げている。しかし、これらは、流行りのサウンドの模倣的な側面を示したに過ぎない。デビューアルバムとしては、一定の力量以上の何かが示されている。しかし同時に、現時点では、「スペシャル・ワン」の存在感が示されたとまでは言いがたい。オセアニア圏のシンガーソングライターとして世界の音楽ファンに何を伝えていくのか、そして、モリー・ペイトンとは一体何者なのか、二作目のアルバムにおいて、それらが明示されることを期待してやまない。
78/100
「Asphalt」