ーグルジエフの人生と考え
グルジェフは、コーカサス地方のアルメニア出身の神秘思想家で、20世紀最大のオカルティストとして知られている。神秘思想家としては、一般的にヘルメス主義の影響を受けているといわれ、イスラム神秘主義の「スーフィズム」の影響下にあるという説もある。彼はオカルティストとして絶大な影響力を誇った。
グルジェフは、ギリシャ系の父とあるルーマニア系の母のもとに生まれた。青年時代のグルジエフは、医師と牧師になるという夢を抱えていたが、その医術は、現代的に解釈すると、神秘主義的な治癒の方法に焦点が置かれていた。以後、彼は古文献を渉猟し、神秘主義者としての道のりを歩み始めた。彼の行動の手始めとなったのが、コーカサス地方をはじめとする放浪の旅である。
グルジエフは、アナトリア、エジプト、バビロニア、トルキスタン、チベット、コビ、北シベリア、東欧から小アジア、アラビアをくまなく歩いた。彼の探究心は、最終的に古代文明に行き着き、複数の秘技的な宗教集団と接触する。そのなかには、イスラム、キリストの神秘主義派、チベット密教、シベリアのシャーマニズムなど、多岐にわたるレリジョンが含まれている。
グルジェフは、複数の地域で秘技的な文化に接するが、最も強い触発を受けたのが、西アジアの北ヒマラヤにある「オルマン僧院」と言われている。ここにグルジェフは数ヶ月滞在し、イスラム神秘主義のひとつとされる「スーフィズム」を通じて、「大いなる知恵」を掴んだとされる。
しかし、グルジェフは意外にも、最初に実業家として名を揚げた。 20世紀初頭、チベットから戻った彼は、中央アジアのタシュケントで事業をはじめ、それを拡大させ、いつの間にか大金を手にしていた。彼が第一次世界大戦直前の社会的に混迷を極めていたロシアに姿を現した時、すでに彼は100万ルーブルもの資金を手にしていた。
この時代、彼は、実業家としての並々ならぬ才覚を発揮し、鉄道、道路のインフラ、レストラン、マーケット、映画館の経営に携わり、驚くべき大金をその手中に収めた。1ルーブルを現在の円のレートで換算すると、グルジエフは1,5億円以上もの収益を上げたということになる。 金銭価値は市場の相対的な評価に過ぎないので、現在ではさらに多額の価値があると推測される。
以降、ヨーロッパの貴族社会の人々や名士と交流を交わし、名声を獲得していったといわれている。そのなかで、新約聖書のなかで使徒が語ったように、ナザレのイエスがなした奇跡的な治療を施し、これがのちに、20世紀最大の神秘思想家として知られる要因になったと推測される。
グルジェフは、神秘主義の教団の首領として弟子たちをワークというかたちで先導するかたわら、アラビア、イスラム、スラブの民族音楽に触発された音楽家/舞踏家として芸術的に優れた才覚を発揮し、数年間で複数のスコアを遺している。なぜ、体系的な音楽教育を受けていないグルジェフが、音楽や舞踏という分野に活路を見出したのかは不明だが、これは秘技的な教団を率いる以前の放浪の時代に、音楽的な源泉が求められるのは明白だろう。彼は、それらをアカデミーで学ぶのではなく、生きた体験として学んだことは想像に難くない。グルジェフの音楽には、ヨーロッパ、南米、南アジアとも異なるエキゾチックな響きがある。その楽曲の演奏時には、Santur、Tmbuk、Duduk、Pkuなど、アラビア、イスラム圏の固有の楽器が複数使用される。
そして、グルジェフがアナトリア、エジプト、バビロニア、トルキスタン、チベット、コビ、北シベリア、東欧から小アジア、アラビアといった若い時代に旅をした地域のエキゾチズムが彼の音楽の根幹を成すことは、実際の音源を聴けば痛感できる。
彼の神秘主義の教えの中には、現代社会に通じる真実性が含まれていることがわかる。グルジェフは、「人類全体が目覚めておらず、眠ったままの隷属的存在」であるとし、そこから開放されることの重要性を訴えた。それを単なる神秘思想やオカルトと結びつけることは簡単だが、現代的な視点から見ると、スピリチュアリティに基づく思想だけを最重要視すべきではないように思える。
グルジェフは生前、弟子に対して、人類がなぜ戦争を幾度も繰り返すのかについて、そして戦争がなくならない理由について次のようなことを語っている。彼が話すのは1世紀前のことだが、しかし、2020年代の東欧やイスラエルで起きていることに深い関連性を見出すことができる。
ーー戦争を嫌う人々は、ほとんど世界が創造された当初からそうしようと努めてきたと思う。それでも、現在やっているような大きい規模の戦争は一度もなかった。戦争は減るどころか、時代とともに増えていて、しかもそれは普通の手段では止めることが出来ない。世界平和や平和会議に関する議論も、単に怠惰の結果であり、どころか欺瞞に過ぎない。 人間は、自分自身について考えるのも嫌でたまらず、いかにして他人に望むことをやらせることばかり考えている。
ーーもし、戦争をやめさせたいと考える人々の十分な数が集まれば、彼らはまず彼らに反対する人々に戦争を仕掛けることから始めるだろう。そして、彼らはそういうふうに戦うだろう。人間は今あるようにしかなれず、別様であることは出来ない。
ーー戦争には我々の知らない多くの原因が潜んでいる。 ある原因はひとりの人間の内側にあり、また別のものはその外側にある。そして戦争を止めるためには人間の内側から手をつけなければいけない。環境の奴隷であるかぎり、巨大な宇宙のちからという外的な影響をいかにして免れることができるのか? 人間はそもそも、まわりの外的な環境に操られているだけだ。もし、それらの物事から自由になれれば、そのときこそ人間は本来の意味で自由な状態になることができる。
ーー自由、開放、これがまず人間の生きる目的でなければならない。自由になること、隷属の状態から開放されること、これこそ人々が獲得すべき目標となるだろう。内面的にも外面的にも、奴隷状態にとどまるかぎり、その人は何者にもなることもできず、また、何もすることができない。内面的に奴隷であるかぎり、外面的にも奴隷状態から抜け出すことはできない。だから自由になるためには、人間の内的自由を獲得しないといけない。
ーー人間の内的な奴隷状態の第一の要因となるのは、その人自身の無知、なかんずく自分自身に対する無知である。自分自身を知らずして、みずからの内側にある機械的な動きとその機能を理解せずには、人間は本当の意味で自由になることも、自分自身を制御することもできない。それは単なる奴隷に過ぎないか、あるいは、外的な環境の翻弄される遊び道具にとどまるだろう。ーー グルジェフ
ーーグルジエフの音楽観 客観的な音楽と主観的な音楽の定義 東洋の発見
客観的な芸術と考えられるものに対する一般的な反応について語るのは難しい。それは、私たち誰もが経験したことのある普通の連想プロセスを超越しているように見える。私たちが知っている多くの音楽では、少なくともある文化圏の一般的な経験の範囲内では、特定の音の進行や質、それらの組み合わせや時間的な間隔が、他の人と共通する特定の感覚や感情を聴き手に呼び起こす。
この現象は、一見不可解であると同時に否定できない。この現象は、聴き手の中で活性化される共鳴から生じるに違いなく、さらに、音と記憶との関連性が曖昧だったり不明だったりしても、過去の経験との連想を引き起こすことが可能なのだ。全般的な芸術において、この振動(ヴァイヴ)の力は、その過程と結果を部分的にしか知らないまま使われている。アーティストの主観的な意識によって制限され、アーティストが発信するものは、同じように「主観的な反応」しか生み出せない。
従って、主観による表現の結果は偶然のものに過ぎず、「受け手によって正反対の効果をもたらすこともありうる」というのがグルジェフの主張である。「無意識的な創造的芸術は存在しえない」とまで彼は主張している。
逆に、客観的な音楽は、振動の法則を決定する数学、ピタゴラス派の標榜する黄金比による正確無比で完全な知に基づいており、それゆえ聴く人に特定の予測可能な結果をもたらす。グルジェフは、無宗教の人が修道院にやって来た時の例を挙げている。そこで歌われ演奏される音楽を聴いて、その人は宗教性をもたないにもかかわらず、なぜか「敬虔な祈り」を音楽の流れのなかに感じとることがある。この例では、人間を高い内的状態に導く能力が、「客観的な芸術の特性のひとつ」として定義付けられる。その効果は、人によって程度が異なるだけである。
音楽の持つ客観的な力学について、グルジェフは『ベルゼバブ物語』の中でもう一つの例を挙げている。彼は、特別なシステムに従って調律された普通のグランドピアノで、ある一連の音を繰り返し叩く驚くべき老練なダービッシュについて述べている。
ーーこれらの音はすぐに、聴衆の一人の足に、師匠が予言したとおりの場所にできものを生じさせる。その直後、別の音符の連打でその腫れ物はすぐさま消える。エリコの城壁が破壊されたという伝説は、単に奇跡的な出来事の想像上の物語ではない可能性を考えることはできないだろうか? もしかしたら、ヨシュアは音の振動の特異な性質と効力を知悉していたのかもしれないーー
このように、グルジェフの考えでは、心地よい楽音を楽しむだけでは、いかに深刻で高尚なものであろうと、科学として、芸術として、高次の知識として、そして、人間の成長と進化のために必要な糧としての音楽の究極的な理想には、少しも近づいていないことは明らかなのである。
グルジェフが、真理の体現という本来の神聖な目的を果たす芸術を発見したのは、主にアジアだった。東洋の古代芸術を彼は台本のようにすらすら読むことができた。それは好き嫌いのためではなく、「より深く理解するため」と彼は言った。
しかし、平均的なヨーロッパ人にとっては、ある程度の音楽的教養があっても、東洋音楽はエキゾチックであるが、最後には単調で理解しがたいものに思える。ベートーヴェンの交響曲やシューベルトのリート、あるいは単純な民謡の「内容」を受け取ることができるように思えるのと同じように、私たちはこの音楽のほとんどが「何について」書かれているのか理解できないのだ。
グルジェフは、オクターブ構造は普遍的であるが、東洋の音楽では、西洋人にとって奇妙な方法で分割されている可能性があることを想起させる。基音とオクターブとの間には、4つという少ない分割もあれば、48という多い分割もある。西洋的な考えでは、私たちの知覚は7音のダイアトニックスケールや、ピアノの鍵盤のように等距離にある12音の半音階構造によって制限される。
東洋の音楽は、微分音的な配置によって、私たちの「制限された音階」では到達しえない、かけ離れた感情を呼び起こすことができる、と言われている。にもかかわらず、私たちのほとんどは、それらが調律されていないような音楽というかたちでしか聴くことが出来ない。私達は、アジア人であっても、常日頃から西欧的な音楽の中で生き、それが一般的な概念であると捉えている。
他方、特別な感受性と開放性を持つヨーロッパ人が、東洋音楽のなかに熟考すべき深遠な何かが存在することを肯定しえる何かを発見する可能性が高いことは、紛れもない事実だろう。チベットの僧侶の深い三和音の詠唱、スーフィーのジークルの小声のクレッシェンド、日本の能楽の伴奏の滑舌のよい声音など、これらはすべて、感覚的な印象のみならず、未知なる感情を呼び起こす音楽形式に他ならない。当初の反応はしばらく新奇な感覚として後に残るかもしれない。それでも未だ疑問点は残る。ドミナントからトニックへの進行を追うように、知性により音楽の「構文」を追うことができなければ、その音楽は主観的に完全に受け入れられたのだろうか?
音楽を聴く行為というのは、聴覚により何かを把捉しているように見えて「他言語の構文」を追っているに過ぎない。そして、その語法が一般的なものと乖離するほど、その言語はより難解になり、一般的には受け入れ難いものとなる。
してみれば、各地域の文化の壁が、各々の音楽的な語法や言語的な特性を有するがゆえ、純粋な芸術という形で高次の知識を伝えることを阻害していると定義付けられる。しかし、もしかしたら、この真実を追求することが可能な道筋がどこかにみつかるかもしれない。グルジェフの客観的芸術の定義に近づけるような音楽的な事例を、西洋の遺産や伝統から探すのはどうだろう。アンブロジオ聖歌やグレゴリオ聖歌の純粋さと正確さについて思いを馳せるのはどうだろう?
あるいは、ノートルダム派の謎めいたオルガヌムや、15世紀のフランドルの巨匠、ヤコブ・オブレヒトが作曲した、「3」という数の順列を表現した数秘的な声楽ミサに注目すべきかもしれない。J.S.バッハが静謐で瞑想的な殻の中で対位法の難解な謎を探求したライプツィヒの合唱前奏曲や平均律のフーガの芸術を考えてみることはできないだろうか。あるいは、モーツァルトの五重奏曲の、シルクのように滑らかで欺瞞に満ちた表面の下に、音、音程、リズムの組み合わせが、言葉では説明できないような感情を人間の心に呼び起こす秘密が隠されているのではないだろうか?
これらの全般的な疑問は、芸術に関するグルジェフの考えを肯定し、彼自身が作曲した音楽と関連づけようとするとき、特に大きな意味を持つようになる。もちろん、グルジェフの音楽の目的そのものや、それが創作された状況さえも、音楽の捉え方に大きな影響を与える可能性があるということがわかる。
ーーロシアの作曲家、トーマス・デ・ハルトマンとの関わり
グルジェフとロシアの作曲家トーマス・デ・ハルトマンとの関わりはよく知られている。若いデ・ハルトマンは、精神的な教えを求めて1916年にグルジェフのもとを訪れ、彼の弟子となった。グルジェフは訓練された作曲家ではなかったため、デ・ハルトマンもグルジェフの音楽的思考を表現する理想的な補助役となった。
彼はまず、グルジェフの教えの不可欠な部分である聖なる舞曲(ムーヴメント)のために、グルジェフの音楽を調和させ、発展させ、完全に実現することから始めた。数年後、デ・ハルトマンは、ムーヴメントとは独立したグルジェフの音楽作品に同様の方法で協力した。驚くべきことに、これらの後者の作品は非常に数が多く、ほとんどすべてが1925年から1927年にかけて、グルジェフが数年前に研究所を設立したフランスのフォンテーヌブローのプリューレで作曲された。1927年、この音楽活動は終わりを告げ、グルジェフが再び作曲することはなかった。
ド・ハルトマンの貢献の重要性は極めて大きい。実際、デ・ハルトマンの献身的な協力がなければ、グルジェフの音楽的アイデアは私たちが知っているように生まれなかったのではないか、と考える人もいるだろう。しかし、グルジェフの音楽を綿密に研究し、特にデ・ハルトマンがグルジェフと関わる前、関わっていた時、関わっていた後の、グルジェフ自身の膨大な音楽作品と比較すれば、グルジェフの音楽の真の源泉はグルジェフ自身にあったことは明らかである。
もちろん、デ・ハルトマンには洗練された音楽的精神があり、この共同作業ではそれを見事に発揮した。しかし、グルジェフの目的に対する彼の感覚は鋭く、聡い音楽的本能を十分に保ちながら、この仕事のために自らの創造性を昇華させることができた。彼がグルジェフから指示されたメロディーをいかにして上品かつ適切に調和させ、発展させたとしても、本質的な音楽的衝動と、その音楽が呼び起こす独特の感情の質は、一人の人間から生まれたものであることは明らかである。デ・ハルトマンが作曲した各曲の草稿は、グルジェフによって聴かれ、グルジェフがその意図を実現できたと満足するまで、しばしば大幅に修正されることもあった。
デ・ハルトマンは、グルジェフとの作曲過程についての驚くべき記述からも明らかなように、この共同作業における自分の役割について、控えめであるどころか、どちらかと言えば自嘲的であった。デ・ハルトマンはグルジェフとの共同作業について次のように回想している。
ーーゲオルギイ・イワノヴィッチのすべての音楽の一般的なキャッチとメモは、通常、プリーレハウスの大きなサロンまたはスタディハウスのいずれかで、夕方に起こりました。私は演奏し始め、音楽用紙を持って階下に急いで降りなければならなかった。すべての人々がすぐに来て、音楽のディクテーションはいつもみんなの前にありました。
ーー書き留めるのは簡単ではありませんでした。彼が熱狂的なペースでメロディーを演奏するのを聞いたので、私は紙に一度に曲がりくねった音楽の反転、時には2つの音符の繰り返しを走り書きしなければならなかった。しかし、どんなリズムで? アクセントの作り方は? メロディーの流れは、時々止めたり、バーラインで分割したりできませんでした。そして、メロディーが構築されたハーモニーは東洋のハーモニーであり、私は徐々にそれを認識しただけだったのです。
ーー多くの場合、私を苦しめるために、彼は私が表記を終える前にメロディーを繰り返し始め、これらの繰り返しは微妙な違いを持つ新しいバリエーションであり、私を絶望に駆り立てました。もちろん、このプロセスは単なるディクテーションの問題ではなく、本質的なキャラクター、メロディーの非常にノヤウまたはカーネルを「キャッチして把握」するための個人的な練習でした。
ーーメロディーが与えられた後、ゲオルギイ・イヴァノヴィッチはピアノの蓋をタップしてベース伴奏を構築するリズムを演奏しました。その後、私は与えられたものをすぐに演奏し、私が行くにつれて調和を即興で演奏しなければなりませんでした。
 |
| Gurdjieff |
グルジェフは、ロシア領のアルメニアとトルコの国境にある、豊かな民族と宗教が混在する中心地で生まれ、幼少期を過ごした。少年時代から人間存在の意味について深い疑問を抱いていた。彼は、彼を取り巻く光景や音、特に音楽に対して非常に敏感であった。
深く慕い、『驚くべき人々との出会い』の中で彼が感動的な章を書いている父親は、「アショク」という職業に就いており、彼の民族の古代の伝説の数々を歌や詩で語る吟遊詩人のような存在だった。
これがグルジェフの最も初期の音楽的印象と影響であった。その後、若い学生時代にロシア正教会の聖歌隊で歌った。それ以上の音楽的訓練はほとんど受けていない。しかし、少年時代やその後の旅で吸収した多様な土着の音楽に対する彼の並外れた感受性は、彼自身の作曲に顕著に反映されている。
民謡や舞踊、さまざまな聖職者の宗教的聖歌、エジプトや中央アジア、遠くはチベットの寺院や修道院で耳にした神聖な合唱曲など、ありとあらゆる音楽がグルジェフのスコアのなかには通奏低音のように響き渡る。彼自身の楽器演奏能力については、ギターや、片手で弾き、もう片方の手で空気を送り込む小さなハルモニウムの形をした鍵盤の演奏など、ささやかなものだったようだ。
彼の音楽にはアラビア、イスラム、スラブの独特な音楽性が発見できる。そこには讃美歌の影響があると指摘する識者もいる。現代音楽のシーンでは、グルジェフのアーティスト/ミュージシャンとして再評価の機運が高まっているという話もある。それらのスコアの再構成に取り組むのが、The Gurdjieff Ensemble(グルジエフ・アンサンブル)、そして、ジャズレーベル、ECMである。
 |
| The Gurdjieff Ensemble |
ドイツの国家観としては、グルジエフの作品をリリースすることは勇気が必要だが、従来から「エスニック・ジャズ」というジャンルを手掛けてきたレーベルは、アラビア、イスラム圏の音楽の伝統性をより良く知るための最適な機会を提供している。The Gurdjieff Ensembleの功績は、グルジェフの音楽の隠れた魅力を発見したことに加えて、単なるオカルティストや神秘主義者の遊戯という領域を超越し、真に芸術的な表現に引き上げようとする挑戦心に求められる。
以前は、アラビア、イスラム圏の作曲家は、日の目を見る機会が少なく、軽視されることもあったが、以下に紹介する、グルジエフのスコアの再録のリリースなどの機会を通して、スラブ、アナトリア、イスラム、中央アジアを中心とする文化圏の音楽にも注目が集まることを期待したい。
The Gurdjieff Ensemble & Levon Eskenian『Music of Georges I. Gurdjieff』
グルジェフ(1866年頃~1949年)の音楽を民族的なインスピレーション源に立ち返らせる、魅力的で非常に魅力的なプロジェクト。
これまでグルジェフの作品は、西洋ではトーマス・デ・ハルトマンのピアノ・トランスクリプションによって研究されてきた。アルメニアの作曲家レヴォン・エスケニアンは、印刷された音符を越え、グルジェフが旅の間に出会った音楽の伝統に目を向け、その観点から作曲を再編成した。
エスケニアンは、アルメニア音楽、ギリシャ音楽、アラビア音楽、クルド音楽、アッシリア音楽、ペルシャ音楽、コーカサス音楽のルーツに注目している。アルメニアを代表する奏者たちの協力を得て、エスケニアンは2008年にグルジェフ民族楽器アンサンブルを結成し、彼らとともにこの驚くべきアルバムを完成させた。
レヴォン・エスケニアンの楽器編成で私が最も魅力を感じるのは、静寂の荒野でほんのわずかな音への介入を行う際、不必要な "作曲 "や "巧みさ "を排した、極めて綿密で明快な作業アプローチである。グルジェフの音楽の核心には深い静寂があり、それは聖書のコヘレトの書の章、あるいは遠い国の深い静寂が語る真実と関係している。- ティグラン・マンスリアン
Anja Lechner / Vasslis Tsabropoulos 『Chants, Hymns and Dances』
ドイツのチェリスト、アンニャ・レヒナーとギリシャのピアニスト、ヴァシリス・ツァブロプロスによる魅力的な新プロジェクト「聖歌、賛美歌、舞曲」は、「世界の十字路からの音楽」という副題が付けられるかもしれない。グルジェフの作品のなかでは最も室内楽的な響きを持つ。
東洋と西洋、作曲と編曲と即興、現代音楽と伝統音楽の境界線を曖昧にするプロジェクトだ。レパートリーの中心は、古代ビザンチンの賛美歌をインスピレーション源とするツァブロプーロスの作曲と、アルメニア生まれの哲学者・作曲家であるジョルジュ・イヴァノヴィッチ・グルジェフ(1877-1949年頃)の音楽で、コーカサス、中東、中央アジアの聖俗両方のメロディーとリズムを使用している。 ーECM
The Gurdjieff Ensemble & Levon Eskenion『Komstas』
アルメニアン・グルジェフ民族楽器アンサンブルは、G.I.グルジェフ/トーマス・デ・ハルトマンのピアノ曲を「民族誌的に正統な」アレンジで演奏するために、レヴォン・エスケニアンによって設立された。
ECMからのデビューアルバム『ミュージック・オブ・G.I.グルジェフ』は広く賞賛され、2012年にエジソン賞のアルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。今、エスケニアンと彼の音楽家たちは、コミタス・ヴァルダペト(1869-1935)の音楽に注目している。
作曲家、民族音楽学者、編曲家、歌手、司祭であったコミタスは、アルメニアにおける現代音楽の創始者であり、コレクターとしての活動の中で、アルメニアの聖俗音楽を独自に結びつけるつながりを探求した。民俗楽器の演奏とインスピレーションに満ちた編曲に焦点を当てたこのアンサンブルは、201年2月にルガーノで録音されたこのプログラムで、コミタスの作曲の深いルーツに光を当てる。ーECM
The Gurdieff Ensemble & Levon Eskenion 『Zartir』
昨年にECMから発売された『Zartir』は、グルジエフの音楽的な遺産を発掘するためのアルバムである。
レヴォン・エスケニアンによる注目のアンサンブルのサード・アルバムは、これまでで最も冒険的な作品となった。G.I.グルジェフの音楽を民族楽器のために再生させただけでなく、アシュグ・ジヴァニ、バグダサール・トビール、伝説的なサヤト・ノヴァなど、アルメニアの吟遊詩人やトルバドゥールの伝統の中にグルジェフを位置づけている。これと並行して、神聖な舞踊のための作品に重点を置いた『大いなる祈り』は、グルジェフ・アンサンブルとアルメニア国立室内合唱団との魅惑的なコラボレーションで頂点に達し、複数の宗教の儀式音楽を取り入れている。
アレンジャーのエスケニアンは、「『大いなる祈り』は単なる "作曲 "以上のものだと思います。グルジェフの作品の中で、私が出会った最も深遠で変容的な作品のひとつです」と語る。
『ザルティール』は2021年にエレバンで録音され、2022年11月にミュンヘンでマンフレート・アイヒャーとレヴォン・エスケニアンによってミキシングされ完成した。ーECM
こちらの記事も合わせてお読み下さい:
Tシャツ産業の発展、ロック・ミュージックとの関わり











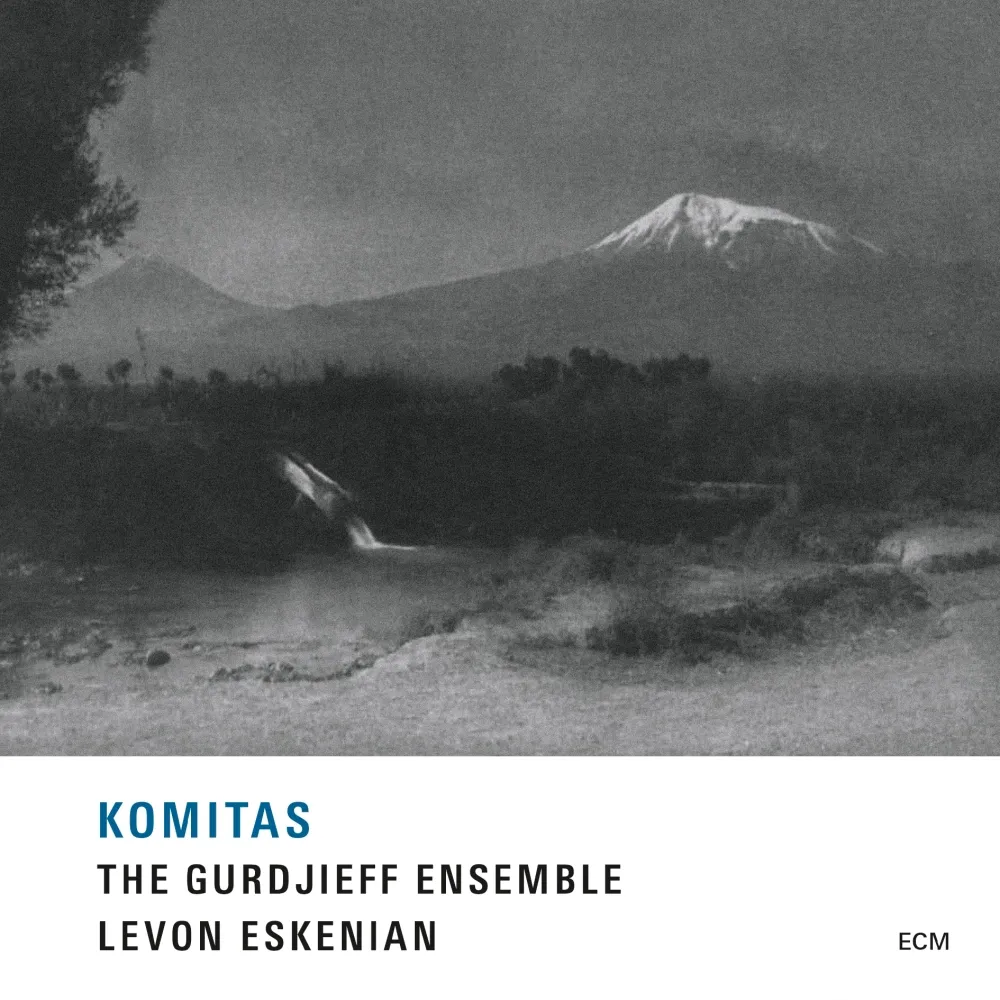

























.jpg)














