 |
ジャコ・パストリアスは型破りな演奏家として知られているが、一方、モダンジャズの先駆者で、ニュージャズやクロスオーバージャズへの橋渡しをした数奇な存在でもある。ベーシストとしては、ジャズ・ファンクからアフロキューバンジャズ、エスニックジャズ、アヴァンジャズ、R&B、それらを一緒くたにするフュージョンといった多彩な音楽性の中で、このジャンルの可能性を敷衍させる働きをなした。彼を一定のグループの中に収めることは難しいのではないか。
そもそも、たまたまジャズマンとして活躍しただけで、ロックミュージシャンと見なされた時期もあったのだし、彼の念頭にはこのジャンルだけが存在したとは到底考えづらいのである。ベーシストとしては、フレットレス・ベースの演奏、ミュート、ハーモニクスの奏法に関して、大きな革新性をもたらした。同時に、スラップ奏法の先駆的な技法も見受けられる。さらにアヴァンギャルドな演奏法の中でも、ミニマリズムの技法を駆使することがある。ロックミュージシャンはもちろん、エレクトロニックの界隈でも影響を受けた方は少なくないのではないか。
ジャコ・パストリアスは、1951年12月1日にフィラデルフィア州ノリスタウンに生まれた。父はドラマーで、彼のことを「ジャコ」と呼んで可愛がった。1958年、ジャコ一家は、フロリダのフォート・ローダーデイルに転居した。この街は、キューバ、ジャマイカからの移住者が多かった。このことが、後に、中南米の音楽をジャズの中に織り交ぜるための布石となった。ドラマーである父親の影響は大きかった。しかし、パストリアスは明確なレッスンを受けないまま、器楽奏者として多彩な才覚を発揮するようになった。子供の頃から、ドラム、サックス、ギター、ベースの演奏を難なくこなすようになった。だが、当初は父親と同じくドラマーを志していた。
彼は13歳の時、フットボールの競技中に右腕を負傷した。このことでドラマーになる夢を断念した。しかし、彼は簡単に音楽の道を諦めることが出来なかった。17歳のときには手術を受け、ようやく彼の腕はふつうに動くようになり、ベーシストとしての道を歩むことを決意する。 パストリアスは、すでにプロになるまえに結婚していたが、妻が身ごもったために、やむなく洗車場で働いたことが伝えられている。パストリアスは妻の出産前に、700ドルをためていたが、子供が生まれるおよそ一ヶ月前に、これらの費用をアンプ代につぎ込んでしまった。だが、その後、パストリアスは500ドルを貯め、それを妻の出産の費用に宛てたのである。
すでに娘が生まれた頃、どうやらベーシストになる決意は固まっていた。彼はレコードを聴いたり、本を読んだりするのを中断し、ベースの演奏や自作曲の制作に昼夜没頭するようになった。エレクトリック・ベーシストというのは、フュージョンジャズの文脈から登場したが、彼が伝統的なコントラバス奏者ではないにもかかわらず、ジャズシーンでも高い評価を受け、そしてジャコ・パストリアスという固有的なサウンドを生み出したのは、この時代の鍛錬によるところが大きいと伝えられている。独創性、技術、そして卓越性、どれをとっても一級品であるパストリアスの代名詞となるサウンドの多くは、彼が名もなきミュージシャンとして活動していた時代に培われたものであった。しかし、ジャコ・パストリアスのベースは、従来のウッドベースの奏法に依拠するところが大きい。彼がソロ活動やバンドを始める以前のウェザー・リポートのジョー・サヴィヌルは、初めてパストリアスの演奏を耳にしたとき、こう尋ねたという。「それで、君はエレクトリックベースを弾けるのかい?」よもやサヴィヌルは彼がそのサウンドがエレクトリックベースによって奏でられたものだとは思わなかったというのである。
優れた音楽家がいると、周りに秀逸なプレイヤーが自然に集まって来るということがある。例えば、ジャコ・パストリアスの場合、すでにマイアミ大学に在学中に伝説的なジャズ・ミュージシャンと知己を得ていた。まずはシカゴのギタリスト、ロス・トロウトにはじまり、その後はピアニストのポール・ブレイと仕事をした。また、同じ頃、パット・メセニーと知り合った。
ジャコ・パストリアスは、パット・メセニーの自宅で演奏したあと、ポール・ブレイと一緒にライブ・アルバム『ジャコ・パストリアスとの出会い(Jaco Pastorius / Pat Metheny / Bruce Ditmas / Paul Bley)』(1974)、『Broadway Blues』(1975)で共演したほか、また、後には、パット・メセニーのスタジオアルバム『Bright Size Life』(1976)にも共同制作者として名を連ねている。また、同年、ジョニ・ミッチェルのアルバム『Hejira』にも参加した。
伝説的な演奏家との共演の機会を経て、ジャコ・パストリアスの名声は高まりつつあり、フロリダ/フォート・ローダーデイルのナイトクラブ「Bachelors Ⅲ」に出演するようになった。レイ・チャールズ、ティナ・ターナー、アル・グリーンなど錚々たる顔ぶれが出演するなか、ジャコ・パストリアスは、ハウスバンドを率いていたアイラ・サリヴァンのコンボで演奏を務めたのである。
 |
1975年の夏、彼に決定的なチャンスがやってきた。このクラブで当時大人気だったジャズ・ロック・グループ、BS&T(ブラッド・スウェット&ティアーズ)が出演したとき、ドラマーのボビー・コロンビーに才覚を認められ、彼の紹介もあって、パストリアスはデビュー・アルバムをエピックでレコーディングすることになった。その翌年、彼がニューヨークで録音をおこなっていた時、ウェザー・リポート(Weather Report)のジョー・サヴィヌルと再会した。
当時、サヴィヌルは、バンドのアルバム『ブラック・マーケット(Black Market)』を録音していた。ジャコ・パストリアスの顔を見るなり、「ちょうどよかった。フロリダサウンドが欲しかった!!」といい、さっさとパストリアスを引き連れ、バンドメンバーに迎え入れることになった。
1976年、ソロデビューアルバム「Jaco Pastorius(ジャコ・パストリアスの肖像)」がSony/Epicから発売された。大胆にもセルフタイトルを冠してである。アルバムは彼をレコード会社に紹介したコロンビーがプロデュースした。
従来から言われているように、ジャコ・パストリアスのベースの演奏は、オルタード・スケールを活用することが多い。しかし、スケール的にはスタンダードなものが基本になっている。しかし、このデビューアルバムの多彩さはなんだろうか。彼が影響を受けた音楽のほとんどを凝縮させたかのようでもある。デビュー作であるというのに、アンソロジーのような印象があり、末恐ろしいほどの才覚が11曲に詰め込まれている。
驚くべきことに、彼のデビューアルバムには、クラシック、ジャズ、現代音楽、ファンク、R&B、そしてラテン音楽を始めとするエスニックすべてがフルレングスにおさめられている。その中でも、ミュートやハーモニクスを生かした「Portrait Of Tracy」、民族音楽のリズムを取り入れ、それらをジャズとミニマリズムから解釈した「Okonkole y Tromba」等の独創性が際立っている。また、「Opus Pocus」ではカリブ海のスティールパンの演奏が取り入れられている。当時は「フュージョン」とも称されていたが、クロスオーバージャズの先駆的なアルバムでもある。今なおジャコ・パストリアスの演奏、そして作曲は鮮烈な印象をとどめている。
それは時々、編曲という形に表れ出ることがあった。いつ彼がクラシックを聴いていたのか、もしくはスコアを研究していたのかは定かではないが、1981年に発表されたセカンドソロアルバム『World Of Mouth』では、「半音階幻想曲(Chromatic Fantasy)」という曲が登場し、これはバッハの半音階幻想曲とフーガ(BMV903)の編曲あるいはオマージュである。他にもビートルズの「Blackbird」をアレンジしている。
一般的には、彼の演奏や作曲の中には、ファンク、R&Bの系譜とスタンダードジャズが含まれているが、それと同時並行して、クラシックの影響をジャズの中に織り交ぜようと試みていた。彼はジャレットと同じように、カウンターと伝統という対極の性質を持ちながらも、ほとんど同根にある二つの音楽ーージャズとクラシックーーの並列が可能であるかを見定めていた。
この曲は、最初はクラシックふうに聞こえるが、後半にはオーケストラの民族音楽へと変化していく。レスピーギやラヴェルが探求していた、エスニックとクラシックの融合である。これはプログレッシヴ・ロックと並行するようにして1970年代のフュージョンの時代の音楽という実感を抱く。
それだけではない。ジャコ・パストリアスはまるで彼自身のルーツや音楽的な原点を再訪するかのように、もうひとつカリブ海の沿岸地域の音楽をジャズの中に率先的に導入していた。キューバのようなカリブの音楽といえば、まずはじめにブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブが思い浮かぶが、ジャコ・パストリアスの場合は、フリージャズのような刺激的なジャズの形式と融合させた。同じアルバムの「Crisis」のような楽曲に、その影響を発見することが可能である。
一時期、彼は、ショーバンドのメンバーとなったあと、観光船のバンドに入ったことがあった。そして、メキシコ、ジャマイカ、バハマ、ハイチなどを訪問し、多彩なラテン音楽を自分の音楽的な糧としていった。彼は、実際、これらの土地で現地のミュージシャンと親しくなり、ラテン音楽の手ほどきを受けた。「音楽的な仕事はしなかったけど、かなり勉強になった」というジャコ・パストリアスの言葉には、表面的なもの以上の奥深い意味が含まれている。未発表の作品やライブ盤を除いて、わずか二作のスタジオ・アルバムしか録音しなかったジャコ・パストリアス。以降の時代を生きていれば、もちろん、ECMの録音を遺しただろうし、ラテン音楽の世界的な普及にも努めたに違いない。少なくとも、そういった心残りを補うために、上記の二作のアルバムは存在する。いや、それ以上の価値があるのではないだろうか。




















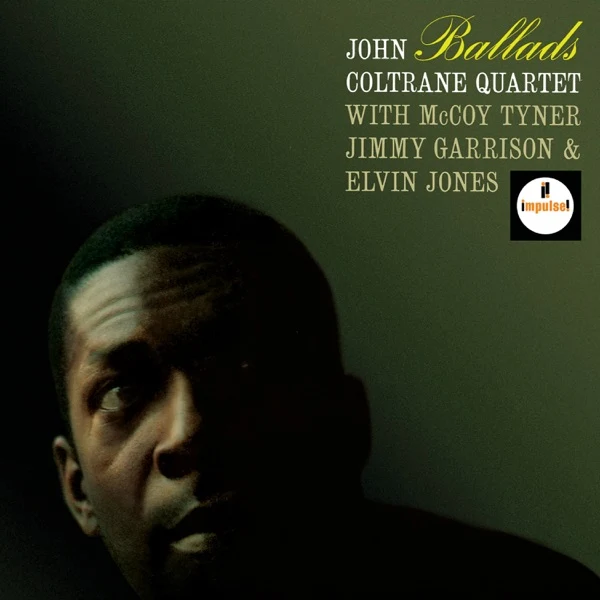


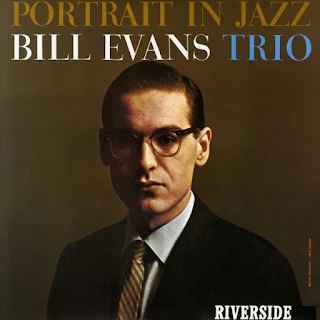







.jpg)













