Squid 『Cowards』
 |
Label: Warp
Release: 2025年2月7日
Review
最もレビューに手こずった覚えがあるのが、Oneohtrix Point Never(ダニエル・ロパティン)の『Again』だったが、ブリストルのポストパンクバンド、Squidの『Cowards』もまた難物だ。いずれも、Warpからの発売というのも面白い共通点だろう。
そして、いずれのアルバムも成果主義に支配された現代的な観念からの脱却を意味している。スクイッドは無気力と悪魔的な考えがこのアルバムに通底するとバンドキャンプの特集で語った。また、サマーソニックの来日時の日本でのプロモーション撮影など、日本に纏わる追憶も織り交ぜられており、日本の映像監督が先行曲のMVを制作している。従来、スクイッドは、一般的なロンドンのポストパンクシーンと呼応するような形で登場。同時に、ポストパンクの衝動性というのがテーマであったが、ボーカルのシャウトの側面は前作『O Monolith』から少し封印されつつある。それとは別のマスロックの進化系となる複雑なロックソングを中心に制作している。さて、今回のイカの作品は音楽ファンにどのような印象をもって迎え入れられるのだろう。
近年、複雑な音楽を忌避するリスナーは多い。スクイッドも、時々、日本国内のリスナーの間でやり玉に挙げられることもあり、評論家筋の評価ばかり高いという意見を持つ人もいるらしい。少なくとも、最新の商業音楽の傾向としては、年々、楽曲そのものが単純化されるか、省略化されることが多いというデータもあるらしい。また、それはTikTokのような短いスニペットで音楽が聞かれる場合が増加傾向にあることを推察しえる。ただ、音楽全体の聞き方自体が多様化しているという印象も受ける。以前、日本のTVに出演したマティ・ヒーリーは短いスニペットのような音楽のみが本質ではないと述べていた。結局、音楽の楽しみ方というのは多彩化しており、簡潔な音楽を好む人もいれば、それとは反対に、70年代のプログレッシヴロックのような音楽の複雑さや深みのような感覚を好き好むと人もいるため、人それぞれであろう。ちゃちゃっとアンセミックなサビを聞きたいという人もいれば、レコードで休日にじっくりと愛聴盤を聞き耽りたいという人もいるわけで、それぞれの価値観を押し付けることは出来ない。
一方、スクイッドの場合は、間違いなく、長い時間をかけて音楽を聞きたいというヘヴィーなリスナー向けの作品をリリースしている。また、『Cowards』の場合は、前作よりも拍車がかかっており、まさしくダニエル・ロパティのエレクトロニクスによる長大な叙事詩『Again』のポストロックバージョンである。スクイッドは、このアルバムの冒頭でチップチューンを絡めたマスロックを展開させ、数学的な譜割りをもとに、ミニマリズムの極致を構築しようとしている。
スクイッドはアンサンブルの力量のみで、エキサイティングなスパークを発生させようと試みる。バンドが語るアパシーという感覚は、間違いなくボーカルの側面に感じ取られるが、バンドのセッションを通じてアウトロに至ると、そのイメージが覆されるような瞬間もある。それは観念というものを打ち破るために実践を行うというスクイッドの重要な主題があるわけだ。激動ともいえるこの数年の大きな流れからしてみれば、小市民は何をやっても無駄ではないのかという、音楽から見た世界というメタの視点から、無気力に対して挑もうとする。これが「Crispy Skin」という日常的な出来事から始まり、大きな視点へと向かっていくという主題が、ミニマリズムを強調した数学的な構成を持つマスロック、そしてそれとは対象的な物憂げな雰囲気を放つボーカルやニューウェイヴ調の進行を通じて展開されていく。この音楽は結果論ではなく、「過程を楽しむ」という現代人が忘れかけた価値観を思い出させてくれるのではないか。
以前、ピーター・ガブリエルのリアル・ワールド・スタジオ(実際はその近くの防空壕のようなスタジオ)で録音したとき、スクイッドは成果主義という多くのミュージシャンの慣例に倣い実践していたものと思われる。だが、このアルバムでは彼等は一貫して成果主義に囚われず、結果を求めない。それがゆえ、非常にマニアックでニッチ(言葉は悪いが)なアルバムが誕生したと言える。その一方で、音楽ファンに新しい指針を示唆してくれていることも事実だろう。
そして「プロセスを重視する」という指針は、「Building 500」、「Blood On The Boulders」に色濃く反映されている。ベースラインとギターラインのバランスを図ったサウンドは、従来のスクイッドの楽曲よりも研ぎ澄まされた印象もあり、尚且つ、即興演奏の側面が強調されたという印象もある。いずれにしても、ジャジーな印象を放つロックソングは、彼等がジャズとロックの融合という新しい節目に差し掛かったことを意味している、というように私自身は考えた。
続く「Blood On The Boulders」では、ダークな音楽性を通して、アヴァンギャルドなアートロックへと転じている。ハープシコードの音色を彷彿とさせるシンセのトリルの進行の中で、従来から培われたポストパンクというジャンルのコアの部分を洗い出す。この曲の中では、女性ボーカルのゲスト参加や、サッドコアやスロウコアのオルタネイトな性質を突き出して、そしてまるで感情の上がり下がりを的確に表現するかのように、静と動という二つのダイナミクスの変遷を通じて、スクイッドのオリジナルのサウンドを構築するべく奮闘している。まるでそれは、バンド全体に通底する”内的な奮闘の様子”を収めたかのようで、独特な緊張感を放つ。また、いっとき封印したかと思えたジャッジのシャウトも断片的に登場することもあり、これまで禁則的な法則を重視していたバンドは、もはやタブーのような局面を設けなくなっている。これが実際的な曲の印象とは裏腹に、何か心がスッとするような快感をもたらすこともある。
同じように、連曲の構成を持つ「Fieldworks Ⅰ、Ⅱ」では、ハープシコードの音色を用い、ジャズ、クラシックとロックが共存する余地があるのかを試している。もっとも、こういった試みが出来るというのがスクイッドの音楽的な観念が円熟期に達しつつある証拠で、アンサンブルとしての演奏技術の高いから、技巧的な試みも実践出来る。しかし、必ずしも彼等が技巧派やスノビズムにかぶれているというわけではない。
例えば、「Ⅰ」では、ボーカルそのものはスポークワンドに近く、一見すると、回りくどい表現のように思えるが、ハープシコードの対旋律的な音の配置を行い、その中でポピュラーソングやフォーク・ソングを組み立てるというチャレンジが行われている。そして「Ⅰ」の後半部では、シンセによるストリングスと音楽的な抑揚が同調するようにして、フィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」のオーケストラストリングを用いて、息を飲むような美しい瞬間がたちあらわれる。この曲では必ずしも自己満足的なサウンドに陥っていないことがわかる。ある意味では、音楽のエンターテインメント性を強調づけるムーブメントがたちあらわれる。
また、「Ⅱ」の方では、バンドによるリズムの実験が行われる。クリック音(メトロノーム)をベースにして、リズムから音楽全体を組み上げていくという手法である。また、その中にはジャズ的なスケール進行から音楽的な細部を抽出するというスタイルも含まれている。一つの枠組みのようなものを決めておいて、そのなかでバンドメンバーがそれぞれ自由な音楽的表現を実践するという形式をスクイッドは強調している。それらがグラスやライヒのミニマリズムと融合したという形である。それが最終的にはロックという視点からどのように構築されるかを試み、終盤に音量的なダイナミクスを設け、プログレやロック・オペラの次世代にあるUKミュージックを構築しようというのである。試みはすべてが上手くいったかはわからないけれども、こういったチャレンジ精神を失えば、音楽表現そのものがやせほそる要因ともなりえる。
以後、楽曲自体は、聞きやすい曲と手強い曲が交互に収録されている。「Co-Magnon Man」ではロックバンドとしてのセリエリズムに挑戦し、その中でゲストボーカルとのデュエットというポピュラーなポイントを設けている。シュトックハウゼンのような原始的な電子音楽の醍醐味に加えて、明確に言えば、調性を避けた十二音技法の範疇にある技法が取り入れられるが、一方で、後半では珍しくポップパンクに依拠したようなサビの箇所が登場する。明確にはセリエリズムといえるのか微妙なところで、オリヴィエ・メシアンのような「調性の中で展開される無調」(反復的な楽節の連続を通して「調性転回」の技法を用いるクラシック音楽の作曲方法で ''Sequence''と言う)というのが、スクイッドの包括的なサウンドの核心にあるのだろう。これらの実験音楽の中にあるポップネスというのが、今後のバンドのテーマになりそうな予感だ。また、ギターロックとして聞かせる曲もあり、タイトル曲「Cowards」はそれに該当する。ここでは、本作のなかで唯一、ホーンセクション(金管楽器)が登場し、バンドサウンドの中で鳴り響く。アメリカン・フットボールの系譜にあるエモソングとしても楽しめるかもしれない。
どうやら、アルバムの中には、UKの近年のポストロックやポストパンクシーンをリアルタイムに見てきた彼等にしか制作しえない楽曲も存在する。「Showtime!」は、最初期のBlack Midiのポスト・インダストリアルのサウンドを彷彿とさせ、イントロの簡潔な決めとブレイクの後、ドラムを中心としたスムーズな曲が繰り広げられる。そして、アルバムの序盤から聴いていくと、観念から離れ、現在にあることを楽しむという深い主題も見いだせる。そのとき、スクイッドのメンバーは、おそれや不安、緊張から離れ、本来の素晴らしい感覚に戻り、そして心から音楽を楽しもうという、おそらく彼等が最初にバンドを始めた頃の年代の立ち位置に戻る。
アルバムの最後では、彼等のジャンルの括りを離れて、音楽の本質や核心に迫っていく。ある意味では、積み上げていったものや蓄積されたものが、ある時期に沸点のような瞬間を迎え、それが瓦解し、最終的には理想的な音楽に立ち返る。その瞬間、彼等はアートロックバンドではなくなり、もちろんポストパンクバンドでもなくなる。しかし、それは同時に、心から音楽をやるということを楽しむようになる瞬間だ。「Cowards」は、音楽的に苦しみに苦しみ抜いた結果にもたらされた清々しい感覚、そして、次なるジャイアント・ステップへの布石なのである。
82/100
Best Track 「Blood On The Boulders」








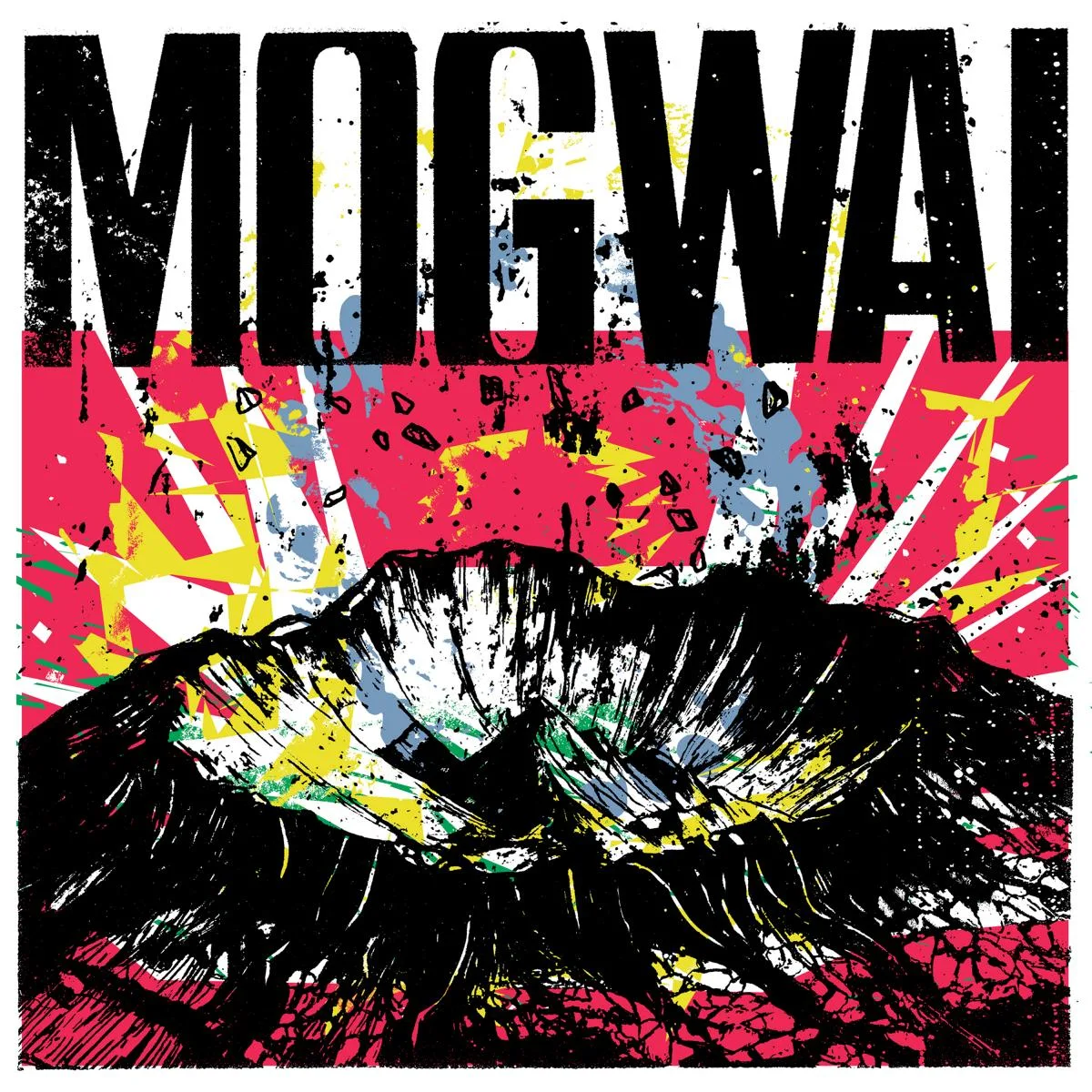



























.jpg)














