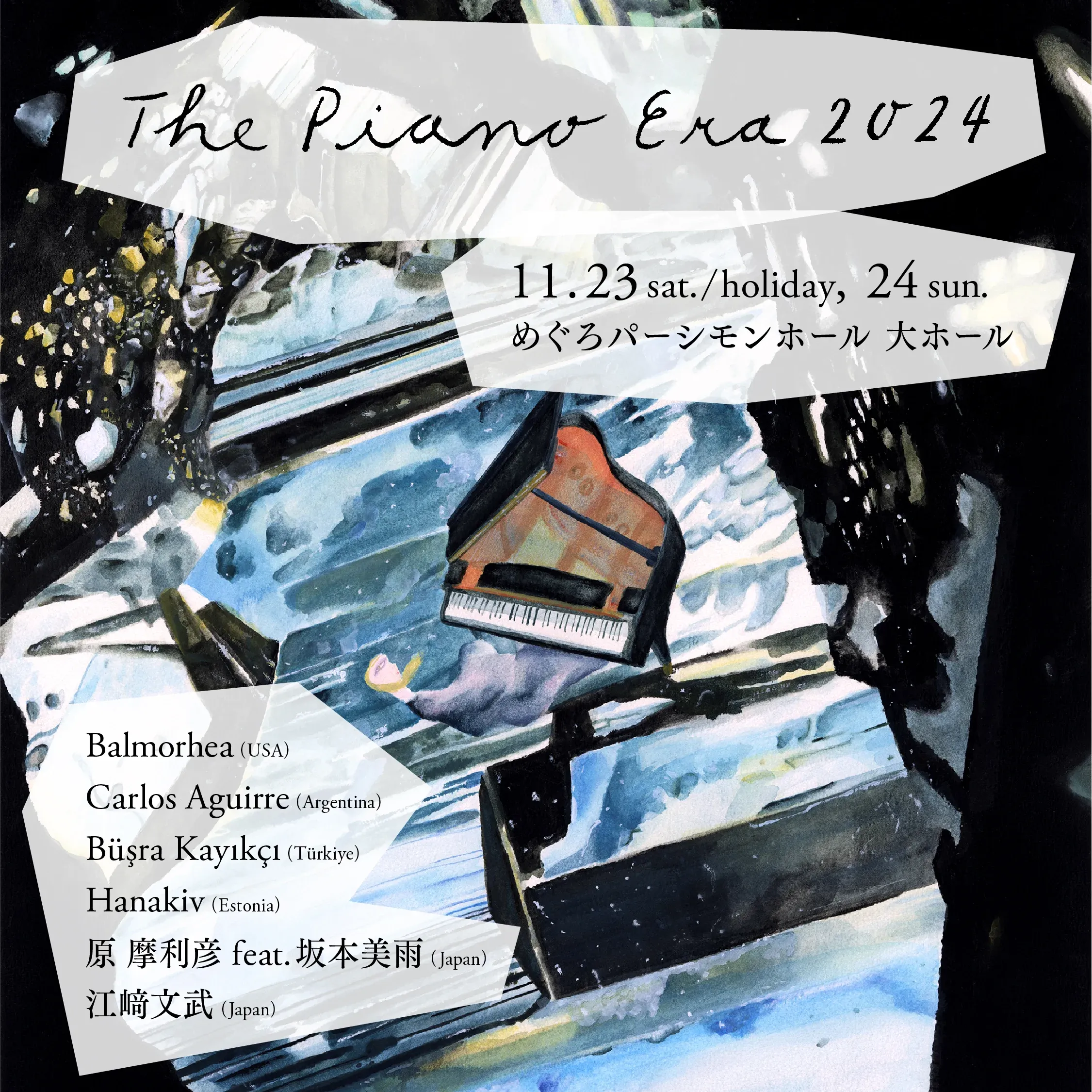|
テキサスの3人組、Being Dead(ビーイング・デッド)は入り口の作り方を心得ている。彼らの新譜『EELS』の最初の数秒で、「Godzilla Rises」の明るくハードなギター・ラインは映画のような即興性を呼び起こし、海底から出現した生物がキャンディでフリーキーなストップモーションで登場する。
ビーイング・デッドのレコードはモザイクのようであり、テクニカラーの呪文のようであり、それぞれの曲が自己完結した小さな宇宙のようである。夢のような『EELS』は、ビーイング・デッドというデュオの深層心理をさらに探っているが、最も重要なのは、2024年、テキサス州オースティンの小さな家に引きこもっているファルコン・ビッチとスムーフィー、2人の真のフリーク・ビッチによる、喜びと予期せぬ旅である。
ジョン・コングルトン(グラミー賞受賞プロデューサー)とのレコーディングのため、彼らはロサンゼルスに2週間滞在し、出発の数日前までレコードのための曲作りを行った。コングルトンは、彼らが新しいやり方を見つけ、ソングライティングの核となる部分を何層にも剥がす手助けをしてくれた。
ビーイング・デッドは、デュオから、ベーシストのリッキー・モット(彼を加えたトリオに成長した。「Rock n' Roll Hurts」での笑い声で、このレコードで彼はついに不滅の存在となった。
その結果、『EELS』はよりダークなレコードとなり、より悪魔的な内面を引き出した。失恋あり、興奮あり、魅惑あり、ダンスあり.....。ファルコン・ビッチとスムーフィーは、どの曲でも同じことを2度やりたがらない。「Firefighters」のガレージロックのようなディストーションから、ハンドレコーダーで録音されたデモの形で登場する「Dragons II」まで、予想外だが直感的である。そして最も大切なのは、ビーイング・デッドが唯一無二の存在であるということ。
その動物の名前(うなぎ)が示すように、【EELS】の曲は柔和で、レコードは濁った水や奇妙な夢の中をそぞろ歩くようであり、その動きは神秘的で美しく、揺らめくような光沢を映し出す。全16曲を聴いていると、新しい洞窟を発見するような、もしくは、未知の深みに飛び込むような、それと同時に、完全にオープンハートな気分になる。
アーティストのジュリア・ソボレヴァが描いたアルバムのアートワークには、奇妙な妖怪が描かれている。それは『ビーイング・デッド』を象徴するのにふさわしく、歓迎的で遊び心のあるエネルギーを発散している。たとえ何か不吉なものがその向こうに潜んでいたとしても。
Being Dead 『EELS』 知られざるアメリカ 奇妙なユーモアの救い
 |
その時代錯誤なサウンドは明らかに度を超しているが、ローリング・ストーンズの最初期のような作風は魔術的な魅力を持つ。サイケ、ガレージロック、サーフロック、ヨットロック。この3人組は持ちうる音楽的な駆使し、この世で最もマニアックなサウンドに挑んでみせている。まさしく「Desert Sand」を引っ提げて登場したBeach Fossils(ビーチ・フォッシルズ)のデビュー当時のことを想起させる。
サンフランシスコと並んでサイケデリックカルチャーの要衝地であるテキサスからは、時代を問わず、奇妙なバンドが登場することがある。ビーイング・デッドは、バットホール・サーファーズのカオティック・パンクと同じように、「一体、どこからこんな音楽が出てくるのか?」と首を傾げさせる。東海岸と西海岸の文化に絶えずもみくちゃにされ、かき回され、翻弄されつづけた挙句、「これはやばい!」と思い、生き残るために突然変異をするしかなくなった……。ビーイング・デッドは、ザ・ロネッツ、ディック・デイル、ストーンズ、ソニックス、ビーチ・ボーイズ、ラモーンズ、ディーヴォ、ディッキーズ、少年ナイフ、X、これらを全部結びつけ、西海岸の70'sのフラワームーブメントやヒッピームーヴメントを復刻しようと試みる。
本作はカルト的なレコードであることは否めない。ただ、若さゆえの馬鹿騒ぎはなく、内輪向けのナードな騒ぎ方でもんもんとしており、ある意味ではリンダ・リンダズとは正反対のサウンドで、万人受けはしない音楽なのかもしれない。笑い方も「ハハハ」ではなく、「ヘヘヘ」といった照れ笑い。しかし、最初の内的なエナジーは16曲を通じて、まったく印象が変化していき、本作の最後では晴れやかな印象を持って終わる。卓越性や商業性を度外視した上で、心ゆくまで彼らが理想とする音楽を追求した結果が、このアルバムには顕著な形で表れている。
『EELS』のアルバムのアートワークに描かれているのは、地球外生命体のようでもあり、可愛らしい怪物のようでもある。頭上に奇妙な電飾を持ち、また、同じような不思議な生物を従え、解釈次第では、奇妙な存在感を際立たせている。しかし、これらの奇妙な化け物たちは、なぜか、オディロン・ルドンが描き出す怪物のように、不気味で恐ろしくも可愛らしい感じがある。奇異な存在なのに、なぜか温かさに満ちている。これはトリオの音楽性にも当てはまる。そして、タイトルのウナギのように、3人の曲や演奏、そしてボーカルが水の中を揺れ動く。それはまた未確認飛行物体が空を舞うようでもあり、海中をゆらめく海藻のようでもある。
これらのカルトロックは、アンダーグラウンドに潜り続けたことで生み出されたものである。彼らは深く潜りすぎたため、地上に戻ってこられるかが不透明であるが……。また、同時に、東海岸と西海岸の音楽が徹底して未来か過去に潜っていく中、もうひとつの知られざるアメリカの姿を、トリオは本作の音楽に反映させている。彼らは、バイラル・ヒットやインスタ映えから目をちょっとだけ背ける見栄や体裁とは無縁の愛すべきタイプだ。ナード・ロック、そう言えば身もふたもないかも知れないが、ある意味では、現代の多くのオルタナティヴロックバンドが忘れてしまった何かを持ちあわせている。オルタナはヒップであるのはかなり例外的であって、本来は内輪向けのためのものであることを忘れてはいけない。そういった中で、ビーイング・デッドはあらためて最初期のガレージ・パンクのような形で、ロックの魅力に迫ろうとする。もちろん、それは内輪向けの音楽の延長線上にあり、それ以外の何物でもないのだ。
そういったマニア向けの音楽に親しみやすさと近づきやすさをもたらしているのが、60、70年代のシスコのサイケや、あるいはカルフォルニアのフラワームーブメントのようなヒッピーやラブ・アンド・ピースに根ざした平和主義的な考えだ。これらは西海岸の文化への親しみを表す。これらの文化はほかでもなく、資本主義社会が先鋭的になっていく中で、金銭的な価値とは相異なる新たな発想を追求しようというのが至上命題であった。その中にある共同体やリベラル思想は飾りのようなもので、これらの文化の核心にあるわけではなかった。UCLAの学生は、ヘッセの急進的な小説「荒野のおおかみ」に触発され、組織に属さないDIYのスタンスを保ちながら、これらの新自由主義の根本を構築しようとしていたのだった。それはある意味では、資本主義社会の基本的な構造である「ピラミッドの階層」への強固な反駁を意味していた。それらは中世ヨーロッパの「コミューン」のような共同体としての役割を持っていたのだった。
「Godzilla RIses」
アルバムのオープニングを飾る「Godzilla Rises」を聞くと、フラワームーブメントの平和主義の思想を想起させ、それ以降のニューエイジ思想の根幹をなすワンネス的な考えをふと呼び起こすこともある。これらは結末としては、レノン&ヨーコが世界的に提示したようなラブ・アンド・ピース思考へと直結した。これらの動向は、 しかしながら、資本家や大衆を操作する類の人々にとっては、都合が悪かった。そして最終的に、これらの独自の共同体は解体されることになる。また、アフリカでも同年代に、フェラ・クティ(エズラ・コレクティヴの祖である)は、独自の国家を建国していた。これもまたヒッピー主義と同じように「ハリボテで空想的」に過ぎなかったが、アフロソウルの先駆者は、表現自体が商業主義に絡め取られていくのを頑なに拒否し、アフリカの民族性がヨーロッパ主義に植民地化されぬように徹底して反抗していたのだった。つまり、クティは音楽を作っても、権力者に魂を売ったことは一度もなかった。
これらのアンチテーゼや体制に対する反抗心を持った表現者がどれほどいるのだろうか。社会に順応することを示すことだけが音楽ではなく、主流派への賛同を示すために表現があるわけでもなければ、承認欲求のためだけに芸術があるわけではない。少なくとも、「お花畑思考」とエリート主義者から揶揄されながらも、1970年代の人々は、自主性を持って生きようとしていたのだったし、従属的な存在になることを是としない思考力もあったのである。そして、このアルバムは、そういった「人間としての自律性」を再び蘇らせるものである。まるでビーイング・デッドは、マーク・トウェインの名言をなぞらえるかのように、「主流派は常に間違っている」といわんばかりに、われわれの中に内在する盲信や虚妄を打ち砕こうとするのだ。
オハイオのDEVOの前衛性、それらはイギリスのニューウェイヴ、ドイツのバウハウス運動以降の前衛主義と呼応していた。これらのニューウェイブのグループは、機械産業の中で生きる人間らしさを主張し、スチームパンクやSFのようなカルチャーを飲み込み、未来志向のサウンドを制作したが、それと同時に「ロボットにはならない」と逆説的に主張していた。それらがUSのニューウェイブ、カルフォルニアのパンクの原点になった。
「Van Goes」は、その系譜に属する。WIREの『Pink Flag』(マイナー・スレットの音楽性のヒントになった)のポスト・パンクや不協和音を踏まえ、それらを西海岸の80年代のカルフォルニアのパンクサウンドのテイストを加える。さらに、彼らはそれらを古典的なガレージ・ロック、ストーナー・ロックと結びつけて、プリミティヴなロックの魅力を呼び覚ます。さらに、2010年代のニューヨークのベースメントのサーフロックやシューゲイズとかけ合わせ、現代的なサウンドに近づいてゆく。全般的には、Wet Legのようなサウンドに接近していくのだ。
これらの古典的なロックのスタイルは、曲ごとに自由な気風を以て少しずつ変化していき、タイトルのウナギのように、うねうねと少しずつ匍匐前進していくような感じがある。「Blanket of my Bone」では、ガレージロックとサーフロック、「Problems」では、ビートルズのようにメロトロンを使用し、 バーバンクやマージービートをリヴァイヴァルさせる。思わず「古すぎる!」と叫びたくなるような音楽ではあるけれど、聞き入らせる何かがあるのが不思議でならない。続く「Firefighters」は、Boys、Sonicsのような最初期のガレージ・サウンドを受け継ぎ、それらをニューヨークのSwell Maps、ベルファストのStiiff Little Fingersのようなパンクサウンドで縁取っている。エッジの効いたギターにYo La Tengoのようなボーカルとコーラスが合わさる。
「Firefighters」
その後、Being Deadのオールドスクールのタイプの楽曲はさらに時代を遡っていくかのようだ。それにつれて感覚としての音楽もより深い場所へと潜り込んでいく。
「Dragons Ⅱ」では、バーバンク・サウンドとサイケフォーク、「Nightvision」では、ローリング・ストーンズのフラワームーブメントのロックソングという形で続いていく。しかし、これらの曲は、単に音楽性をなぞらえるにとどまらず、これらのジャンルの特徴である若者の多感さや孤独感や内的な暗さといった感覚的な何かを巧みに掴んだ上で、ジャンクなサウンドに落とし込んでいるのが秀逸である。それは、瞑想的な感覚を擁する70年代のロックの再構成のような意味を持つ一方、ウッドストックやワイト島のライヴといった原初的な音楽フェスティバルに存在したヒッピー主義や平和主義的な思想は、ロックンロールの幻惑や陶酔へと繋がる。
「Gazing at Footwear」はサイケロックやシューゲイズの系譜にある一曲で、ボーカルも4トラックで録音したような古臭さ。しかし、同時に、ビンテージな魅力があり、フリークの心をくすぐる。そしてもうひとつのガールズバンドのような雰囲気が漂う瞬間もある。「Big Bovine」はサーフロックとカルフォルニアパンクを融合させ、アルバムの中で最も心楽しい瞬間を作り出す。
3人の音楽は音楽のシリアスさではなく、フランクさに重点が置かれている。そしてその気安さは時々、ユーモアに変わり、音楽の持つ開放的な感覚を象徴付ける。マック・デマルコのサイケフォークの影響を反映させた「Storybook Bay」 は、インタリュードのような役割を持つが、ボーカル曲の合間にある間奏は、彼らの音楽が自宅のガレージのライブセッションの延長線上にあることを示唆している。真面目なのか、ふざけているのか見分けづらいオペラのような声も、快活な笑いというよりも、乾いたシュールな笑いを呼び起こそうという彼らの音楽の核心を担っている。つまり、深刻になりすぎないことが、彼らの音楽を魅力的にしているのだ。
セッションの延長線上にある音楽は「Ballerina」でガレージ・パンクや、Germs、Circle Jerksのようなカルフォルニアパンクのスタイルを受け継いだオレンジ・カウンティの原初的なパンクへと変化し、LAのXのようなニュアンスを付け加えている。もちろん、これらのロックソングの基底にあるのは、ダンスのためのブラックミュージックとして勃興したロックンロールである。
これらのダンスミュージックの系譜のロールに属する「Rock n' Roll Hurts」は、最終的には「テキサスの雑多性」というバンドの重要な音楽を示し、ビーチ・ボーイズのようなコーラス・グループのサウンドや、ビバップ的なニュアンスを示している。これらは、Wrens、Yo La Tengoといった2000年代のオルタナティヴロックの系譜に属する。それにパーティサウンドのようなニュアンスを添える。しかし、それはもちろんセレブレティのために用意された音楽ではない。どちらかといえば、ナード、あるいは社会的なオタクのためのパーティソングなのである。
音楽の表現性が強ければ、救いがあるというものではない。もちろん、扇動的であるとか、即効性があるというのも、一元的な指標に過ぎないのではないか。確かにヒップなポップスは、耳障りがよく、聴きやすく、親しみやすく、乗りやすいというように、多数の利点があることは確かだが、音楽にしても、ミュージシャンにしても、使い捨てになる恐れがあるのではないか。音楽の最大の魅力は、「一般性」にあるにとどまらず、それとは対極の「独自性」に宿る場合もある。それが一般的に知られざるものであればあるほど、何らかの副次的な意義を持ちうる。
ポピュラーであれ、ダンスであれ、ロックであれ、そういったコアな音楽は、まず間違いなく商業音楽の基盤を支える重要で不可欠な存在でもある。Being Deadは、ジョン・コングルトンの助力を得て、オルタナティヴの核心を捉え、カルフォルニアの音楽に親しみを示し、サーフロックやパンクロックの側面を強調する。「Love Machine」は、少年ナイフの次世代のガールズパンクの象徴的なアンセムとなりえるし、「I Was A Tunnel」は、ベッドルームポップの知られざるローファイな側面を生かした夢想的なインディーフォーク、ドリーム・ポップの曲である。
彼らのフリーク性が最高潮に達するのが、本作のハイライト「Goodnight」となるだろうか。同曲は、サイモン&ガーファンクルのマイナー調のフォークソングをベースにし、軽妙なオルタナティヴロックを制作している。それに、楽しいテイストを付け加えることも忘れてはいない。そして、これらは、現代的な人々の心に深く共鳴する何かがあるかもしれない。もちろん、日本の人々についても同様である。それは、サイモン&ガーファンクルが生きていた時代の世相と、現代の世界情勢が重なる部分があるからである。このアルバムの最高のハイライトである「Goodnight」というフレーズには、言葉が持つ以上の強い迫力が込められている。