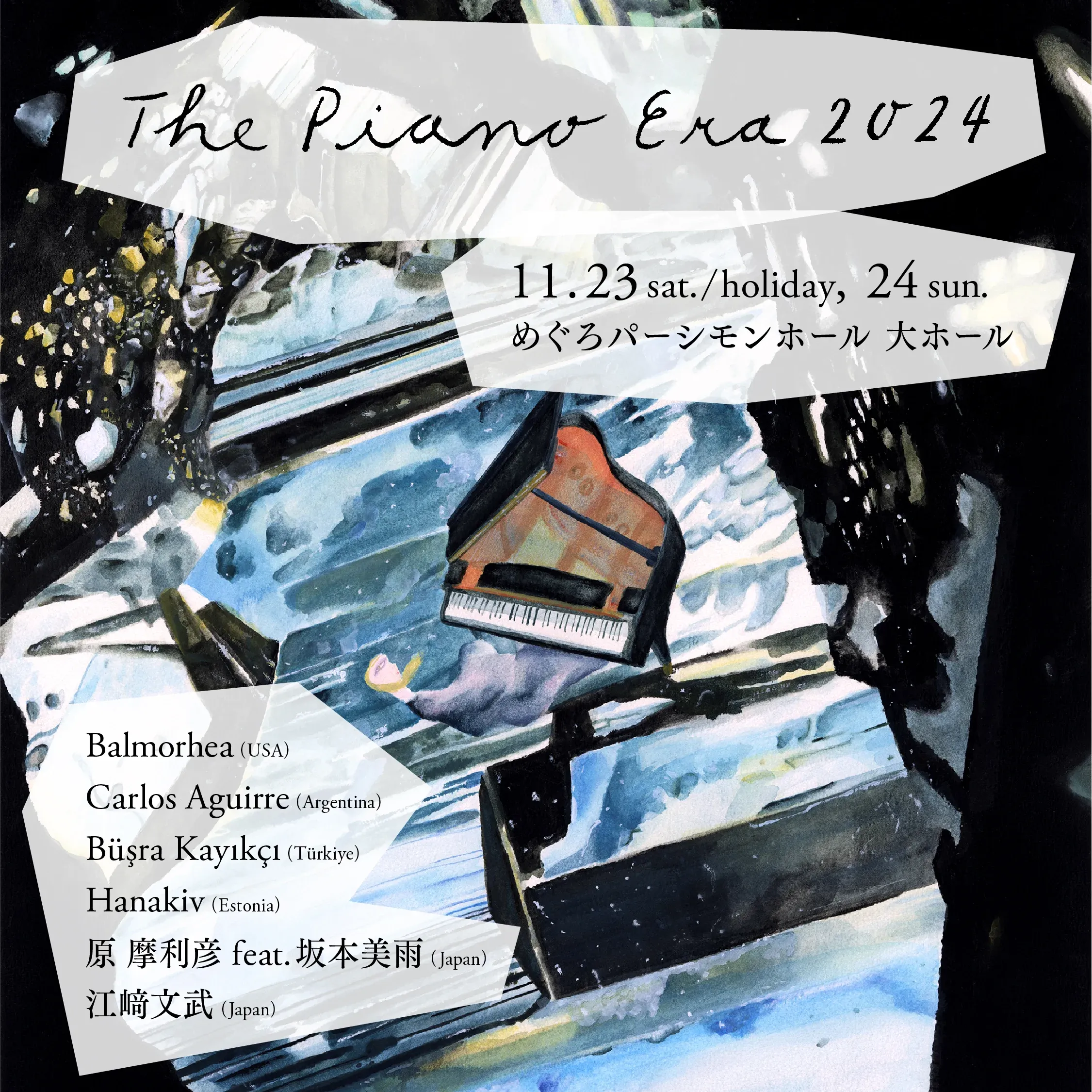|
| ©Grace Pickering |
Moonchild Sanelly(ムーンチャイルド・サネリー)は、ビヨンセやティエラ・ワック、ゴリラズ、スティーヴ・アオキなどのアーティストとコラボレートしてきた南アフリカのゲットー・ファンク・スーパースターだ。
本日、彼女は3枚目のスタジオ・アルバム『Full Moon』を2025年1月10日にTransgressive Recordsからリリースし、2025年のイギリスとアイルランドのヘッドライン・ツアーを行うことを発表した。
Full Moon』は、サネリーのユニークなサウンド、陽気なアティテュード、個性的なヴォーカル、ジャンルを超えたヒットメーカーとしての才能を披露する12曲からなるコレクションで、アルバムの最新シングルとビデオ「Do My Dance」がリリースされる。
マラウイ、イギリス、スウェーデンでレコーディングされ、ヨハン・ヒューゴ(セルフ・エスティーム、MIA、Kano)がプロデュースしたフルムーンのクラブ・レディなビートは、エレクトロニック、アフロ・パンク、エッジの効いたポップ、クワイト、ヒップホップの感性の間を揺れ動く。
「Do My Dance」で、リスナーはこのアルバムの規模と野心を知ることになる。ハイ・オクタンシーでアンセミックな「Do My Dance」は、大胆なハッピー・ハードコア・ビートに支えられた速射砲のようなヴァースと、明るく大胆なシンガロング・コーラスで、スタイルとテンポを越えて跳ね回る。
ネイト・トーマスが監督した「Do My Dance」のビデオは、ヨハネスブルグで撮影され、彼女の特徴であるティールカラーのムーンモップを冠にした、輝かしい美的センスに溢れたアーティストが登場する。
このレコードを『FULL MOON』と名付けたのは、これらの経験を生き、書くことで得た、本当に明確な感覚を伝えるためなんだ」とムーンチャイルドは語る。「『Phases』では月の満ち欠けを表現した。月が満ち欠けをするとき、月は一度に自分の一部を見せる。満月は、私全体が照らし出される。私の全自己の到着だ」
「FULL MOONは、私がここにたどり着くまでに経験しなければならなかったこと、感じなければならなかったすべての感情、経験したすべてのことの集大成です」ムーンチャイルドは続けた。「このプロジェクトには、最初から最後まですべてが凝縮されている。ケンカ、悲しみ、立ち直ること、手放すこと、許すこと、受け入れること。赦しには精神的、霊的な一体感があり、それはあなたを完全なものにしてくれる。だから私はここにいる。"FULL MOON "だ」
「Do My Dance」
Moonchild Sanelly is the South African ghetto-funk superstar who’s collaborated with artists including Beyonce and Tierra Whack, Gorillaz, Steve Aoki and more.
Today, she announces her third studio album, Full Moon, out 10 January, 2025 via Transgressive Records, along with her 2025 UK and Ireland headline tour.
Full Moon is a collection of 12 tracks showcasing Sanelly’s unique sonic fingerprint, joyous attitude, distinctive vocals and genre-bending hit-making prowess, including and the album’s latest single and video, “Do My Dance, out now.
Recorded in Malawi, the UK and Sweden, and produced by Johan Hugo (Self Esteem, MIA, Kano), Full Moon’s club-ready beats oscillate between electronic, afro-punk, edgy-pop, kwaito, and hip-hop sensibilities. With “Do My Dance,” listeners get a taste of the scope and ambition of the album. High octane and anthemic, “Do My Dance” bounces across styles and tempos, with rapid-fire verses underpinned by an audacious Happy hardcore beat, bursting into a bright, bold singalong chorus. The video for “Do My Dance", directed by Nate Thomas, was filmed in Johannesburg and features the artist in all her glorious aesthetic, crowned by her signature teal-coloured Moon Mop, watch HERE.
“I called this record ‘FULL MOON’ to convey a really clear sense that I got from living and writing these experiences,” notes Moonchild. “Phases showcased all my sides, the different phases of the moon, and this one is all those parts of me being in unison with each other. When the moon is in phases, it shows parts of itself at a time. Full Moon is me, lit up in my entirety. The arrival of my whole self. It’s the arrival.”
“FULL MOON is a culmination of everything that I needed to experience to get to this point, every emotion I had to feel, everything I went through,” she adds. “This project has it all, from beginning to end. The fights, the sadness, the getting back up, the letting go, the forgiveness, the acceptance. There’s a sense of mental and spiritual togetherness that comes with forgiveness and it makes you whole. So here I am, a FULL Moon.”
Moonchild Sanelly 『Full Moon』
 |
Label: Transgressive
Release: 2025年1月10日
Tracklist:
1. Scrambled Eggs
2. Big Booty
3. In My Kitchen
4. To Kill a Single Girl (Tequila)
5. Do My Dance
6. Falling
7. Gwara Gwara
8. Boom
9. Sweet & Savage
10. I Love People
11. Mntanami
12. I Was the Biggest Curse
*Pre-order(International): https://transgressive.lnk.to/fullmoon
UK & Europe Tour Dates 2024
31 October Tou Scene, Stavanger, NORWAY
01 November Molde Mundo, Molde, NORWAY
02 November Oslo World, Oslo, NORWAY
04 November Quasimodo, Berlin, GERMANY
05 November DE VK, Brussels, BELGIUM
06 November Le Hasard, Paris, FRANCE
07 November Op Locatie, Amsterdam, NETHERLANDS
11 November Sunflower Lounge, Birmingham, UK - SOLD OUT
12 November Rough Trade, Bristol, UK - SOLD OUT
13 November Colours, London, UK - SOLD OUT
Australia Tour Dates 2024
16 October Tumbalong Park - SXSW Sydney, SYDNEY, AUS
18 October The Lord Gladstone - SXSW Sydney, SYDNEY, AUS
18 October The Lansdowne Hotel - SXSW Sydney, SYDNEY, AUS
19 October Yah Yah’s, MELBOURNE, AUS
UK & Ireland Tour Dates 2025
18 March YES (The Pink Room), MANCHESTER, UK
20 March The Grand Social, DUBLIN, Ireland
21 March The Wardrobe, LEEDS, UK
22 March King Tut’s, GLASGOW, UK
24 March Hare & Hounds, BIRMINGHAM, UK
25 March Strange Brew, BRISTOL, UK
26 March Heaven, LONDON, UK