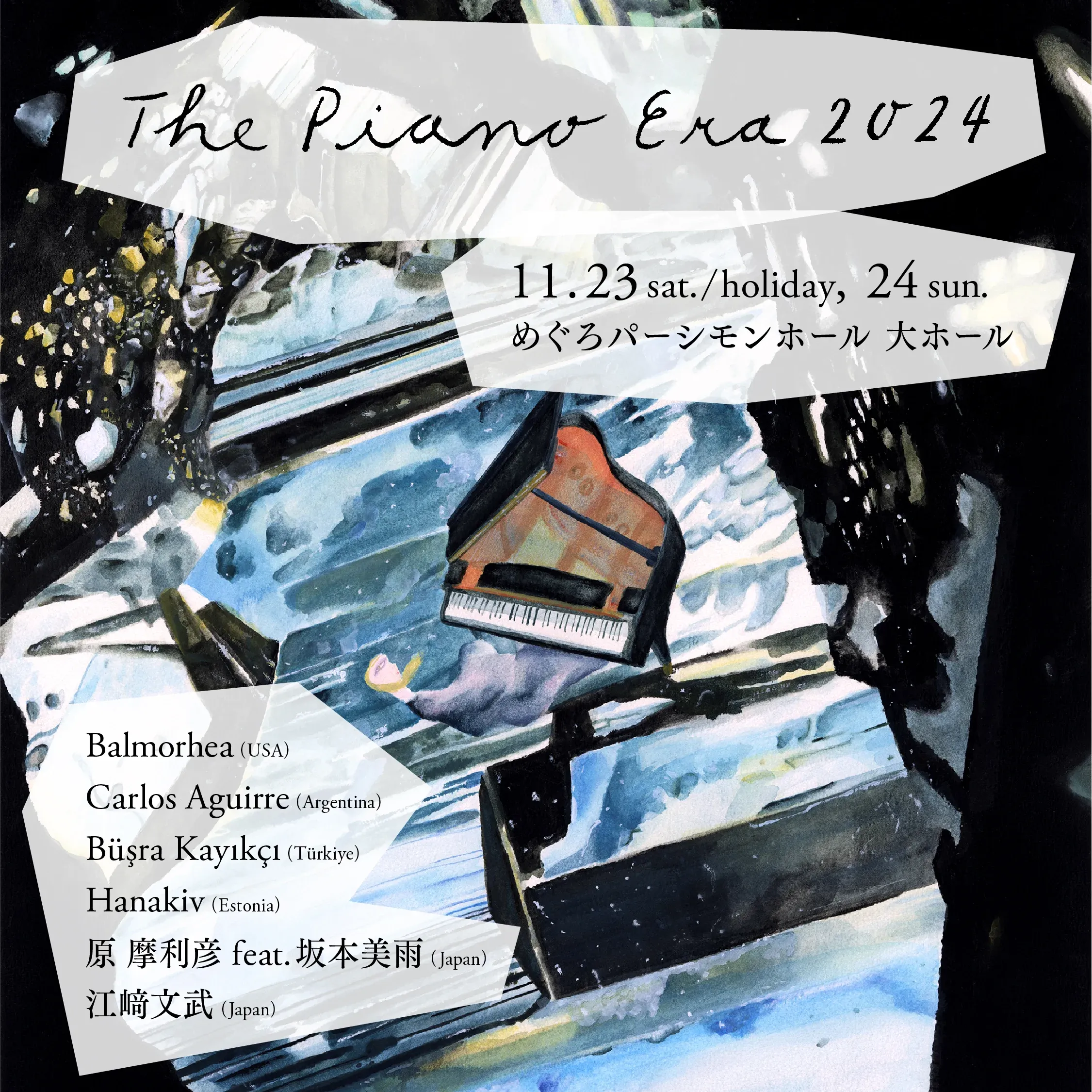・Helen Merrill(ヘレン・メリル)
 |
| Armando Peraza, Helen Merrill, Cannonball Adderley, Al McKibbon, Toots Thielmans and Oscar Peterson (reflected in the mirror), Chicago 1957 |
ヘレン・メリル(1930年7月21日ニューヨーク生まれ)は、国際的に知られる女性ジャズ・ヴォーカリストである。そして、ジャズヴォーカルの形式に革新性をもたらした。彼女のくぐもったスモーキーなボーカルは、時を越え、未来の音楽ファンの心を絆すにちがいない。
メリルの憂いに充ちたブルージーな歌声はブルージャズの代名詞である。同時に、ジャズだけではなく、米国のカントリーソングを普及させた年代もあった。そして渡辺貞夫(世界のナベサダ)、菊池雅章とのコラボレーションを見ても分かる通り、日本にボサ/ジャズを普及させた偉大な文化的な功労者でもある。日本の音楽業界には、必ずしも器楽曲への親しみが満遍なく浸透しているとは言いがたい。やはり、ボーカル曲が重要な普及のポイントだ。その点を踏まえると、ボーカルを通してジャズというジャンルを広めた功績はとても大きいように感じられる。
ヘレン・メリルは1930年、クロアチア移民の両親のもとに生まれた。14歳でブロンクスのジャズ・クラブで歌い始める。16歳になる頃にはフルタイムで音楽を始めた。1952年、メリルはジャズ・ピアニストの先駆者であるアール・ハインズのバンド(Earl Hines Band)に「A Cigarette For Company」を歌うよう依頼され、レコーディングのデビューを果たした。エタ・ジョーンズ(Etta Jones)も同じアルバムでデビューした。
「A Cigarette for Company 」と、それに続くルースト・レコード・レーベルのシングル2枚がきっかけとなり、メリルはマーキュリー・レコードの新レーベル、エマーシーと契約を結んだ。
1954年、メリルは最初の(そして今日までで最も高く評価されている)LPを録音し、伝説のジャズ・トランペット奏者クリフォード・ブラウン(Clifford Brown)とベーシスト/チェリストのオスカー・ペティフォード(Oscar Pettiford)らをフィーチャーした同名のレコードを出した。このアルバムはブラウンにとって最後のレコーディングのひとつとなり、彼はわずか2年後に交通事故で亡くなった。プロデュースとアレンジは、当時21歳だったクインシー・ジョーンズが担当。ヘレン・メリルの成功により、マーキュリーは彼女と4枚のアルバム追加契約を結んだ。
 |
ヘレン・メリルに続く1956年のアルバム『Dream of You- ドリーム・オブ・ユー』は、ビバップ・アレンジャーでピアニストのギル・エヴァンス(Gil Evans)がプロデュースとアレンジを手がけた。『ドリーム・オブ・ユー』でのエヴァンスの仕事は久しぶりのことだった。メリルの作品での彼のアレンジは、その後のマイルス・デイヴィスとの活動の音楽的基礎を築いた。
1950年代後半から1960年代にかけて散発的にレコーディングを行った後、メリルは多くの時間をヨーロッパ・ツアーに費やした。一時期イタリアでアルバムを録音し、ジャズ界の著名人チェット・ベイカー、ロマノ・ムッソリーニ、スタン・ゲッツらとライブ・コンサートを行った。1960年代にアメリカに戻ったメリルは、日本でのツアーを経て1967年に日本に移住。メリルは日本でフォロワーを増やし、その人気は今日まで続いている。日本でのレコーディングに加え、トリオ・レコードのアルバム・プロデュースや東京のラジオ局での番組司会など、音楽業界の他の側面にも関わるようになった。
メリルは1972年にアメリカに戻り、以来レコーディングと定期的なツアーを続けた。その後のキャリアでは、さまざまなジャンルの音楽を試みている。
ボサノヴァ・アルバム、クリスマス・アルバム、ロジャース&ハマースタインのレコード1枚分を中心にレコーディングしている。メリルのその後のキャリアで、過去の音楽パートナーに捧げたアルバムが2枚存在している。1987年、メリルとギル・エヴァンスは名曲『Dream of You- ドリーム・オブ・ユー』の新たなアレンジを録音した。『Collaboration-コラボレーション』というタイトルでリリースされ、1980年代のメリルのアルバムの中で最も高い評価を得た。
1987年にはCD『Billy Eckstine sing with Benny Carter』を共同制作し、ミスターBと2曲のバラードをデュエットした。1995年には亡きトランペッター、クリフォード・ブラウンへのトリビュートとして『Brownie: Homage to Clifford Brown』を録音した。
メリルのミレニアム・リリースのレコーディングのひとつは、彼女のクロアチアの伝統とアメリカ人としての生い立ちから生まれた。『Jelena Ana Milcetic, a.k.a. Helen Merrill』(2000年)は、ジャズ、ポップス、ブルースの曲と、クロアチア語で歌われるクロアチアの伝統的な曲を組み合わせた内容。
1960年11月、初の日本公演を行う。1963年にも日本を訪れ、山本邦山等と共演。1966年頃、UPI通信社(アメリカの通信社)のアジア総局長”ドナルド・ブライドン”と2度目の結婚し、それを機に日本に移住した。
以後、渡辺貞夫との共演盤『Bossa Nova In Tokyo- ボサ・ノヴァ・イン・トーキョー』、猪俣猛とウエストライナーズとの共演盤『Autumn Love- オータム・ラヴ』、佐藤允彦と共に制作したビートルズのカヴァー集『Helen Meril Sings New York- ヘレン・メリル・シングス・ビートルズ』、当時やはり日本在住だったゲイリー・ピーコックとの共演盤『Sposin'- スポージン』等を発表。その後、ブライドンと離婚し、1972年にはアメリカに帰国して音楽活動を停止するが、1976年にはジョン・ルイスとの共演盤『Jango- ジャンゴ』を発表し、活動を再開。
親日家として知られており、活動再開後は数多く来日、ライブ・コンサート活動をしている。近年では2015年に続いて、2017年4月に最後となる来日公演を行った。
また、1993年、日本映画『僕らはみんな生きている』(滝田洋二郎監督)の主題歌として、「手のひらを太陽に」を英訳してカヴァーした。クリフォード・ブラウンとの共演から40年後に当たる1994年には、『Brownie: Homage to Clifford Brown- ブラウニー〜クリフォード・ブラウンに捧げる』を発表した。『You And The Night And The Music - あなたと夜と音楽と』(1997年)ではジャズ・ピアニストの菊地雅章と共演を果たした。チェコ/プラハで録音された『Lilac Wine- ライラック・ワイン』(2003年)では、エルヴィス・プレスリー(Elvis Presley)の「Love Me Tender」やレディオヘッド(Radiohead)の「You」をカヴァーした。
2017年、ブルーノート・トーキョーの公演を最後にメリルはライブ活動から引退している。
■ヘレン・メリルの代表的なアルバム
1.『Helen Merrill』(With Clifford Brown) Verve/UMG 1955
言わずとしれたヘレン・メリルの代表作。ブルージャズの不朽の名盤でもある。トランペット奏者であるクリフォード・ブラウンを従えたバンド編成の作品。(モノトーンのオリジナル盤、青いバージョンのリマスター盤が発売されている。)モノラルながら音がクリアと定評がある。実際的に音質の鮮明さにおいて、1955年(1954年)としては画期的なレコーディングだ。
ブラウンは1954年当時、エマーシー・レコード所属の女性ボーカリストのレコーディングに度々参加しており、本作に先がけてダイナ・ワシントンやサラ・ヴォーンとも共演。なお、メリルは本作の録音から約40年後の1994年1月、トランペット奏者を迎えてクリフォード・ブラウンに捧げられた内容のアルバム『ブラウニー〜クリフォード・ブラウンに捧げる』を録音し、同作では本作からの「Don't Explain」、「You'd Be So Nice To Come Home To」「Born To Be Blue」」がリメイクされた。後に大物プロデューサーとなるクインシー・ジョーンズがアレンジを手がけている。
ヘレン・メリルは2009年のインタビューにおいて、「私は前からクインシーと知り合いだったわ。その頃の奥さんと一緒に、私の近所に住んでいたのだった。当時のクインシーは新進気鋭の若者でした。全然お金がなかった」と語っている。
『Helen Meril』は、録音現場の空気感が色濃く反映され、「真夜中の不可思議な時間」を感じさせる。つまり、1955年前後のニューヨークの永遠の夜が録音されている。専門的な批評としては、「クール・ジャズとハードバップの融合」(All Music)とも評される。
ジャズの代名詞的な「ウォーキングベース」が散りばめられ、ブラウンのしなやかなトランペットを中心とする曲やピアノを主題とする曲がバランスよく収録されている。
ハードバップを吸収したブラウンのプレイが押し出されたご機嫌な曲もあるが、このアルバムでは以降のメリルの代名詞ともなるブルージャズの憂愁に充ちたスモーキーなバラードが最大の魅力と言っても良いかもしれない。
ジャズの永遠の名曲「Don't Explain」はいわずもがな、ポピュラーとしても十分楽しめる「Yesterdays」、ニューオリンズのジャズを洗練させた「Born To Be Blue」など、聴きどころは多い。リマスターヴァージョンの方が音質や音像もクリアで、どことなく都会的な響きがある。
2.『Dream Of You』 The Verve/ UMG 1956
本作はヘレン・メリルのスタジオ・アルバムで、ギル・エヴァンスが編曲と指揮を担当した。 この録音は、エヴァンスがマイルス・デイヴィスと1957年に共演した『Miles Ahead』に先立って行われた。1987年、メリルとエヴァンスはアルバム『Collaboration』のため、そして同じ曲の新しいヴァージョンを録音するために再会した。
1992年にCD化された『Dream Of You』には、ギル・エヴァンスではなく、ジョニー・リチャーズが編曲・指揮を担当した楽曲が追加収録されている。
ヘレン・メリルのキャリアの初期の歌手としての役割は、ニューオリンズ・ジャズのブルーズの文脈をポピュラーの領域にその裾野を広げることにあった。今作では、ビッグバンドの形式をコンパクトにし、ミュージカルやブルージャズ、そしてガーランドの系譜にあるポピュラーの中間にある音楽性が選ばれている。
いわば、音楽的な文脈を広げる過程にある作品で、過去と現代のジャズを架橋する役割を果たしている。トランペット等の華やかなイメージがジャズヴォーカルとどのように組み合わされるかという点では、ブロードウェイのミュージカルに近いニュアンスを擁する。ヴォーカルそのものは、上記のセルフタイトルの系譜にあり、ブルージーで淑やかな歌声を披露している。「Any Place I Hand My Hat In My Home」では、かなりベタなブルージャズのスケール進行等も含まれている。古典的なジャズの作法を基にした、茶目っ気たっぷりのアルバムと言える。デビューアルバムよりもライブレコーディングのような位置づけにある作品と称せるだろう。
3.『The Nearness of You』 The Verve/UMG 1958
『The Nearness of You』は、ヘレン・メリルの5枚目のスタジオ・アルバムでモンロー的なイメージが打ち出されている。スタンダード・ナンバーの演奏から成るが、音源はミュージシャンの構成が全く異なる二つのセッションのものである。後から行われた1958年2月21日のセッションは、ピアニストのビル・エヴァンスやベーシストのオスカー・ペティフォードなど非常に高名なジャズ・ミュージシャンたちがフィーチャーされている。 デビュー・アルバムの頃のムーディーなジャズに回帰を果たしている。有名なジャズミュージシャンが参加しているが、意外と歌モノとしての要素が強いのが分かる。この後の時代の異なるジャンルのクロスオーバーや、ポピュラーシンガーとしての萌芽をこのアルバムに見出せる。
4.『You’ve Got A Date With The Blues』
作品の評価はすべて完璧にこなすことは難しい。何を音楽に求めるのかという点で評価が変わってくる場合があるためだ。また、その点で、できれば多数の評価を基にし判断する必要がある。ヘレン・メリルの代表的な作品は、そのほとんどが50年代後半に集中している。1959年、カントリーとジャズを融合させた『American Country Songs』では、他のジャンルに寄り道をしている。その後、発表された『You’ve Got A Date With The Blues』では、再び本格派のブルージャズへ復帰している。
ヴォーカリストとしての経験を積んだためか、少しもったいぶったような歌い方をすることもあり、賛否両論分かれるところかもしれない。ただし、デビューアルバムの頃と比べると、巧緻なボーカルを披露しているのは確か。いわば背後のバックバンドとどのように連携を取るべきなのかを熟知するようになった。
依然としてブルージャズのスタイルを多角的に追求した作品である。そして中盤から終盤にかけて聴き応えが増していくという稀有なアルバムの一つである。ヴォーカリストとしては円熟期を迎えており、歌手の全盛期の息吹を捉えられる。なおかつ、ジャズバンドとしての聞き所も用意されている。タイトル曲「You’ve Got A Date With The Blues」での巧みなアンサンブルはメリルを中心とする編成でしかなしえない。「Thrill Is Gone」ではお馴染みのアンニュイな歌声を披露している。さらに、本作の中盤では、ブルージャズとしてうっとりさせる箇所もある。とりわけ、ジャズアンサンブルとして最高の地点に到達した「Blues In My Heart」は、トランペット等のホーンに加えて、エレクトリック・ギターの演奏が加わり、豪奢な印象がある。また、以降の年代のクロスオーバーの要素の萌芽も見出すことが出来る。例えば、フレンチポップからの引用も顕著で、「Lorsque Tu M' Embarasses」はニューヨークのポピュラーにイエイエの要素をもたらしていた最初の事例なのではないだろうか。いわばファッションブランドの全盛期のパリとニューヨークの文化的な融合という側面も捉えることが出来るはず。
この後、ヘレン・メリルは、ボサノヴァやフレンチポップ、アートポップ等、クロスオーバーに積極的に取り組むようになった。この歌手の音楽的な表現は一つの地域や音楽に限定されることなく、ワールドワイドなものとなっていく。いわば世界音楽のようなニュアンスを持つに至る。
5.『Parole e musica』RCA 1960 *2012年にリマスター化
1959年にヨーロッパにわたったヘレン・メリルはイタリアに居を構え、62年まで滞在した。その間に行ったレコーディングには、『SMOG』のサントラ盤に収録されている 2曲などがありますが、これは、『SMOG』のためのレコーディングから遡ること2年、 1960年の10月から11月にかけてローマでRCAに録音したリーダー作。不朽のジャズソングにフルートのおしゃれな演奏がキラリと光る。
日本では『ローマのナイトクラブで』というタイトルで知られている。このアルバムで、メリルはサントラ盤同様ピエロ・ウミリアーニと共演している。ウミリアーニの編曲とピアノ、ニニ・ロッソのトランペット、ジノ・マリナッチ のフルートなども光っていますが、何といっても絶頂期のメリルが魅力全開。モノクロ映画的な雰囲気を持ち合わせるヘレン・メリルの裏の名盤。心地よいジャズをお探しの方に最適。映画のモノローグもジャズソングの間に収録されている。