Shannon Lay

SUB POPといえば、80-90年代のシアトルのグランジシーンを牽引したアメリカでも最重要インディペンデントレーベルであることをご存知の方は多いハズ。
かつて、Nirvanaを世に送り出し、Green River、Mudhoney,TADといったシアトルグランジの代表格を数多く輩出、90年代のアメリカのインディー・ロックシーンを司っていたレコード会社です。 しかし、2010年代くらいからはアメリカではロックシーンが以前に比べると下火になったのはたしかで、近年このレーベルから90年代のような覇気を持ったバンドが台頭してこなかったのも事実。
最近のサブ・ポップはどうなってるのかと言えば、 90年代よりも取り扱うジャンルの間口が広くなっていて、近年のリリースカタログをザッと見わたした感じ、アメリカ出身のインディー・ロックのマニア向けのアーティストを取り扱っており、その中には、コアなクラブ・ミュージック、R&B系統のアーティスト、ラップ系アーティストのリリースも積極的にリリースするようになっています。
このあたりは、サブ・ポップもさすが、昨今のアメリカのインディー・シーンの売れ線に対して、固定化したシーンの一角に、一石を投ずるかのような鋭〜い狙いを感じます。その一石がどのような波紋を及ぼすのか、かつてのニルヴァーナのように、ミュージックシーンを揺さぶるようアーティストが出てくるのかは別としても、サブ・ポップが、なんとなく全盛期の勢いを取り戻したようなのを見るにつけて、熱烈なインディー・ロックファンとしては嬉しいかぎり。
さて、NYのラナ・デル・レイを筆頭に、シャロン・ファン・エッテン、エンジェル・オルセンといった個性的な面々がシーンの華やかに彩るアメリカのインディー・ロック/フォークシーンにおいて、知性の溢れる音楽を引っさげて、サブ・ポップから満を持して台頭した女性シンガーソングライターがいます。
"Shannon LAY ..." by Patrice Calatayu Photographies is licensed under CC BY-SA 2.0
作品紹介に移る前に、このシャロン・レイのバイオグラフィーについて簡単にご説明しておきましょう。 シャノン・レイは、カルフォルニア、レドンド・ビーチ出身のミュージシャン。
13歳の時からギターの演奏に親しみ、17歳の時、生まれ故郷レドンドビーチを離れて、LAに向かう。ほどなくして、Facts on Fileというロックバンドのリードギタリストとして活動。
その後、Raw Geronimoというロックバンドに参加。このバンドは、後に”Feels”と名乗るようになる。シャノン・レイはFeelsのメンバーとして「Feels」2016、「Post Earth」2019の二作のオリジナル・アルバムをリリースしていますが、レイはこのFeelsというバンドを2020年1月に脱退しています。
このロックバンドFeelsの活動と並行して、ソロアーティスト”シャノン・レイ”としての活動をはじめる。最初のリリースは、Bandcamp上で楽曲を展開した「Holy Heartache」2015となるが、この作品について「バンドキャンプで作曲した楽曲を公開しただけに過ぎず、公式な作品であるとは考えていない」と彼女自身は語っています。
その後、"Do Not Disturb"から10曲収録のスタジオ・アルバム「All This LIfe Gonig Down」を発表し、SSWとして正式にデビューを果たす。
その後、二作目のアルバム「Living Water」をWoodsist/Mareからリリース。さらに、2019年、シアトルの名門”SUBPOP”と契約を結び「August」を発表。2021年、最新作「Geist」をリリース。
この作品はアメリカの音楽メディアを中心に大きく取り上げられており、好意的な評価を受けています。他にも「Sharron Lay on Audio Tree Live」2018「Live at Zebuion」2020と二作のライブアルバムを発表しています。
Sharron Layの主要作品
「All This Life Going Down」2016 Do Not Disturb
TrackLists
1.Evil Eye
2.All This Life Going Down
3.Warmth
4.Anticipation
5.Leave Us
6.Backyard
7.Parrked
8.Ursula Kemp
9.Thoughts of You
10.Jhr
シャノン・レイの公式なデビュー作「All This Life Going Down」。フォーク音楽、あるいはケルト音楽に近い雰囲気の清涼感のある格式あるフォーク音楽としてのイメージを持つシャノン・レイは、このデビュー作にて、その才覚の片鱗を伺わせつつある。
ローファイ感あふれるインディーロックを展開しており、ディレイ/リバーブを覿面に効かせたインディー・ロックが今作では繰り広げられていますが、その中にも何となく、ケルト音楽に近い民謡的、あるいは牧歌的な雰囲気を感じさせる楽曲が多い。アメリカをはじめとする多くの音楽メディアはこの音楽について、ベッドルームポップと称しているようですが、今作は民謡的な音楽性をインディー・ロック、ローファイとして表現していると評することが出来るかもしれません。
今作においてのシャノン・レイの音楽は徹底して穏やかで知性のあふれる質感によって彩られています。ディラン、サイモン&ガーファンクルに代表されるような穏やかで詩情あふれる清涼感のあるアメリカンフォークをよりコアなオルタナティヴ音楽として現代に引き継いだと言う面で、後年のシャノン・レイの音楽性の布石となる才覚の片鱗が感じられる知性あふれるフォーク音楽。詩を紡ぐように歌われるヴォーカル、ナイロンギターの指弾きというのも真心をこめて丹念に紡がれていく。なおかつ、ゆったりした波間をプカプカと浮かぶような雰囲気があり、これは彼女の故郷、カルフォルニア、レドンド・ビーチに対する深い慕情にも似た「内的な旅」なのか。
シャノン・レイは、ボストンの”Negative Approach”をはじめとするDiscord周辺のハードコア・パンクに深い影響を受けているらしく、ロックとしての影響は、この陶然として雰囲気を湛えるインディーフォークに表面的にはあらわれていない印象を受けますが、 ハードコアパンクのルーツは、彼女のフォーク音楽に強かな精神性、思索性を与え、音楽性をより強固にしているのかも知れません。
アルバム全体として、穏やかで、まったりとした空気感の漂うデビュー作。近年のアメリカのインディーシーンには存在しなかった旧い時代の民謡にも似た温かな慕情に包まれている。
「Living Water」2017 Woodsist/Mare
TrackLists
1.Home
2.Living Water
3.Orange Tree
4.Caterpiller
5.Always Room
6.Dog Fiddle
7. The search for Gold
8.The Moons Detriment
9.Recording 15
10.Give It Up
11.ASA
12.Come Together
13.Coast
14.Sis
海際の崖に座り込むシャノン・レイを写し込んだアルバムワークを見ても分かる通り、前作の牧歌的でありながらどことなく海の清涼感を表現したような作風は、二作目「Living Waterにおいてさらなる進化を遂げています。
一作目はアメリカンフォークに対する憧憬が感じられましたが、今作はさらにその詩的な感情は、美麗なヴァイオリンのアレンジメントにより強められたという印象を受ける。
前作に続いて、ディラン直系のフォークが展開されていきますが、このストリングス・アレンジによる相乗効果と称すべきなのか、アメリカンフォークというよりケルトの伝統楽器フィドルを用いた「ケルト音楽」にも似た音楽の妙味が付加されたという印象を受けます。
このスタジオ・アルバムの表向きの表情ともいえる表題曲「Living Water」に代表されるように、前作に比べて音楽性はより内面的な精神のあわいを漂いつつ、そのあたりの外界と内界の境界線にうごめく切なさがこの音楽において、前作のようなアコースティック弾き語りのフォーク音楽により表されています。前作が爽やかさを表したものなら、より今作は、悲しみとしてのフォーク音楽が体現されているようにも思えます。
しかし、そういった主要な楽曲の中に「Caterpiller」「Always Room」で聴くことの出来る心休まる牧歌的なフォーク音楽もまたこのアルバムの見逃せない聞き所といえる。これは2020年代のアメリカの男性ではなく、女性によって紡がれる新たなフォーク時代の到来の瞬間を克明に捉えた作品。
「August」2019 Sub Pop
TrackLists
シアトルの名門インディーレーベル「Sub Pop」に移籍しての第一作「August」でよりシャノン・レイの音楽性は一般的なリスナーにも分かりやすい形となってリスナーに対して開かれたと言えるかもしれません。
二作目に続いて、ストリングス・アレンジを交えて繰り広げられるギャロップ奏法を駆使したシャノン・レイのアコースティックギターの演奏は精度を増し、トロット的な軽快なリズム性において深くルーツ音楽に踏み入れています。
もちろん、フォーク、カントリー音楽のルーツに対して深い敬意をにじませつつ、シャノン・レイの音楽はアナクロニズムに陥っているというわけではありません。そこにまた、新奇性や実験性をほんのり加味している点が今作の特徴であり魅力でもあります。さらには、レコーディングのマスタリングにおいて、豪華なサウンド処理が施され、ルーツミュージックの影響を漂わせながら、ポップ音楽として聞きやすく昇華された作品。
以前のリリース作に比べ、収録曲の一部には、サブ・ポップのレーベル色ともいうべきオルタナティヴ性も少なからず付け加えられた印象もあります。
噛めばかむほど、味わいがじわりと広がっていく渋みのあるフォーク音楽。今作ではシャロンレイの才気がのびのびと発揮されています。
大いなる自然の清涼感を感じさせる牧歌的でさわやかな雰囲気は次作の布石になっただけではなく、最早、シャロン・レイの音楽性の代名詞、あるいは重要なテーマのひとつとして完成されたというような雰囲気も伺えます。特に、今作において、シャノン・レイのシンガーとしての才覚、音楽性における魅力は華々しく花開いたといえる。
「Geist」2021 Sub Pop
TrackLists
2021年10月8日に前作と同じく「SUB POP」リリースされた「Geist」はドイツ語で「概念」の意味。
コラボレーション作で、Devin Hoff 、Tu Segallが参加、そしてプロデューサーにJarvis Taveniereを迎え入れたスタジオ・アルバムとなります。このシャノン・レイの最新スタジオ・アルバムで目を惹かれるのはサイケデリックフォークの第一人者、Syd Barretの「Late Night」のカバーのフューチャー。
アコースティックギターに歌という弾き語りのスタイルはこれまでと変わりませんが、ピアノ、エレクトリック・ピアノ、ストリングスアレンジの挿入をはじめ、パーカッションの導入にしてもかなりダイナミックな迫力が感じられる傑作となっております。
そして、以前の三作ではぼんやりとしていたような音像が今作は、より精妙なサウンド処理が施されているよりハッと目の醒めるような彩り豊かな叙情性溢れるサウンドが生まれ、そして、インディーフォーク作としてこれまでの歴代の名作と比べてもなんら遜色のない、いや、それどころかそれらの往年のフォーク作品をここでシャノン・レイは上回ったとさえ言い得るかもしれません。
これまでのレイの音楽性はより清涼感を増し、このフォーク音楽に耳を傾けていると、さながら美しい自然あふれる高原で清々しい空気を取り込むような雰囲気を感じうることができるでしょう。表題曲「Geist」をはじめ、「A Thread To Find」「Sure」と、フォークの名曲が目白押し、さわやかな癒やしをもたらしてくれるインディー・フォークの珠玉の楽曲ばかり。アルバム全体が晴れ晴れとした精妙さがあり、特に、ラストトラックを飾るインスト曲「July」を聴き終わった時には、音楽をしっかり聴いたというような感慨を覚え、音楽の重要な醍醐味、曲が終わった後のじんわりした温かな余韻を味わえるでしょう。
シャノン・レイの最新作「Geist」は、アメリカのフォーク音楽の2020年代を象徴するような作品で、これから女性アーティストのフォークがさらに盛り上がりを見せそうな予感をおぼえます。













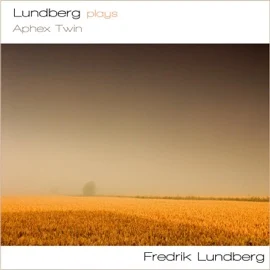


























.jpg)














