Apifera
アピフェラは、イスラエル出身のYuvai Havkin、Nitaii Hershkovis、Amir Bresler、Yonatan Albarakの四人によって結成されたジャズ・カルテット。音楽性は、電子音楽、ジャズ、民族音楽、また、オリジナルダブのような様々な音楽のクロスオーバーしたものであるといえるでしょう。
テルアビブに活動拠点を置くアピフェラは、2020年、LAの比較的知名度のあるインディペンデントレーベル”Stone Throw Records”と契約を結び、七作のシングル盤、一作のスタジオアルバム「Overstand」をリリースしています。活動のキャリアは二年とフレッシュなグループではありますが、それぞれ四人のメンバーは既にソロアーティストとしてアピフェラの活動以前に地位を確立しています。
彼ら四人の生み出す音楽性には、イスラエルという土地に根ざした概念性が宿り、西欧とも東洋とも相容れない独特な文化性によって培われたアート性が込められています。それはこの四人の音楽のバックグラウンドの多彩さにあり、イスラエルのフォーク・ミュージック、フランス近代の印象派の音楽家、モーリス・ラヴェル、エリック・サティ、スーダンとガーナの民族音楽、サン・ラのようなアヴァンギャルドジャズ、スピリチュアルミュージックまで及びます。従来の音楽スタイルを好んで聴いてきたリスナーにとっては、初めて、ポストロック界隈の音楽、あるいはまた、シカゴ音響派の音楽に接したときのようなミステリアスかつ魅惑的な音楽に聴こえるかもしれません。
イスラエル出身のアピフェラの音楽は、グループ名の由来である「蘭に群がるミツバチ」に象徴されるように、色彩豊かなサイケデリアのニュアンスも存分に感じられるはず。しかし、それは例えば、アメリカのサンフランシスコの1970年代に生み出されたサイケデリアとは異なり、アフリカの儀式音楽に根ざしたサイケデリア、西洋側の観念から見ると、相容れないような幻想性が描き出されているのが面白い。そのサイケデリア性は、全然けばけばしくもなく、どきつくもない、上品な雰囲気も滲んでいるのを、実際の彼らの音楽に耳を傾ければ、気づいていただけるでしょう。そのニュアンスは、これまで彼らがリリースしてきた作品のアルバム・ジャケットを見ての通り、ミステリアスでありながら、心休まるようなエモーションによって彩られているのです。
アピフェラの音楽は、即興演奏によって生み出される場合が多く、それがこのカルテットの音楽を生彩味あふれるものとしている。実際の作曲面においては、音の広がり、テクスチャー、音の温度差、といった要素に重点が置かれ、この3つの要素が、シンセリード、ギター、ベース、ドラム、電子音と楽器のアンサンブルの融合によって立体的に組み上げられていく。
また、オーバーダビングの手法を多用するあたりには、故リー・スクラッチ・ペリーのようなダブアーティストとの共通点も見いだされる。それから、ハウスのブレイクビーツのリズム性を取り入れたり、ジャーマンテクノのような旋律を取り入れたり、また、アバンギャルド・ジャズの領域に恐れ知らずに踏み入れていく場合もある。総じて、イスラエル、テルアビブ出身の四人組、アピフェラのサウンドは前衛的でありながら、懐かしいようなノスタルジアも併せ持っており、それは、このジャズカルテットの中心人物、Nitai Herdhkovisが語るように、「現実よりも明晰夢のような」サウンド、色彩的なサイケデリアが楽器のアンサンブルによって表現されています。
・「6 Visits」 EP Stone Throw Records
さて、今週の一枚として紹介させていただくのは、11月10日にLAのStone Throw Recordsからリリースされたばかりのイスラエル出身のアピフェラのミニアルバム「6 Visits」となります。
Tracklisting
1.Beyond The Sunrays
2.Half The Fan
3.Psyche
4.Visions Fugitives-Commodo
5.L.O.V.E
6.Plaistow Flew Out
「Beyond The Sunrays」 Listen on youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=YQwpdB4VkPA
他にも今週はブルーノ・マーズ擁するsilksonicの「An Evening At Silksonic」」が発表されたり、また、ジミー・イート・ワールドの「Futures」のライブ音源、また、KISSのデモ音源のリイシュー盤だったりと、比較的、話題作に事欠かない、今週の音楽のリリース状況ではありますが、今回、イスラエル出身のApiferaの新譜を紹介しておきたいのは、「6Visits」がミニアルバム形式でありながら、既存のヨーロッパやアジアの音楽シーンにはあまり存在しなかった前衛的作品であり、聞きやすく、スタイリッシュな格好良さもある。つまり、この作品「6 Visits」が多くのコアな音楽ファンにとって、長く聴くにたるような作品になりえるという理由です。
既に、前作のスタジオ・アルバム「Ovestand」において、異質なサイケデリックテクノ、プログレッシブテクノの一つの未来形を示してみせたテルアビブの四人組は、このEP「6 Visit」においてさらなる未知の領域を開拓しています。
このミニアルバムは、多くがインストゥルメンタル曲で占められていますが、ここに表現されているニュアンスは多彩性があり、このイスラエル、テルアビブ出身の四人組のカルテットの演奏に触れた聞き手は不思議な神秘性を感じるであろうとともに、バンド名「Apifera」に象徴づけられるように、さながら、蘭の花からはなたれる芳香に群がるミツバチのようにその音の蠱惑性にいざなわれていくことでしょう。ミステリアスな雰囲気は往年のプログレを思わせ、アバンギャルドジャズ的でもあり、ダブ的でもありと、音楽通をニンマリさせること請け合いの作品。
そこには、往年のジャーマンテクノ、また、YESのようなプログレッシブ・ロックのようなシンセサイザー音楽のコアな雰囲気が漂い、そして、ハウスのブレイクビーツを実際のドラムにより生み出すという点では、現代のイギリスあたりのフロアシーンの音楽にも通じるものがあるようです。
一曲目「Beyond The Sunrays」は、流行り廃りと関係のない電子音楽が展開されています。その他、オリジナルダブの原点に立ち戻った「Half The Fan」も、懐かしさとともに渋い魅力を兼ね備えています。
今作品に収録されているのはインストゥルメンタル曲だけではありません、三曲目「Phyche」は、ヴォーカルトラックとしてのエレクトロミュージックが展開され、ニュー・オーダーの音楽性にも近いクールさが込められているように思えます。
さらに、イスラエルの伝統的なフォーク音楽を、電子音楽の要素を交えて組み上げた「Visions Fugitives-Commodo」も、エレクトロニカをより平面的なテクスチャーとして捉え直した実験的な楽曲。また、アフリカ民族音楽を電子音楽という観点から再解釈した「Plaistow Flew Out」も、イギリスの最新のフロアシーンにも引けを取らないアヴァンギャルド性を感じていただけることでしょう。
表向きにはアバンギャルド性が強い作品ですけれど、作曲と演奏の意図は飽くまでリスナーの心地よさ、楽しませるために置かれ、もちろん、フロアで聴いて踊ってもよし、また、家でゆったり聴いても良しと、幅広い選択を聞き手に与えてくれる。全体的に見ると、新しいダンスミュージックの潮流、IDMという音楽の次なる未来形は、このアピフェラのEP作品を聴くにつけ、このあたりのイスラエル、テルアビブ周辺から出てくるのではないかと思うような次第です。
総じて、サイケデリアに彩られながらも知性溢れる作品であり、静かに聴いていると、音の持つミステリアスな精神世界の中に底知れず入り込んでいくかのような、深みと円熟味を持ち合わせた音源です。それほどイスラエルというのは多くの人にとってはまだ馴染みのない地域の音楽であるように思われますけれど、これから面白いアーティストが続々と出て来るような気配もあります。イスラエルのフロアミュージックシーンきっての最注目の作品としてご紹介致します。
・Apiferaの作品リリースの詳細情報につきましては、以下、Stone Throw Recordsの公式サイトを御参照下さい。
Stone Throw Records Offical Site













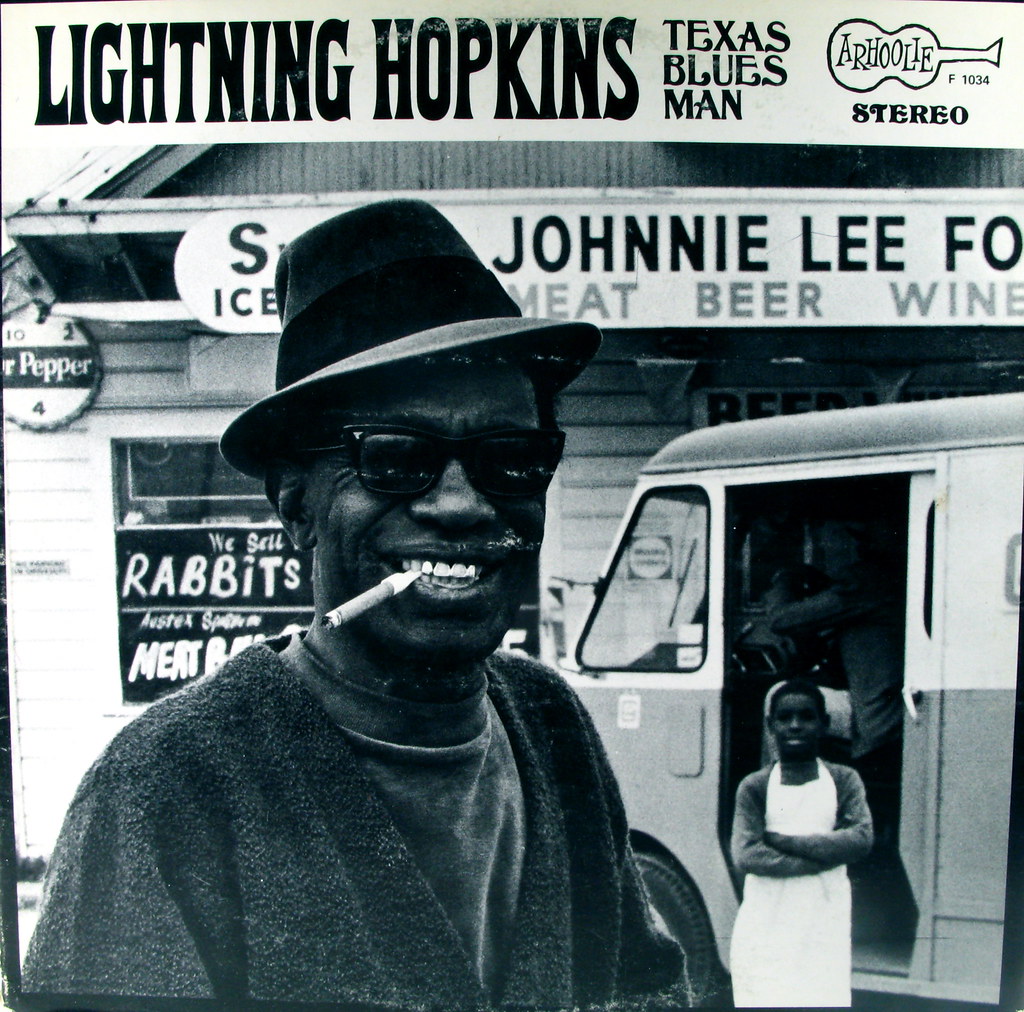











.jpg)














