アノラックサウンド スコットランド、グラスゴーを中心に形成されたギターロック音楽
皆さんは、日本で「アノラックサウンド」と呼ばれ、海外では、ギターポップ/ネオアコースティック、もしくはジャングルポップと呼ばれるジャンルをご存知でしょうか。これは、1980年代にイギリスのチェリーレッド、ラフ・トレードレコードと契約するロックバンドの一群の独特なサウンドアプローチを示している。アズテック・カメラ、オレンジジュース、ヴァセリンズ、ティーネイジ・ファンクラブ、パステルズといったスコットランドのグラスゴー周辺にこれまでになかったネオアコサウンドが発生しました。
それまで、スコットランドには、リバプール、ロンドン、マンチェスター、ブリストルのような表立ったシーンというのが存在しなかった。この1980年代を中心に、グラスゴー、エディンバラ周辺で、ミュージック・シーンが形作されていくようになる。これらのバンドの台頭は、のちの1990年代から2000年代のベル・アンド・セバスチャン、モグワイといった世界的なロックバンドの登場を後押ししたことは、殆ど疑いがありません。
かのベル・アンド・セバスチャンも、上記のバンドサウンド、ヴァセリンズとパステルズのサウンドに勇気づけられ、「グラスゴーにはネオアコあり」ということを新時代において、世界の音楽シーンに提示するため、インディー・ロックバンドを組んで演奏をはじめたのだという。
もちろん、これらの最初のスコットランドのミュージックシーンに台頭したロックバンドは必ずしも洗練されたサウンドを持ち合わせておらず、いわゆる「下手ウマサウンド」とも称されるような、ギターにしろバンドサウンドにしろ、音楽的な瞬発性というか、センスの良さで正面切ってイギリスやアメリカのミュージックシーンに勝負を挑んでみせた。
アズテックカメラ、ヴァセリンズ、パステルズといったロックバンドは、イングランドの他に、スコットランドにも重要な音楽カルチャーが存在することを世界的に証明したのだった。これはかの地の文化の発展のため、音楽表現を介してこういったミュージックシーンが徐々に1980年代を通じて形成されていったという見方もできなくはない。
アノラック、またネオ・アコースティックと呼ばれるサウンドは、街なかに教会が多く、緑豊かな街、グラスゴーらしい牧歌的な雰囲気に彩られ、新しい時代のセルティック・フォークとも称すべき独特な音楽性を擁していた。元は、イングランドよりもはるかに深い音楽的な文化を持つセルティック民謡のルーツが、これらの1980年代のロックバンドのアーティストたちに、自身の文化性における誇りを取り戻させようと働きかけたともいう向きもある。
これらのネオアコ・サウンド、ビートルズのフィル・スペクター時代の音楽性、あるいは、ボブ・ディランの初期のアメリカンフォーク時代に回帰を果たしたかのようなノスタルジックなサウンドは、おだやかさ、まろやかさもあり、反面では、ロンドンパンクのような苛烈さも持ち合わせていた。
そして、温和性と先鋭性、両極端な要素を持つネオアコ、ギターロックに属するロックバンドを中心に発展したグラスゴーの音楽シーンは、やがてイングランドに拡大していき、やがて、遠く離れたアメリカのオルタナティヴロックの源流を形作り、同じような音の指向性を持つ、Garaxie 500、Guide By Voices、Superchunk、Pixiesの音楽シーンへの台頭を促し、世界的なインディー・ロック人気を世界的に後押しました。
もちろん、日本でもこのスコットランドのグラスゴーのシーンは無関係ではないわけではなく、これらのネオアコ、ギターポップサウンドに影響を受けた、フィリッパーズ・ギター、サニーデイ・サービスがさらにこの音楽を推し進めて「渋谷系」というサブジャンルを確立した。もちろん、スーパーカーも、これらのネオアコに関係性を見いだせないわけではない。
これらのスコットランド、グラスゴーの周辺を拠点に活動していたバンドは、エレクトリックとアコースティックの双方のギターを融合したサウンドが最大の魅力だ。それに加えて、かのオアシスやブラーをはじめとする1990年代のブリットポップにも重要な影響を与えている。特に、このブリット・ポップの生みの親であり、ネオアコサウンドの代表格ともいえるThe La'sの日本公演に、その年、サマーソニックで来日していたギャラガー兄弟がそろってお忍びで観に来ていたのは、非常に有名な話である。
これらの1980年代のスコットランド、グラスゴー、エディンバラ、ロンドンのラフ・トレード、ブリストルのサラレコードを中心として発展していったギターロック/ネオアコサウンドは、なんとも美しいノスタルジアによって彩られている。
懐古的なサウンドではあるが、その1980年の世界の空気感がこれらのバンドサウンドに感じられる。その音の雰囲気、熱気、時代性というのは、どの時代の音楽にも感じられる。それが音楽やその他の表現の文化性であり、それがなければ音楽というのは途端に魅力が失われてしまう。さらに、その時代にしか生み出し得ない音楽というのが存在する。1980年代、これから世界がどうなっていくか、というような若者の不安、そしてそれとは反対の、希望、期待、ワクワクした気持ち、音楽を生み出すフレッシュな創造者たちの思いがこれらグラスゴーを中心とするアノラックサウンドには宿っている。
この奇妙な熱狂性は、今なお、独特な魅力、エネルギーを放ちつづけているように思える。ネオ・アコースティックは、その多くが既に時代に古びているサウンドといえるかもしれません。でも、その音の芸術家たちの熱い思いがこれらのサウンドには宿っていることは明確です。オルタナティヴ・ロックの前夜、あるいは、そのムーブメントの後、1980年代から1990年代にかけてのスコットランド、グラスゴーでは何が起こっていたのでしょうか?? その時代の空気感を知るために、是非、以下に取り上げていくギターロック/ネオ・アコースティックの大名盤を手掛かりにしてみて下さい。
ギターロック/ネオ・アコースティックの名盤
1.Aztec Camera
アズテック・カメラは1980年、スコットランドのイースト・キルブライド出身で当時16歳であったロディ・フレイムを中心に結成され、1995年まで活躍した。
スコットランドのネオアコサウンドを世界的なジャンルに引き上げたシーンの立役者であり、UKポップスのグループとして紹介される場合もすくなくないように思える。日本でのギターロック、ネオアコ人気に一役買った貢献者といえる。後には坂本龍一が「Dreamland」のメインプロデューサをつとめたり、また、ヴァン・ヘイレンの名曲「Jump」を揶揄を交えてカバーし、日本のメタル専門誌「BURRN!」で酷評を受けたりと話題に事欠かなかったバンドである。
アズテックカメラは、1991年にグラスゴーのインディーレーベル「ポストカード」から1stシングル「just like gold」をリリースデビューし、その後、イングランドの名門レーベル、ラフ・トレードから主要な作品の発表を行った。このバンドの織りなす、ゆるい、まったりした甘口のポップス、フォーク音楽は、後のグラスゴーシーンの重要な基盤を築き上げた。牧歌的な雰囲気もありながら、どことなく、ビートルズのマージー・ビートの時代へと回帰をはたしかのような楽曲の数々は、ニューロマンティックのような陶酔的ノスタルジックさがふんわりと漂っている。
アズテック・カメラの名盤としてはこのバンドの全盛期にあたる「High Land,High Rain」を挙げておきたい。
・「High Land,High Rain」1983 Warner Music
2.Orange Juice
オレンジジュースはスコットランド、グラスゴー近郊のベアズデンにて結成された。結成当初は、ニュー・ソニック名義で活動し、ポスト・パンクシーンの渦中に登場した。
アイルランド勢のスティッフ・リトル・フィンガーズを差し引くと、英国一辺倒であったロックシーンに、スコットランド勢として、アズテックカメラと共にスコットランドの音楽の存在を象徴付け、最初に勇猛果敢に切り込んでみせたバンドといえるだろう。1979年から活動し、1985年に解散。オレンジ・ジュースは、ネオアコ、ギターポップのゆるく、まったりした甘口なサウンドを最初に確立し、最も古いこのグラスゴーシーンの形成したロックバンドであり、グラスゴーの音楽シーンを語る上では不可欠な存在である。
1983年リリースの「Rip It Up」は、全英シングルチャート8位にランクインする等、商業的にも健闘した。
オレンジジュースの生み出すサウンドは、まさにエレクトリックとアコースティックの中間を行くもので、このネオアコのドリーミーなサウンドの最初の確立者といったとしても過言ではない。アズテック・カメラと同じように、ビートルズの初期の音楽性のようなノスタルジーに溢れ、甘酸っぱいサウンドを主要な音楽性にするという面ではパワー・ポップに近い雰囲気を併せ持っている。
オレンジ・ジュースの名盤は、イルカのイラストが描かれた「You Can't Hide Your Love Forever」が挙げられる。「Falling and Falling」をはじめポップスとして聞きやすく、粒ぞろいの楽曲が多い。アズテックカメラと同じく、日本のシティ・ポップにも比するノスタルジーな雰囲気に溢れる永遠不変の名作である。
・ 「You Can't Hide Your Love Forever」1982 Polydor Records

3.The Vaselines
ネオ・アコースティック、ギターポップのサウンドの性格を1980年代後半において象徴付けたユニット、ユージーン・ケリー、フランシス・マッキーの二人によって結成されたザ・ヴァセリンズ。
UKの53rd&3rdレコードの知名度を高めたにとどまらず、後にアメリカの名門Sub Popと契約をし、特に、カートコバーンはこのバンドの音楽性に深い薫陶を受けており、Nirvanaの主要な音楽性を形作っている。コバーンは、後に、「Molly's Lips」をパンク風のアレンジとしてカバーし、ヴァセリンズはアメリカのオルタナシーンでミート・パペッツと共に象徴的な存在となった。
ピクシーズと共に「オルタナの元祖」とみなされるヴァセリンズであるが、意外にもオルタナとして聴くと、肩透かしを食らうはずだ、ヴァセリンズのサウンドは、スコットランドらしい牧歌的で温和なサウンドを特徴とし、そこにオルタナ性、いわばブルーノートではないひねくれた特異なメロディラインをオルタナティヴロックが全盛期を迎えつつある前夜に生み出していた。
上記の要素は、シアトルのインディーレーベル、Sub Popからリリースされた「The Way Of The Vaselines」、その後に発売されたヴァセリンズのベストアルバム「Enter The Vaselines」というオルタナの不朽の名作、ネオアコの不朽の名作の一つに感じられるはずで、また、「オルタナティヴー亜流性」というロック音楽の謎を紐解くための鍵になりえるかもしれない。
特に、このヴァセリンズのベスト盤としてリリースされたアルバムに収録されている「Son Of The Gun」のイントロでの狂気的に歪んだディストーションギターは当時としてはあまりにも衝撃的だった。そして、ディストーションサウンド、それから、ピクシーズの歪んだポップセンス、さらに、同郷シアトル、アバディーンのメルヴィンズの轟音性、この3つの要素に、1980年代終盤、カート・コバーンは、グランジの萌芽、新しい音楽の可能性を見出した。もちろん、スコットランドのヴァセリンズは、アメリカのピクシーズとならんで、オルタナティヴやグランジの元祖といえる。その他にも、「Rory Rides Me Slowly」「Jesus Wants Me A Sunbeam」といった、グラスゴーの風景を思わせる秀逸なフォーク曲もこの作品には収録されている。
「Enter The Vaselines」Sub Pop

4.The Pastels
パステルズは、1981年にスティーヴン・パステルを中心に結成されたグラスゴー、ギター・ポップ/ロックの代表格と称すべき偉大なインディーロックバンド。
1982年に1stシングル「songs for children」をWhaaam!からリリースしてデビューをかざった。その後、イギリスの名門ラフ・トレードとの契約にこぎつけ、アノラックサウンドのムーブメントを牽引、それほど大きな商業的な成功こそ手にしていないが、現在、編成がユニットになっても変わらず、穏やかで、親しみやすい、インディー・ロックバンドとして活躍している。
2009年には、日本の同じくアノラック・サウンドを掲げて活動するTenniscoatsとのコラボレーション作品「Two Sunsets」もリリースしていることにも注目しておきたいところだろう。
パステルズの魅力は、スティーヴン・パステルの生み出すギターロックのセンスの良さ、それに加え、カトリーナ・ミッチェルの親しみやすく肩肘をはらない等身大のヴォーカルに尽きる。インディーフォークとロックをセンスよく融合させたという点ではヴァセリンズと同じような音楽性が見いだせる。
スコットランドの美しい緑、そして牧場の風景を思わせるような音楽性、それに加えて、どことなく甘酸っぱいような叙情性に彩られたサウンドは、イギリスのエモの発祥ともいうべき個性派サウンド。
流行り廃りとは関係なく、ことさら刺激的なわけでもない。なのに、深い親しみ、愛おしさをおぼえてしまうのが、パステルズの二人の生み出す叙情性あふれる音楽の不思議さ。アノラックサウンドの名盤としては、2013年の「Slow Summits」も粒揃いの良作として捨てがたいものの、パステルズの活動の最盛期にあたる1993年リリースされた「Trucklload Of Trouble」を挙げておきたい。
「Truckload Of Trouble」1993 Paperhouse Records
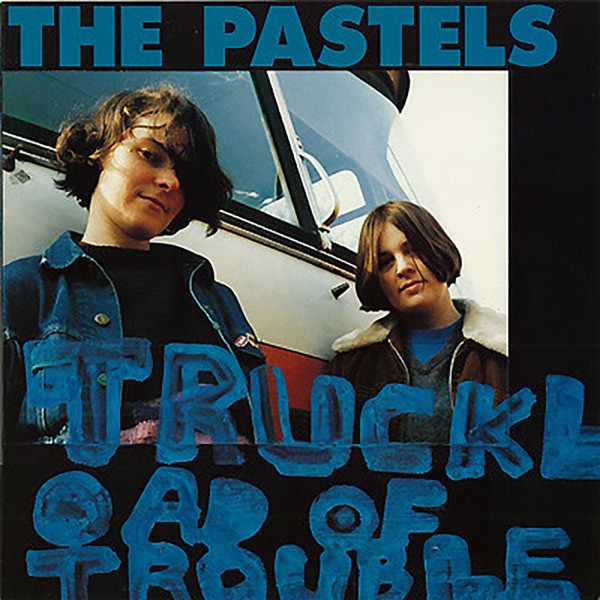
5.BMX Bandits
BMXバンディッツは1985年、スコットランドのベルズヒルにてダグラス・スチュアートを中心に結成されたギター・ポップ・バンド。現在も変わらず活躍中のアノラックサウンドのドンともいえるような存在。
後に、ティーンエイジ・ファンクラブのメンバーとなるノーマン・ブレイク、そして、後にヴァセリンズのメンバーとなるフランシス・マッキーも在籍していたという点では、スコットランドのシーンの中心的な存在といえる。このバンドからファミリーツリーを描いて、のちのスコットランドの代表格を複数登場させたという点では、シカゴのCap’NJazzに比するべき神々しい存在であり、ネオアコ、ギターロックシーンにおいての最重要バンドのひとつに挙げられる。
BMX・バンディッツのゆるく、穏やかな脱力系のサウンドは、後発のロックバンドに大きな影響を与えた。取り分け、ホーンセクション、ストリングスをスタイリッシュに取り入れた遊び心満載の音楽性は、後のスコットランドのベル・アンド・セバスチャンの音楽性、あるいは、日本のフリッパーズ・ギター、サニー・デイ・サービスをはじめとする渋谷系サウンドの源流を形作った。
BMX・バンディッツの名盤を挙げるとするなら、1993年リリースの「Life Goes On」が真っ先に思い浮かぶ。ここで、バンディッツは、まるで、涼やかな風に髪を吹き流されるかのような、切なく、淡く、爽やかなアノラックサウンド最高峰を極めた。良質なポップセンスに彩られたネオアコの傑作として名高い作品。
「Life Goes On」2005
6.Teenage Fanclub
ティーンエイジ・ファンクラブはスコットランド、グラスゴーの代表格ともいうべき偉大なインディーロックバンドである。BMXバンディッツのメンバー、ノーマン・ブレイク(Vo.Gt)を中心に、1985年に結成された。
このバンドは、ニルヴァーナの「Nevermind」の世界的なヒット、それに続く、インディーロックブームに後押しを受け、押し出されるような形で、アノラックサウンド、ギター・ポップ・アノラックサウンドの代名詞的存在となった。のちにニューヨークのマタドールレコードと契約し、ヴァセリンズ以上に、ベルセバと共にスコットランドで最も成功したロックバンドに挙げられる。
特に、このバンドはライブのステージ演出が豪華であり、まるで夢見心地にあるような瞬間をオーディエンスに提供してくれる。ティーンエイジファンクラブの音楽性は、ビートルズサウンドを現代的に再現し、それをパワー・ポップのような質感に彩ってみせた、いわばスコットランドの良心とも称するべきサウンド。ノスタルジックな雰囲気のあるチャンバーポップスの良いとこ取りの音楽性が最大の強みでもある。
ティーンエイジファンクラブの名盤としてはベタなチョイスではあるけれども、「バンドワゴネスク」をあげておきたい。このノスタルジックで、永遠不変のポピュラー音楽は、音楽にたいする無限の没入という、音楽ファンにとってこの上ない贅沢で芳醇な時間を与えてくれるはずである。
「Bandwagonesque」Geffen Records 1991
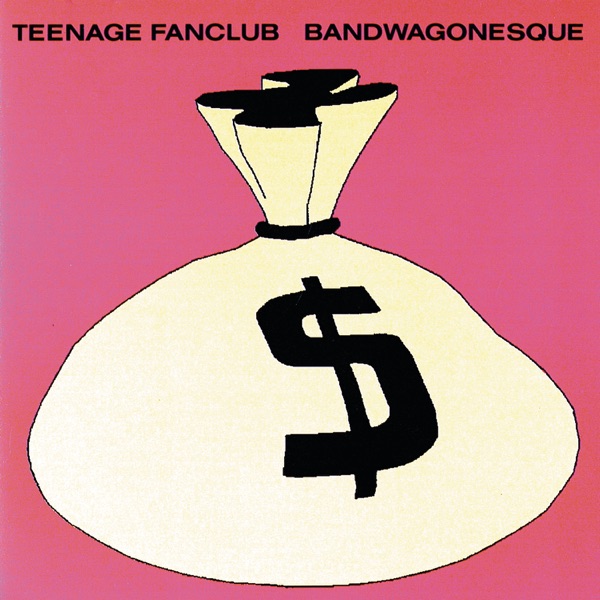
7.Belle And Sebastian
スコットランドのアノラックサウンドのシーンで満を持して登場したのがベル・アンド・セバスチャン。
教会の牧師をつとめるスチュアート・マードックを中心に1996年にグラスゴーで結成され、現在も変わらず世界的なインディー・ロックバンドに挙げられる。最初のリリース、「タイガーズ・ミルク」は千枚のプレスしか生産されなかった作品ではあるが、マニアの間ではかなりの人気となり、850ポンドのプレミアがついたという。後に、ラフ・トレード、ジープスター、マタドールを渡り歩いたという面では、およそ世界的なインディーレーベルからのリリースを総なめにしたといえる。
もちろん、ベルセバの魅力は、表向きのブランド力にあるわけではない。もちろん、ザ・スミスのアルバムジャケットからの影響性にあるわけでもない。後の全英チャートでの健闘や、ブリット・アワードのベストニューカマー賞を獲得したりといった付加的な栄誉はこの大所帯ロックバンドのほんのサイドストーリーの域を出ないように思える。ベルアンドセバスチャンが後に成功を手にしたのは、最初期からスコットランド、アノラックサウンドの後継者としてBMXバンディッツの音楽性を引き継ぎ、良質なインディー・フォークを生み出し続けたから、つまり、ベル・アンド・セバスチャンの音楽の良さから見ると、至極当然の話だったといえる。
これまでの二十年以上もの長きに渡るキャリアで、大きなブランクもなく、継続的に良質な作品をリリースしつづけているというのは、殆ど驚異的なことといえる。何かを続けることほど難しいことはないからだ。もちろん、現在も変わらず、フロントマンのスチュアート・マードックは、ステージで、はつらつとした姿を見せ続けていることにも敬意の念を表するよりほかない。
ベルセバの名盤を一つに絞るのは至難のわざである。フロントマンのスチュアート・マードックの牧師という職業にかけていうなら、ベルセバの名盤をひとつだけ挙げることは、”針の穴に糸を通すより難しい”のかもしれない。最初期には、目のくらむほどの数多くのインディー・ロックの名盤がリリースされているが、比較的最近のリリースの中にも良い作品が見受けられる。しかし、アノラックサウンドの後継者という点に絞るならば、最初のリリースの「Tigersmilk」が最適である。後のベルセバの独特な内向的なサウンドの醍醐味は、一曲目「The State I Am In」に凝縮されている。
「Tigersmilk」Jeepstar Recordings 1996


























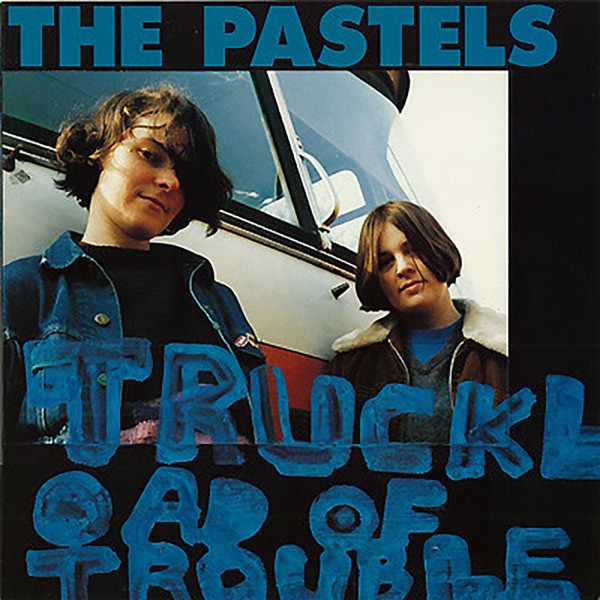


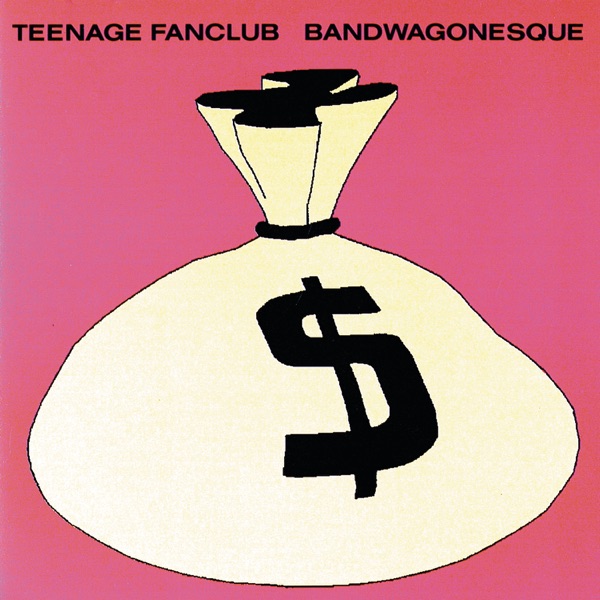







.jpg)














