ゴダイヴァ夫人ついて
ベルギーの世界的なチョコレートメーカー「Godiva」のブランドネームの裏には、英国のコヴェントリーの修道院に端を発する古い伝説と民間伝承が潜んでいることをご存知の方は少なくないと思われる。
この「Lady Godiva」なる物語は、およそ11-13世紀に最初のストーリーが生みだされ、現在でも数々の写本が現存しているのだという。その始まりは、コヴェントリーの修道院の聖職者がこの物語の原本を元にストーリを作製したのだ。
なんとも、ミステリアスな雰囲気が込められているこのゴダイヴァ夫人の物語については、大まかに言えば、英国、コヴェントリーの農民たちに重税を貸していた領主レオフリック伯爵への民衆の怨恨がいやまさるばかりであったため、妻のゴダイヴァ夫人が一肌脱いで、コベントリーの街を乗り物で裸で走り回るという話の筋が伝説として伝えられている。そして、これがベルギーのGodiva社の社名のルーツとなっている。
そして、この英国のコヴェントリーに伝承されているゴダイヴァ夫人伝説は、アラビアン・ナイトのように、ある原作を元にして、後に、様々なサイドストーリー、挿話のようなものがいくつも付け加えられ、原作に話にだんだん尾ひれがついていき、現代に伝わる伝説は原初の話よりも粗筋がずいぶん大げさになっている。
それにとどまらずヨーロッパの美術の彫刻、版画の題材にも、このコヴェントリーの伯爵夫人のテーマがいくつか選ばれている。
つまり、「ゴダイヴァ夫人の伝説」はミステリアスな憶測を呼び、学術研究の対象ともなっているようである。英国を始めとするヨーロッパのストーリーマニアにとっては常に「Lady Godiva」は謎に包まれていて、その実在、真実性に対する好奇心を掻き立ててやまぬようである。
このレディ・ゴダイヴァ伝説というのはいかなる物語なのか?? それを以下に詳述していきたい。
1.伝承と実在
まず、このゴダイヴァ夫人は実在する人物だということは、おおよそ、現代の伝承研究者の間で認識が一致している。
このゴダイヴァ夫人伝説について知る方、または、美術彫刻でこのゴダイヴァ作品について触れたことがおありの方は、まず「Lady Godiva」というと、裸体の夫人、身体を覆うほどの長い髪をイメージするはずである。
実際、この夫人は、いくつかの絵画、版画、彫刻の作品に15世紀から登場するようになった。伝説というのは、常に、その話自体、架空のものか実在のものか判別がつきがたいゆえ、多くの芸術家の題材として選ばれ、創作のモチーフにもなっているのである。
まず、Godivaは、古英語名、”Godgyu”、”Godgifu”(神の贈り物、良い贈り物の意)がラテン語に転訛された形式だという。
Godgyfuは、11世紀のアングロサクソン人の貴族であったといい、 その生涯は英国史上最も劇的なものであったと伝えられている。Godgyfuという人物について知られていることは、様々な宗教にまつわる年代記、「Domesday Book」として知られる編集物にその記述が見られる。
Godgyfuについての信頼性のある最初の資料記録は、1035年に記された書物に見られる。書物名は不明だが、この書物には、彼女が、既にメルシア伯爵のレオフリックと結婚していたという記述が見られる。
ゴダイヴァ夫人の生年月日については不明であり、また、同様に、裸でコヴェントリーの街を通過したとは書かれていない。
ゴダイヴァ夫人が実在したことについては、ほぼ疑いないというのが現代のヨーロッパの史実家の見解としては一致しているようだが、この「Lady Godiva」のハイライトともいえるワンシーン、コヴェントリーの町中を馬車で走り回ったという史実、及び、それにまつわるサイドストーリー、町中でひとりだけゴダイヴァの裸を見てしまった「覗き屋トム」についての記述も公的な資料には登場しないそうである。
そもそも、コヴェントリーは、ゴダイヴァ夫人が実在した時代、総人口、500人ほどのささやかな規模の村であったらしく、そもそも、馬のような乗り物で豪快に走り回ることなど不可能であったという現代史実家の鋭い指摘もなされている。
こういった心楽しい、ストーリーキングのような挿話については、後になってコベントリーの修道院の宗教家によって付け足された「創作」であるというのが通説となっている。
また、このゴダイヴァ夫人について言及される最初の年代記には、ゴダイヴァ夫人とレオフリック伯爵が、コヴェントリーの修道院建設費用を寄付したことが明確に記されている。
つまり、ここに、ささやかな一村の領主として見本のような夫婦であったという事実性が最初の資料から引き出されるのである。
2.コヴェントリーとゴダイヴァ夫人の宗教における関係性
他のアングロサクソン人の同じ階級にある女性と同様、ゴダイヴァ夫人は彼女自身の権利において財産を所有し、 両親からの土地や財産の相続、親戚からの相続、また、土地の交換、購入を元に、土地財産やコミュニティーにおける宗教基盤を築き上げた。
この事実から推察されるのは、当時の英国社会において、土地や財産だけでなく、盤石な宗教基盤を持つ事がそのまま上流階級におけるステータスとなり、他の領地の上流階級の人々に地位を誇示する「政治力」に繋がったということである。さらにまた、ゴダイヴァ夫人の所有するコヴェントリーの農村の領地も、彼女の欠かさざる資産であったことが伺える。また上述した「Domesday Book」には、彼女の死から20年後、69もの大親族があったと記述が見られる。
ゴダイヴァ夫人とレオフリック伯爵が、コヴェントリーの土地の保有に興味を示した理由については未だ明らかにされていない。史実としてみれば、当時、コヴェントリーは、当時、小さく、目立たない、農業コミュニティーに過ぎなかったという。早くも、1024年になると、宗教的な基盤が形作られていき、コヴェントリー大司教(後のカンタベリー大司教)が、レオフリック伯爵に貴重な宗教的な遺物が遺贈された。これは、ローマの司教によって購われた「聖アウグスティヌスの腕」の塑像であった。
最初のゴダイヴァとレオフリックの目論見は、このローマ司教からの遺贈物を収容するなんらかの聖域を設けたいということにあった。既に、1043年には、カンタベリー大司教により、聖マリア、聖オスバーグ、オールセインツのベネディクト会修道院が財産として捧げられた。聖オスバーグの院は、銅と金で装飾された豪華絢爛な装飾のほどこされた建築である。
ここに、当時のコヴェントリー大司教から遺贈された聖遺物「聖アウグスティヌスの腕」が安置されることになった。
また、ゴダイヴァ夫人とレオフリック伯爵は、新設された修道院に金銀、宝石と言った装飾品を惜しみなく寄贈したことで資産家として有名となった。その他にも、ゴダイヴァ夫人とレオフリック伯爵は、ウォリックシャー、グロスターシャー、レスターシャー、ノーザンプトンシャー、及び、ウスターシャーの不動産を修道院に対して寄付を行った。
 |
| セイントメアリー・ストウ教会 |
特に、セイントメアリーズ・ストウは、英国に現存する教会建築の重要な基礎を持つとして歴史的に意義深いものであるという。
この最初期の修道院建築の礎となっている石細工は955年のもので、ゴダイヴァとレオフリックは建築の材料となる素材を惜しみなく提供している。
この建築の顕著な特徴は、サクソン人とデーン人の持つ建築形式が混淆したようなものであったと思われる。
堂内には、4つの丸みを帯びたアーチの形式が見られ、このアーチ式の石柱には、10世紀から11世紀の古い船の落書きが引っかき傷で描かれているという。これは近くのトレントという土地を航海したデンマーク人の襲撃を徴したものであろうとの指摘がなされている。
3.レオフリック伯爵の足跡
伯爵のレオフリックは、かなりの才能、政治家としての力量も具備していた。そもそもこれらの資質がなければ、当時の英国社会で伯爵として生き残ることは不可能であったと言われている。
1017年にデーン・クヌートによって伯爵の称号を得、彼はクヌートの治世にかけて繁栄を続けた。その後、ハロルド一世(1035−1040)の世が続き、クヌート一世の後継者を選ぶ必要があった。
クヌートのもうひとりの息子、ハーダナグットは次の世を継ぎ、さらには、この夫人と伯爵と深い関わりを持つエドワード懺悔王(1042-1066と呼ばれる人物がこの地を支配した。
人間というのは、権力をひとたび手に入れると、それをなんとしてでも我が手におさめつづけようと躍起になる。それは、蛇足となるが、失うことの恐れから何かを増大させようとするのである。もちろん、それはこの伯爵についても同様だった。年をへるごとに、レオフリック伯爵は、深い信仰心を持つに至る。
伯爵の信仰心の対象は、修道院の豪華絢爛な装飾を施した石造建築、あるいはコヴェントリーの領地での権勢、伯爵としての地位の堅持に注がれるようになった。(これは日本中世でも同じような例が見受けられるはずだ)
伯爵の権力の保持、また、資産の増大への指針。つまり、その割を食らったのが、コヴェントリーの領民であった。
既に、1041年には、レオフリック伯爵は、この地の農民らに重税を課しており、それが原因で、多くの領民たちが困窮にあえいでいたというのは、「Lady Godiva」の伝説の物語の中核をなし、また、この物語の最初の起承転結の起こり、話の出発の部分をなしている。
1041年のこと、ハーダグナットが王位にある時代、彼の徴税人二人が、ウスター市民は過大な課税に怒り狂った集団により殺害される。
*この事件に際して、夫に対して重税を民衆に課すのをとりやめさせようとするゴディヴァ夫人が孤軍奮闘し、コヴェントリーの町中を裸体で馬にまたがり駆け巡ったという物語が生み出されたのだろうと思われる。
また、この物語が修道院(それがイギリスであれ、ドイツであれ、フランスであれ、それがまたアッシリアであれ、各地の、中世の修道院に類する建築内には、必ずといっていいほど、祈祷をする場所とともに、浩瀚な書籍を所蔵した文庫と呼ばれる空間が建築中に組み込まれている)から生み出されたというのは、修道士が自らの属する修道院の建設者レオフリック伯爵とゴダイヴァ夫人に対して、何がしかの返報をしたいと考え、その考えを美麗な物語「Lady Godiva」」によって原本や写本を元に、複数人の著者に引き継いで完成させたというのがもっともらしい推察かもしれない。つまり、これは聖職者たちの報恩のストーリーといもいえなくもない。
当時の英国社会では、王の擁する代表者に対する狼藉は、無論、あるまじきご法度であった。この事件を受けて、報復を行うべく、ハーダクナット王は、レオフリック伯爵に依頼し、ウスターに廃棄物を置くことを命じたという。
王の命をレオフリックは恐ろしい効率で進めていき、もともとウスターは大聖堂を抱える美しい都市であったがため、民衆から相当な非難を受けた。しかし、その後、レオフリック伯爵は、この騒動を押さえつけるため、多くの宝飾品を聖堂に寄付をおこなったことにより、彼自体はそれほどの罵倒や論難を受けることはなかった。
レオフリックはこのことで、伯爵としての盤石な地位を確立する。彼の人生の終わり近くには、ウスター後の修道士によって注意深く記録され、1057年、レオフリックの死後になって出版された。
「・・・この同年の10月30日、レオフリック伯爵は亡くなられました。彼はこの国全てに利益をもたらし、宗教および聖俗的なすべての事柄において賢明な決断をお選びになりました。彼はコヴェントリーに埋葬され、息子のエルフガーは彼の権威を引き継いだのです。
4.ゴダイヴァ夫人の晩年
彼の死後、ゴダイヴァ夫人は、ウスターの宗教財団に追加の寄付を行い、レオフリック伯爵の魂の休息を設けることにより、彼女自身の利をはかった。これらの寄贈品の中には、祭壇の正面、壁掛け、ベンチカバー、ローソクの芯、聖書などが含まれていた。レオフリックの死去する前の数年間からウスターに寄贈した品物や財産の長い目録が、伯爵の寄贈品の上に加えられた。
ゴダイヴァ夫人は、記録によれば、1067年に亡くなっている。彼女の死後、ゴダイヴァ夫人は、イギリス国内で最も裕福な五人のひとりに数えられるほどで、およそ160ポンドの銀の価値に相当する資産を所有していたと伝えられている。
その後、彼女の保有していた土地は新しい王、ウィリアムによって没収されたという。ゴダイヴァ夫人は、その後、夫のレオフリック伯爵が建築したコヴェントリー修道院教会で夫の隣に埋葬された。マルムズベリーのウィリアム氏によれば、彼女の死にゆく行為は非常に敬虔的であったという。
最後の修道院への寄贈品として、ゴダイヴァ夫人は、聖母マリア像の首に、宝石のネックレスをかけるように命じた。
この教会は、残念ながら、現在、ゴダイヴァ夫人の生きていた時代の原型は残っていないらしく、カルバン主義の宗教改革が発生した時代に破壊され、宝石物も略奪され、この教会内におさめられていた聖遺物は分散した。ともに、ゴダイヴァ夫人の伝説もまた真実の行方が定かならぬものとなったのだ。いずれにせよ、ゴダイヴァ夫人伝説はまだまだ史実として調べる余地があり、きわめてミステリアスなベールによって覆われている。
こちらの記事もぜひご一読ください:
LIMINAL SPACE-リミナルスペース- 現実空間と異空間の狭間











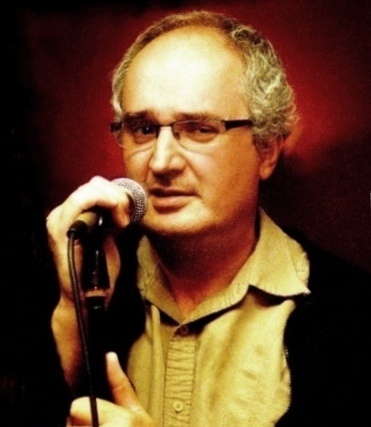













.jpg)














