Steve Tibbetts
スティーヴ・チベッツは、アメリカのギタリスト兼作曲家。アートスクールに在学していた時代からギターの多重録音に夢中になり、その後、ドイツのECMと契約を交わし、これまで多数の作品をECMからリリースしている。
スティーヴ・チベッツは、レコーディングスタジオをサウンドを作成するためのツールとみなしている。チベッツの楽曲は、ニューエイジ、アンビエント、ワールド・ミュージック、実験音楽と、幅広いサウンドの特徴を持つ。
特に、チベッツの楽曲性として顕著なのは、ギターの多重録音である。複雑なループディレイ、ディケイのサウンド処理を施した録音の素材を幾重にもダビングさせ、独特なミニマル色の強いギター音楽へ昇華する。彼のギター演奏が特異なのは、ライブの演奏のためでなく、それをレコーディング、完成されたプロダクションのためにループエフェクトをプログラミングとして用いていることである。
スティーヴ・チベッツは、自身の楽曲について「ポストモダンのネオプリミティヴィズム」と称している。ギターのチョーキングを駆使し、周囲のサウンドスケープと電気的な歪みを交互に繰り返しながら、インドの民族楽器”サーランギー”のようなサウンドを生み出す。 また、スティーヴ・チベッツはギターの他に、ケンダンやカリンバといった民族楽器を演奏することでも知られている。
 |
| 1999 Choying and Steve, Walker Art Center |
Steve Tibbettsの主要作品
・「Northern Song」1981

スティーヴ・チベッツの最初期の名盤として挙げられる。1981年のノルウェー、オスロでエンジニアにヤン・エリック・コングショーマンを迎えて録音が行われた作品。彼のアコースティックギタリストとしての才覚が花開いたECMと契約を結んで最初にリリースされた作品である。
このスタジオ・アルバムで、スティーヴ・チベッツこれまでのアコースティックギターの可能性を押し広げている。
弾くというより、撫でるような繊細なギターのフィンガーピッキングの演奏に加え、詩的でナチュラルなアコースティックギターの演奏を堪能できる作品。チベッツは、フォーク音楽の革新性をワールド・ミュージック寄りのアプローチを行うことにより、楽曲をアンビエントに近い領域まで推し進めている。
1981年という年代には、ギターアンビエントというジャンルが存在しなかったはずだが、その音楽性をここでスティーヴ・チベッツは世界で初めて取り入れていることに驚かずにはいられない。
スティーヴ・チベッツの生み出すギター音楽は、瞑想的であり、沈思的であり、独創性に飛んでいる。最後に収録されている「Nine Doors/ Breaking Space」は、ギター演奏のミュートのニュアンスを徹底的に突き詰めていった民族音楽の色合いが強く引き出された楽曲であるが、それと同時に、Fenneszのようなアンビエントギターを世界に先駆けて発明した伝説的な名曲でもある。
・「Safe Journey」 1983

上記の「Northern Song」が、もしかりに地ベッツのアコースティックギタリストとしての傑作だとするなら、「Safe Journey」はエレクトリックギタリストとしての名盤として挙げられる。
この作品においてチベッツは、エレクトリック・ギターのテープループを用いた多重録音、コンガ、カリンバ、スチールドラムといった民族音楽をリズム的に取り入れることにより、これまでに存在しなかった電子音楽寄りの民族音楽を生み出している。
このアルバムでのスティーブ・チベッツの速弾きのテクニックは、ハードロック色を感じさせる熱狂性が込められていることはよく指摘される。これは「The Fall of Us」から突き進めてきたエレクトリックギタリストとしての完成形、究極形が提示されている。
特に一曲目の「Test」では、ヴァン・ヘイレン、ヘンドリックスに引けを取らない凄まじいギターテクニックがインドの打楽器タブラとともに狂乱的に繰り広げられる様はほとんど圧巻というよりほかない。その他にも、「Version」「Any Minute」といった民族音楽の色合いが強い独特な楽曲が収録されている。彼の作品の中では特に民族音楽の性格が絶妙に引き出された作品である。
・「A Man About A Horse」2001

スティーヴ・チベッツの作品の中では、最高傑作のひとつに挙げられることが多い作品である。
アルバムジャケットの海に釣り上げられたバクバイプが燃やされた象徴的なアートワークも衝撃的であり、実際の音楽性についても独特や特異といった性質を越えた前衛音楽をスティーヴ・チベッツは生み出している。これまで、アフリカ、インドといった様々な民族音楽を取り入れてきたチベッツは、この作品において、自身の活動名の由来であるチベットの宗教音楽へと踏み入れている。
「A Man About A Horse」には、チベット地域の宗教音楽を特異なアンビエンスとして取り入れた楽曲が数多く収録されている。マントラをはじめとする、チベット高地発祥の宗教音楽を、アンビエントという側面から西洋的解釈を試み、そこに彼らしいギター音楽に昇華した作品である。
「Burning Temple」に代表されるように、東洋と西洋の概念を融合させたような楽曲がこのスタジオ・アルバムには多数収められており、アンビエント音楽とチベット密教の宗教音楽を融合させた静謐な楽曲群は、これまでにないジャンルがこの世に生み落とされた瞬間と言えるかもしれない。「A Man About A Horse」に収録されている楽曲は当時、ニューエイジという名で呼ばれていたようだが、そういった枠組みで収まりきる音楽ではなく、精神的な音楽といえる。
また、最終曲の「Koshala」での、静と動、緩急をまじえた楽曲、最終盤部でのタブラの狂気的なパーカッション、チベットボウル、ほとんど鬼気迫る勢いで繰り広げられるギター演奏のミニマリズムがかけあわさることにより,独特な内向きの渦のような凄まじいエネルギーが生み出される。
2002年というリリースされた年代を考えると、「A Man About A Horse」は、虐げられるチベットの民族、それから、チベット密教へのギター音楽を通しての「精神的な讃歌」ともとれなくもない。
・この作品の他にも、Steve Tibbettsがチベット仏教の尼僧Choying Drolmとコラボレーションを行った1997年の「Cho」では、Nagi寺院の尼僧たちのチベット語による美しい歌声を聴くことが出来る。
昨今のチベット・ウイグル自治区の情勢を鑑みると、今後、重要な歴史的資料ともなりえるかもしれない。
チベット周辺の文化の研究を行っている方には、密教のマントラのミュージックライブラリーと合わせて是非聴いてみていただきたい作品である。「Cho」は、Rikodiscというワーナー傘下のレーベル”Rhino"からリリースであるため、ここでは、取り上げないことをお許し願いたい。






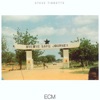

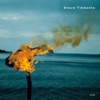












.jpg)














